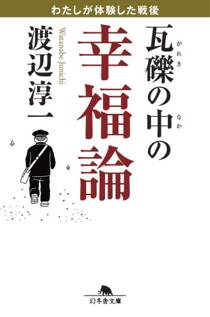太平洋戦争のただ中を生き抜いた作家・渡辺淳一が、自らの記憶をたぐり寄せ、人生の根底を形作った「戦後」を語る。生きる重さと希望を問い直す珠玉の回想録『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』より、一部を抜粋してお届けします。
* * *
日本が戦争に負けた日、昭和20年(1945年)8月15日、わたしは小学校6年生だった。
そのとき、わたしは札幌の西郊、山の手に近い円山という土地に住んでいて、家族は父と母と姉と弟とわたしの5人で、父は市内の高校(当時は旧制中学)の教師、姉は女学生、弟はまだ5歳であった。
玉音放送
この日、敗戦の日は水曜日だが、夏休みの最中であったかと思う。
しかし父と姉は家にいなくて、わたしは自宅で母と二人で放送を聞いた。
当時、天皇陛下の生のお声を聞くことはまったくなく、それだけに陛下の声は玉音といい、聞くのも畏れ多いことだと教えられていた。
やがて正午近く、母が茶の間のラジオの前に座ったので、わたしもその横できちんと正座をして聞いた。
しかし初めの、「朕深く世界の大勢と……」というところだけは聞こえたが、そのあとは抑揚が激しく、さらに陛下のお声がきんきんとした感じで、ほとんど聞きとることができなかった。
口語に直すと
ここで陛下の玉音放送とはどういうものであったのか。今改めて再現してみたいと思うのだが。
朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ
ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ
陛下のお言葉は詔勅のような公用文になると、段落を示す初めの字下げはなく、さらに途中の句読点もくわえないことになっていたようである。
またここでいう、米英支蘇とは、ポツダム宣言に署名したアメリカ、イギリス、中国、ソ連の四カ国のことをさしている。
このあと、詔勅では歴代天皇は日本国民の平穏無事と世界繁栄の喜びをともにしたいと願ってきたことであり、先に米英二国に宣戦したのも、日本の自立と東アジア諸国の安定を願うが故におこなったことである、と開戦に至った経緯を述べている。
しかし交戦四年を経て、我が陸海将兵は勇敢に戦い、一億国民は無私の気持ちから最善を尽くしたが、戦局は必ずしも好転せず、世界の大勢も我が国に有利となっていない。
くわえて敵は新たに残虐な爆弾(原爆)を使用して、無辜の人々を大量に殺傷し、このままでは被害がどこまで及ぶのかまったく予測ができないまでに至った。
このような状態で戦争を継続したのでは、我が民族の滅亡を招き、人類の文明をも破壊しかねない。
このような状態に至っては、私はいかに多くの愛する国民を守り、代々の天皇の御霊に謝罪したらよいのか。これこそ熟慮の末、共同宣言を受諾するよう下命するに至った理由である。
私は日本とともに東アジア諸国の解放に協力してくれた同盟諸国に対して、遺憾の意を表せざるをえない。
日本国民で、前線で戦死した者、公務にて殉職した者、戦災に倒れた者、さらにその遺族の気持ちに思いを寄せると、我が身を引き裂かれる思いである。
今後、日本の受けるべき苦難は並大抵のものではなかろう。しかしながら、私は時の巡り合わせに逆らわず、「堪えがたきを堪え、忍びがたきを忍び」未来永劫のために、平和な世界を切り開こうと思うのである。
私はここで国としての形を維持しうれば、善良なる国民の真意を拠りどころとして、常にあなたがた国民とともに過ごすことができる。もし誰かが感情の高ぶりから、むやみやたらに事件を起こし、そのために進むべき正しい道を誤って、世界の国々から信頼を失うようなことは、私がもっとも深く憂慮するところである。
ぜひとも誇るべき自国の不滅を確信し、責任は重く、かつ復興への道のりは遠いことを覚悟し、総力を将来の建設に傾け、国のあるべき姿の真髄を発揚し、世界の流れに遅れをとらぬよう努めて欲しい。あなたがた臣民みな、この朕の気持ちをよく理解されるよう願っている。
なにかほっと
いま改めて、原文を口語訳にして読むと、陛下がいかに国民のことを案じ、大変な結論に達したか、よく理解することができる。
とくに文中、括弧で囲んだ、「堪えがたきを堪え、忍びがたきを忍び」は、その後、多くの人々が復唱し、心に染み込ませた言葉であった。
ところで、わたし自身はこのお言葉を聞いてどう思ったのか。
初めに記したとおり、よく聞き取れなかったし、お言葉自体はいわゆる文語体でもあったので、よくわからなかったのが、正直な感想である。
しかし、日本が戦争に負け、これで戦争は終わったのだ、ということだけはわかった。
それというのも、この前日、15日に重大発表がある、と知らされたときから、日本がアメリカに降伏するのだということは、噂で知らされていたからである。
そのことを改めて知り、わたしは子供心に、なにかほっとしたというか、安心したような気持ちにとらわれたことはたしかである。
一方、このとき、母はどんなふうに思っていたのか。放送を聞き終えると、母は無言のまま立ち上がって家事に戻り、弟はもう外で遊んでいたようである。
あとで知ったことだが、このあと軍関係者の一部は悲憤慷慨して、皇居前で割腹自殺した人までいたようだが、我が家も家のまわりも、いつもの夏の午後と変わらず、なにごともなかったように静まり返っていた。
* * *
この続きは書籍『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』をお求めください。
瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後
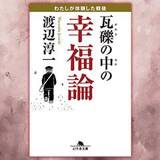
太平洋戦争のただ中を生き抜いた作家・渡辺淳一が、自らの記憶をたぐり寄せ、人生の根底を形作った「戦後」を語る。生きる重さと希望を問い直す珠玉の回想録『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』より、一部を抜粋してお届けします。