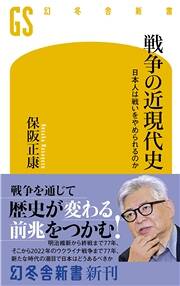世界情勢が揺らぐ今、日本はどこに向かうのか?
ノンフィクション作家・保阪正康さんが、明治から昭和に至る戦争の歴史を解きほぐし、これからの私たちにできることを問いかける幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』より、一部を抜粋してお届けします。
軍人はまず「戦争を避ける」という前提
私は20世紀の戦争を調べていて、「軍人は本来、戦争をしないために存在する」ということが、だんだんわかってきました。
アメリカの軍事関係の英文資料を、辞書を引きながら読み進めると、20世紀のアメリカの軍人のなかには「いかに戦わないか」を前提に「戦略論」を考えている層が存在します。それが本来は健全なのでしょう。
戦略論は「戦争が始まれば、いかに勝つか」ということですが、「いかにして、軍人は戦わないようにするか」という点もきちんと考えていたのです。文民支配下の軍人が持っていた戦争哲学には、まず「戦争を避ける」という前提があった。その点からすると、2つの世界大戦は彼らにとって、不本意なものだったはずです。
第一次世界大戦も第二次世界大戦も、民主主義を守るというテーゼの下に、アメリカはイギリスやフランスなどの連合国軍側について戦いました。言い換えるならば、アメリカの青年は民主主義というイデオロギーに命をかけたことになります。
国民の生命や財産に直接関係する危機であれば、もはや対外戦争は避けられません。それ以外の理由で戦争に動員するのであれば、アメリカの青年を納得させて戦わせるだけの戦略論がなければいけない。これがアメリカの軍人の考え方だと思います。
しかし2度の世界大戦では、「民主主義を守る」というだけでアメリカは戦争を始め、多くのアメリカの青年を失ってしまいました。元軍人の回顧録には、「これは残念なことだった」という記述がしばしば出てきます。
アメリカの冷静なグループの軍人たちが考える戦争目的は、政治家のルーズベルトやチャーチルとは必ずしも同じではないのです。ルーズベルトやチャーチルは、政治で話がつかないから、政治の代替として軍事力に訴えて戦争に踏み切りました。しかし、「いかに戦争をしないか」というアメリカの軍人の教えから読み取れるのは、戦場での勝ち負けを超えたところにある戦争哲学です。
戦争の泥沼化と、失われたアメリカの軍事論
しかし、ベトナム戦争以後、「戦争をしないための軍事論」は完全に崩壊しました。「共産主義と戦う」「テロ国家と戦う」というテーゼのために、20世紀から21世紀にかけて、アメリカは多くの青年を戦場に送って戦死させました。これらは、あくまで政治の代替としての戦争でしかないのです。
第二次世界大戦では、何十万人もの兵隊が殺し合う結果となり、相手方を全面的に屈服させる戦争をすれば、果てしない泥沼に陥ることが教訓として残りました。ヒトラーを倒さなければならないのなら、全面衝突を極力回避し、ナチスドイツ内でヒトラーに反対するドイツの軍人たちと連携する作戦を模索するのが本当の戦略だ、ともアメリカの軍人の残した戦争史には書いてあります。
また、「独ソ戦に干渉せず、両方に戦争させておけばよい。ナチズムとコミュニズムが戦って、両方が消耗したときにアメリカが出ていき、戦争を止めるということで、戦争の要因を除去する」という戦略も考えられたと言いますが、これは「要因を除去する」ことが軍事の役割と想定された節もあります。
そういう「勝利の計画案」を、密かにアメリカの軍人は作っていましたが、日本が真珠湾を叩いて、いきなり全部否定されたために、アメリカは、「日本に勝つ」「ナチズムに勝つ」ということが戦争目的になってしまいました。そのために、戦争が悲惨さを帯び、相手を抹殺する戦争になってしまった。それは軍人が本来役割とする立場と異なると、彼らは言っています。
明確な戦争目的を持たずに戦争をしていた日本
また、「日本の軍隊は精神主義的な軍隊だというが、そうとは思わない。指導者不在の戦争をやると、日本のような乱暴な戦争になる」と、アメリカの元軍人たちはよく書き残しています。
指導者不在であると同時に、日本の軍には戦争目的がなかったと、私は考えます。「大東亜共栄圏の確立だ」「政治が失敗して石油がないので、政治の代わりに戦争をやっている」と日本の軍人は言うのですが、大東亜共栄圏も自存自衛も戦争目的ではない。明確な戦争目的を持たずに、日本は戦争をやったのです。
アメリカの軍人の戦争目的は、前述したように「戦争の要因を除去する」ところにありました。マッカーサーが日本を占領したとき、その戦争目的を占領目的に置き換えました。つまり、「民主化することによって戦争の要因を取り除き、二度とアメリカに刃向かってこない国にする」ということです。
しかし、アメリカ、イギリス、あるいはドイツにもあったのですが、「軍人は本来、戦争しないことが役目である」という考え方が、歴史の表面上に出てくることはありませんでした。ですが、アメリカの軍人教育に、そうした戦略論があったことだけは知っておくべきだと思います。
* * *
この続きは幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』をお求めください。
戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか
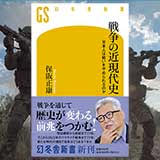
世界情勢が揺らぐ今、日本はどこに向かうのか?
ノンフィクション作家・保阪正康さんが、明治から昭和に至る戦争の歴史を解きほぐし、これからの私たちにできることを問いかける幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』より、一部を抜粋してお届けします。