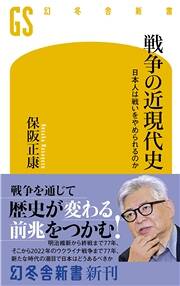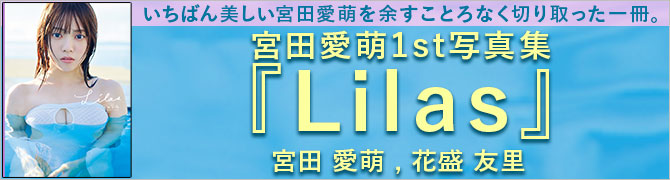世界情勢が揺らぐ今、日本はどこに向かうのか?
ノンフィクション作家・保阪正康さんが、明治から昭和に至る戦争の歴史を解きほぐし、これからの私たちにできることを問いかける幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』より、一部を抜粋してお届けします。
軍部が権力を握り、天皇を利用した
昭和の戦争で大きな問題になるのは、戦争指導者の責任です。これは天皇も含めてですが、ときの軍事指導者、政治指導者の責任問題です。ただし、天皇に戦争責任をすべて負わせるのは極めて無責任だと、私は考えています。天皇親政ならば、その論理は成り立つでしょう。しかし、天皇は飾りのような存在であり、実質的な権力を握っていませんでした。
実質的な権力を握っていたのは、軍部です。軍事の優先性が憲法で保障されていないのに、軍部は権力を掌握して、一方的に政治を従属させた。そして、国策に反する戦争を遂行し、「勝った、勝った」と喧伝しながら負け戦を続けていたのです。
さらに言えば、「天皇のために死ね」という軍国教育があったという常識化した見方も、疑問符を付けて受け止めるべきだと思います。「神武天皇以来の皇国の歴史をより輝かしいものとするために、命を捨てなさい」と軍国教育では教えたと言いますが、これは昭和天皇が望んだものではなく、軍の戦略の不備を隠蔽するために、軍人たちが天皇を利用して使った言葉だということを、私たちは理解しておくことが必要です。
与えられた役割の中で懸命に生きた人々
そして現代日本人に問いかけたいのは、誰もが時代を選択して生まれてきたわけではありませんから、「この時代にめぐり合わせた人たちの人生をどう思うか」という視点です。
昭和の戦争の時代を生きた一般の人たちは、与えられた役割のなかで懸命に生き、戦争に行って、死んでいった。彼らに対して、「あなたたちは侵略の軍隊だ」と決めつけるのは一方的だろうと考えます。
後から見て全否定するのは簡単ですが、それはある意味で思考停止した態度だと言えます。彼らの姿から、私たちは何を学ぶべきか。そこから教訓を得ることで、彼らがたんなる過去の歴史上の人間ではなく、私たちが今まさに刻み続けている歴史のなかで生きてくると思うのです。
「二度と戦争なんか嫌だ」という思いが、憲法九条に凝縮している
一つの象徴的な話を紹介しましょう。
日本火災海上保険(現・損害保険ジャパン)の会長を務めた品川正治という人がいました。すでにお亡くなりになっていますが、彼の著書『戦後歴程』(岩波書店)を読んだとき、なるほどと思いました。
大正13年(1924)生まれの品川は、旧制三高の学生だったときに徴集され、中国戦線に行きます。戦地では行軍ばかりしていた思い出が書かれていますが、戦争が終わると中国側の捕虜収容所に入れられ、昭和21年(1946)に日本へ帰りました。
品川は帰国船のなかで、新聞を手に取ります。ちょうど憲法が発布される頃で、新聞には憲法の草案が紹介されていて、そこに記された憲法九条に驚いたのだそうです。
そして、上官から「部隊の全員の前で読め」と命じられ、前文から読んで聞かせました。読み終わると、兵隊たちはみんな泣いていたと、品川は回想します。
「もう二度と戦争なんか嫌だという思いが、この憲法のなかに凝縮している」「我々がこの憲法を作ったんだ」「死んだ仲間もこの憲法を作ったんだ」。そういう趣旨のことを、品川は書いています。
大企業の経営者には、だいたい保守派の改憲論者が多いですが、品川はいわゆる護憲派でした。しかし、これは「護憲派」「改憲派」という問題ではなく、今の憲法九条には戦場の辛酸を乗り越え、ようやく内地に帰還する兵士たちの思いが凝縮されていることを指摘したいのです。
「凝縮されている」というところが大事です。昭和の戦争を見るときに、現場で戦った兵士たちは誰もが「二度と戦争は嫌だ」と言います。
戦争を知る世代の自民党の代議士に何人も会いましたが、タカ派的な意見の人でも、「今の憲法でよいと思う。あれは死んだ人たちの魂がこもっているのだ」と話す人が少なからずいました。
「戦死した兵隊たちがあの憲法を作った」と思う世代の人たちが、たしかにいるのです。そういう人たちは今、時間の経過とともにほとんど亡くなっています。直接当時の兵隊たちのメッセージが伝わることのない時代になっていますが、今の憲法九条が兵隊たちの涙で出来上がっていることは、知っておく必要があると思います。
* * *
この続きは幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』をお求めください。
戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのかの記事をもっと読む
戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか
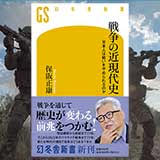
世界情勢が揺らぐ今、日本はどこに向かうのか?
ノンフィクション作家・保阪正康さんが、明治から昭和に至る戦争の歴史を解きほぐし、これからの私たちにできることを問いかける幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』より、一部を抜粋してお届けします。