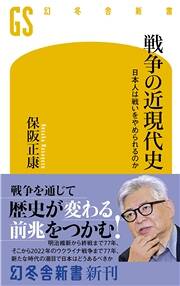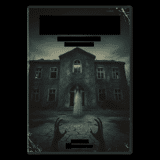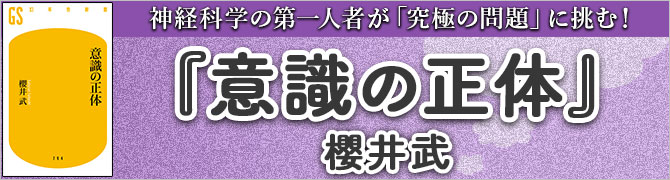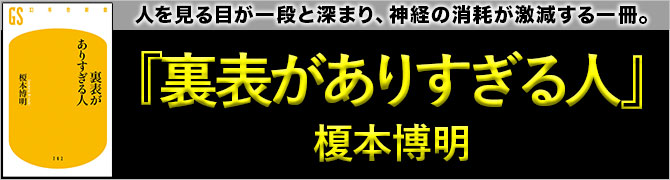世界情勢が揺らぐ今、日本はどこに向かうのか?
ノンフィクション作家・保阪正康さんが、明治から昭和に至る戦争の歴史を解きほぐし、これからの私たちにできることを問いかける幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』より、一部を抜粋してお届けします。
日清戦争で勝利し軍事力強化の道へ進む日本
清国の兵隊と朝鮮半島で戦った日清戦争は、清国の士気が低く、日本軍は清国軍を破り、至る所を軍事的に制圧していきました。
昭和55年(1980)頃、日清戦争に従軍した元兵士の話を聞いたことがあります。
当時は一部で銃撃戦があったとしても、ほとんどが白兵戦でしたが、中国の兵隊は100パーセント逃げたと言うのです。「どうしてこんなに戦わないのだろうと、私たちは不思議でした」と、その元兵士は言っていました。
一方で日本兵は清国軍に捕まってしまうと、どのような運命をたどるかわからないと恐怖感に襲われ、必死に戦ったのです。
また、清国が撃った大砲の弾がほとんど爆発しなかったという話があります。日本の将校が調べたら、砲弾には火薬でなく砂が入っていた。それは西欧の武器商人たちから買ったものらしく、中国はそこまで侮られていたと言っていいでしょう。
砂の入った砲弾は、直接当たらなければ死ぬことはありません。いくら弾が飛んで来ても怖くないから、日本兵は恐れずに前進し、清国の兵隊はみな逃げ散ったのです。
また清国軍には急ごしらえの徴用兵が多かったのに対し、日本軍は練度でまさっていたことも戦況を大きく有利にしました。日本軍は朝鮮半島から清国軍を追い払うことに成功し、黄海海戦などで清の北洋艦隊にも完勝し、明治28年(1895)4月、下関条約が結ばれて講和が成立します。
清国は朝鮮独立を承認させられ、台湾、遼東半島の割譲と、2億両(約3億円)の賠償金を支払うことになりました。しかし遼東半島は、ロシア・ドイツ・フランスの三国干渉によって清への返還を余儀なくされ、日本は「臥薪嘗胆」をスローガンにさらに軍事力強化に邁進します。
日露戦争でも勝利し、日本は軍事が主導する国家へ
日清戦争から10年後に起きた日露戦争は、明治33年(1900)にかけて起こった北清事変(列強の進出に反発した中国民衆の排外運動。義和団事件とも言われる)鎮圧のためにロシアが満州に進出し、その後も居座り続けたことから、日本は「利益線」を守るためにロシアとの戦争に突き進みます。
このとき、ロシア皇帝は「庭にスズメでも取りに行くようなもので、日本の軍隊はすぐ抑えられる」と言ったといいます。つまり、「ちょっとした揉め事に、本格的な派兵をする必要はない」という感覚でいたわけです。
それは当然の感覚で、ロシアは当時のヨーロッパでも屈指の軍事大国でした。大国ロシアとの戦争は、勝つにせよ負けるにせよ、大変な損害と犠牲が見込まれるため、ヨーロッパ各国は、そう簡単にロシアとの戦争を選択できなかったのです。
ところが、日本は何と戦争に踏み切ったのです。世界中が驚いたのは当然のことで、「日本とロシアのどちらが勝つか」という欧米の勝敗予測の賭け率は、圧倒的にロシア有利でした。まさか、本当に戦争をするとは思えないほどの軍事力の差だったのです。
しかし、日本は陸軍が奉天会戦、海軍が日本海海戦という歴史的な戦いでロシア軍を破り、何とかロシアに勝ちました。しかし勝つには勝ったのですが、アメリカの斡旋によるポーツマス条約で講和が成立したに過ぎず、ロシアは本格的に負けたと思っていません。結局、日清戦争のような賠償金は取れませんでした。
それでも、「勝った」という結果を出したので、「大国ロシアを破った日本はどんな国なのか」と、国際社会からの注目が一気に集まります。アジアの小国によるこの勝利は、西欧の植民地支配を受けている世界の国々の革命家たちをおおいに励ましました。
しかし、勝つことによって、私たちの国は大きな錯誤を犯しました。軍事が主導する国家、軍事がすべてを支配する国家へと走り出してしまったのです。
戦争は「儲かる事業」という錯誤
もう一つ、日本の錯誤を取り上げておきます。日清戦争、日露戦争で「戦争は儲かる事業である」と考えたことです。その結果、戦争がこの国の最大の「営業品目」になりました。戦争に勝って賠償金を獲得し、領土を拡大して制圧した地域の資源を手に入れることが、国家最大の利益を得る方法だと安易に考えてしまったのです。
近代に入ると、帝国主義国の先駆けである西欧列強は、戦争に慎重な姿勢を取りはじめました。政治の下に軍事を置くシビリアンコントロールが一般化し、「政治で話がつかない場合、軍事的に動く」という順番になったのです。戦争はあくまで経済を発展させる「市場獲得」のためのものになり、政治の了解があってから軍事行動を行う形に変化していきました。
ところが、日本はそうはならず、「国家が豊かになるためには戦争をやればいい」、つまり戦争によって国家的な利益が拡大すると考えました。日清戦争と日露戦争を通して、「戦争をすることによって、興産立国、産業立国が実現できる」と覚えてしまったのです。
日露戦争を戦ったのも、国家防衛のために戦うという意味もありましたが、もし勝つことができれば、多くの賠償金を取れると考えたからでした。日清戦争では国家予算の1.5倍もの賠償金を取りましたし、その国が持っている権益を奪って確保できることも「利益」と捉えられました。
博打化した戦争、太平洋戦争の悲劇
こうして一にも二にも「最大の営業品目は戦争」という国に、日本はなったのです。「戦争が国家最大の営業形態」だったのは、20世紀にあっては日本だけです。「敵を倒すためなら悪魔とでも手を結ぶ」と権謀術数をめぐらしたヒトラーでさえも、投下する資本との相関関係のなかで戦争を考え、イギリスやフランスと同じ視点で戦争を位置づけていました。
日本はまず戦争を起こし、資本を次々に注ぎ込んでいきます。勝てば賠償金でまかなえばいいと考えたからです。第一次世界大戦を経験して昭和に入ると、その傾向は一段と強まっていきました。
しかし戦争は、勝たなければ利益はゼロです。それどころか、投じた資金はすべて水の泡となります。だから、勝つまでやるしかない。「営業品目」と言いましたが、要するに博打と同じです。戦争が博打になってしまうという最悪の戦争理論に、日本は傾斜していったのです。
それは3年8カ月続いた太平洋戦争を見れば明らかです。ミッドウェイ、ガダルカナル、連合艦隊司令長官・山本五十六の死、そしてサイパン陥落と、ここまで戦況が劣勢に陥ったら、「日本に勝つチャンスはなくなった」と考えるのが普通です。しかし、軍の指導部は本土決戦を唱えて戦争を続けようとしました。
負けたら天皇制がどうなるかわからないし、国が海外に持っている権益を全部失います。場合によっては、日本本土である4つの島も取り上げられるかもしれません。そういうことを全部含めて、「最後までやる以外にない」となったのですが、まさに「勝つまでやめられない博打」のようだったと言えるでしょう。
この「勝つ見込みのない戦争」を遂行し続けたことも、私は「営業」という視点で捉えています。「他社が完全にマーケットを支配しているところに、なぜ出ていくのか」と言っていたら、営業は始まりません。先行する相手をつぶしながらでも、自社のマーケットを広げていくのが営業活動でしょう。日本の戦争もそういうところがあったのです。
* * *
この続きは幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』をお求めください。
戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのかの記事をもっと読む
戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか
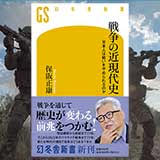
世界情勢が揺らぐ今、日本はどこに向かうのか?
ノンフィクション作家・保阪正康さんが、明治から昭和に至る戦争の歴史を解きほぐし、これからの私たちにできることを問いかける幻冬舎新書『戦争の近現代史 日本人は戦いをやめられるのか』より、一部を抜粋してお届けします。