
社会・教養
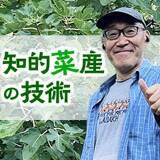

知的菜産の技術、各論編もサクサク進み、大きなところとしては、ナス科、ウリ科、マメ科などを残すばかりとなりました。どれからいってもええのですが、今回はマメ科をば。
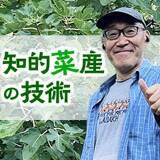
大阪大学医学部を定年退官して隠居の道に入った仲野教授が、毎日、ワクワク興奮しています。秘密は家庭菜園。いったい家庭菜園の何がそんなに? 家庭菜園をやっている人、始めたい人、家庭菜園どうでもいい人、定年後の生き方を考えている人に贈る、おもろくて役に立つエッセイです。

日々更新する
多彩な連載が読める!
専用アプリなしで
電子書籍が読める!

おトクなポイントが
貯まる・使える!

会員限定イベントに
参加できる!

プレゼント抽選に
応募できる!