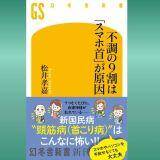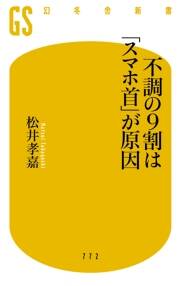不眠・頭痛・意欲低下──その不調、原因は首にあるかもしれません。自律神経失調治療の世界的権威、松井孝嘉先生の『不調の9割は「スマホ首」が原因』は、これらの不調の原因と治療法、日常生活で気をつけるべきことなどを解説した、スマホ時代の必読書。そんな本書の一部を再編集してご紹介します。
* * *
首の不調を防ぐには、日常の習慣を見直すことが大切
頸筋病は、言わば長年にわたって「間違った首の使い方」をしてきたために起きる病気です。
長時間うつむきっぱなしでいたり、スマホやパソコンをずっと使い続けていたり、首を無防備に冷やしてしまったり、首に強すぎる刺激を加えたり……。そういう「首に悪いこと」を習慣的に長年積み重ねてきたせいで首の筋肉が疲弊し、頸筋病の症状に悩まされるようになっていくわけです。これは、乱れた食事や生活習慣を長年にわたって続けていると、いずれさまざまな「生活習慣病」に悩まされるようになっていくのとちょっと似ていますね。
では、いったいどうすればいいのでしょう。
いちばんシンプルな解決策は、「首に悪い習慣」をやめて、「首によい習慣」を身につけることです。
首のために自分でできることは、けっこういろいろあります。
どれも、いますぐ実践できる簡単なことばかり。きっと、みなさんのなかには“なんだ、こんなに簡単なことをするだけでよかったのか”と拍子抜けする方もいらっしゃるかもしれません。
ぜひみなさんも、これから紹介するセルフケアを日々継続して、「首にやさしい生活」を送っていくようにしてください。そして、毎日自分でできるだけのことを行なって、頸筋病のリスクを減らしていくようにしましょう。

首は冷やしてはいけない! 服装にも気をつけよう
首は決して冷やしてはいけません。冷えると、血行がてきめんに悪くなって首の筋肉が固く縮こまり、首こりがいっそう進んでしまうのです。
たとえば、夏、冷房のきいた部屋に長くいて、首すじを触ってみたらヒヤッとするほど冷たくなっていたり、冬、冷たい北風の中を歩いていたら、気持ち悪くなるくらい首や肩が冷えてしまったり……。そういうシチュエーションに陥るのはできるだけ避けなくてはなりません。
体のなかで衣類に覆われていないのは、顔と首と手だけ。顔や手が冷えても神経症状は出ませんが、首が冷えると副交感神経の働きが落ち込んでさまざまな自律神経症状に見舞われることになります。ですから、私たちは春夏秋冬いついかなるときも、首を冷やさないような服装を心がけて、首を保温していく必要があるのです。
首を冷やさないためには、首や胸元が大きく開いたファッションは避け、なるべくハイネックや襟のある服を着て首をガードしたいところです。
冬場であれば、男女ともマフラーやネックウォーマーはマストアイテムでしょう。大きめのマフラーで首全体を包み込むように巻けば、内側に暖かい空気がたまりやすくなります。また、寒さが厳しいときは、夜、睡眠時にネックウォーマーをつけたまま寝るのもいいでしょう。夏場も、冷房風の脅威から首を守るアイテムを怠りなく備えておきたいところ。女性は首にスカーフを巻いたり、薄手のショールを持ち歩いたりして首をガードするといいでしょう。男性も、これに相当する布をポケットにいつも入れていたほうがいいでしょう。
お風呂は半身浴よりも全身浴がおすすめ
毎日の入浴は、首はもちろん、全身を温めるための大切な習慣です。シャワーだけでサッと済ませることなく、体を湯船に浸して、ゆったりとリラックスしながら十分に温まるようにしてください。
なお、首こり予防という点で言うと、半身浴よりも全身浴のほうがおすすめです。半身浴だとどうしても首が冷えてしまい、かえってこりや症状がひどくなってしまうこともあるのです。
全身浴の際は、40度前後のお湯にあごすれすれまで浸かり、ゆっくり温まるようにしてください。ただ、この入浴法はたいへんのぼせやすいので、お湯の温度は低めに設定したほうがいいでしょう。とくに、高齢の方や高血圧、心臓病などの持病がある方は、十分にご注意ください。
あと、先にも述べましたが、シャンプーをするときは、身をかがめたうつむき姿勢で行なうのはNG。些細なことではありますが、首の健康にとってはけっこう大事なポイントなのです。

首こりの予防・改善には「青背魚メニュー」がおすすめ
首こりが気になるみなさんは、ぜひ「青背魚メニュー」を積極的に摂るようにしてはいかがでしょう。アジ、イワシ、サンマ、サバ、マグロなどの背中の青い魚を使ったメニューです。
推奨する理由は、松井病院の頸筋病の入院患者さんに青背魚メニューを提供したところ、明らかな病状の改善が見られたからです。
青背魚のどのような成分が首の筋肉にいい影響を与えたのかは、まだくわしくは分かっていません。ただ、青背魚にはDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などの脂肪酸が豊富に含まれ、これらには神経の機能をよくしたり、血流を促進したりする効果があることが知られています。こういった成分が首の筋肉によい影響をもたらしているのかもしれません。
お刺身、焼き魚、煮魚などの定番料理はもちろん、青背魚をおいしくいただく調理法はたくさんあります。松井病院では、朝、昼、晩、3食とも青背魚を取り入れているのですが、つみれの団子汁にしてみたり、中華風の味付けにしてみたり、洋風のマリネにしてみたりと工夫を凝らし、毎日食べても飽きないようにしています。
みなさんも、首の状態に不安を感じたなら、しばらくの間、青背魚メニューを続けてみてはどうでしょうか。

首をマッサージしたりツボ押しをしたりしてはダメ!
みなさんは「首や肩が少しこっているな」と感じたとき、普段どのように解消しているでしょう。たぶん、一般的に多い答えは「マッサージ」「肩叩き」「ツボ押し」の類いなのではないでしょうか。
しかし、こうしたセルフマッサージや刺激で、かえって首の状態を悪化させてしまっている人も少なくないのです。
首の筋肉はたいへんデリケートで繊細な構造をしています。何層もの筋肉の合間を縫うようにして縦横にたくさんの神経が走っていて、もしヘンに力を加えたりしたら、これらの筋肉や神経が傷つきかねません。
ですから、マッサージやツボ押しなどで安易に自己流の刺激を加えるのは禁物。なかでも、市販のマッサージグッズやツボ押しグッズには、小さな力で強い刺激を生み出すように設計されたものが多いので、首には絶対に使用しないでください。
私のもとにいらっしゃる患者さんにも、「こり解消グッズ」を使って首に刺激を加えていたために、かなり頸筋病の状態を悪化させてしまった人が少なくありません。みなさんも首に異常を感じたら「自分でなんとかしよう」などと思わずに、頸筋病治療ができる医療機関を訪ねるようにしてください。
専門のマッサージ師も言っていることですが、肩のマッサージはいいとしても首のマッサージはやってはいけないのです。これに関してはカナダでの大規模調査研究で証明されています。以来、国際的に認められているまともな治療機関ではどこもやらなくなりました。私はこのことを、カナダのレポートが発表される10年も前から言い続けており、それが証明されるかたちとなりました。
* * *
この続きは幻冬舎新書『不調の9割は「スマホ首」が原因』でお楽しみください。