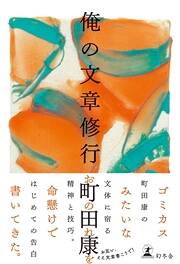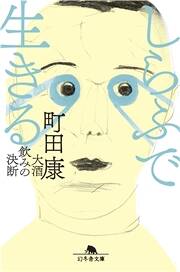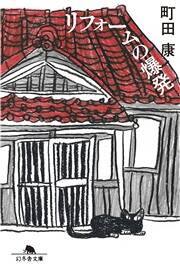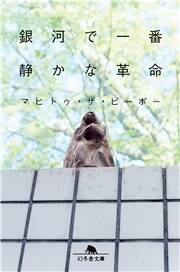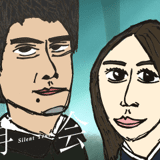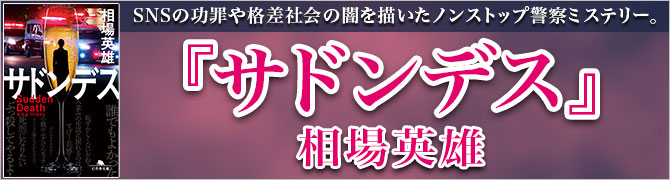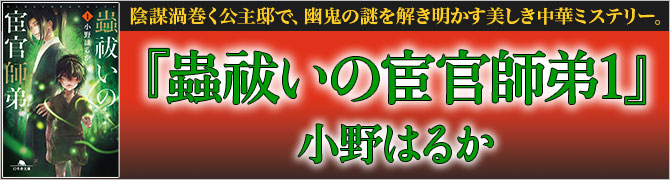町田康さんの『俺の文章修行』刊行記念イベントが2025年4月16日にジュンク堂書店 池袋本店にて開催されました。ゲストは、はじめての小説『銀河で一番静かな革命』が4月初旬に文庫になったミュージシャンのマヒトゥ・ザ・ピーポーさん。「俺ら、ずっと修行の途上」をテーマに、ふたりが向き合う「表現」について語り合いました。
(小説幻冬2025年7月号より転載)
(構成:福田フクスケ)

技術に近道はない
町田康(以下、町田) 今日は『俺の文章修行』に関して思うところを、「ここはおかしいんちゃうか」とかでもいいのでおっしゃっていただければと思うんですが。
マヒトゥ・ザ・ピーポー(以下、マヒト) この本の何が面白いって、文章をうまく書くためのハウツー本の体で始まったものが、「心の錦」や「心の揺れ」こそが技巧よりも重要なんだという話にたどり着き、最終的に「ライブ」の状態に解き放たれるんですよね。町田劇場の舞台袖に立たされて、そのまま放り出されるような読後感で。この本の中で言う「いけず」と呼ばれる「迂回」こそが大事で、そこをゴールに設定しているところが、普通のハウツー本とは全く違っていて、すごく面白いなと思いました。
町田 ミステリー小説なんか迂回の最たるもんですよね。被害者が死んで犯人が分かって「犯人は武田でした」言うたら、もう2行で終わる話なわけやけども、それをずっと迂回していくから物語になる。音楽もそんなとこないですかね。例えばC→G→Cとなったらもう2秒くらいで曲は終わるじゃないですか。でも、それで曲が終わったらちょっと愛想ないから間をいろいろ繋げていこうか、みたいな感覚ってありませんかね。
マヒト 音楽の場合はそこにいる自分の姿勢とか、向き合ってる時の自分の状態を見せている感じですね。自分の歌はいつも同じことを言ってるとも思うのですが、本当に重要なのは用意した歌詞じゃなくて、その歌詞を歌っている時の自分の状態というか。
町田 それはマントラみたいな感じですね。それを唱えることによって自分が何か変容していくっていう。
マヒト その加熱していく過程だったり、加熱した物が冷えて一つのちっちゃい石ころになったり、急にそれがダイヤモンドになったりっていう変容をライブで見せている感じです。そのためのトリガーとして自分が用意した曲なり歌詞なりがあって、自分の状態を動かしているっていうのが一番近い感覚かな。
町田 面白いですね。歌詞って普通、切々と歌うと見てる人は「これ本人が今、言うとんねんな」って思いますよね。せやけど、実はそうじゃなくて、その人の変容する状態を見せられてるんやと。
マヒト この本の中で言うところの「内容」や「内実」というものに近いかもしれないです。
町田 音楽の、とりわけ楽器は、つまらないことでもひたすら練習して習得するしかない部分があるわけですが、逆に、自分がこういうことをやりたいという「内容」に技術が追いつかず人に伝わらないもどかしさというか、技術的な壁にぶち当たるような経験はなかったですか?
マヒト 自分の場合は、誰かに教わったわけではないので、でたらめにスタジオに入ってるうちに技術が追いついてきたという感じでしたね。でも、何よりも一番、自分の「心の揺れ」みたいなものを見失わないようにしなきゃな、というのはずっと直感的に大事にしていて。自分の中に湧き上がる何か整理のつかない、言葉にできないものを発火点にして始めたので、そこを手放すと、そもそも何がしたかったのかを忘れてしまうというか。
町田 アントニオ猪木が晩年に受けたインタビューの中で、格闘技について俺はあんなん人に教えられへんって言ってたんですよ。今の人は技術体系が確立してるから人に教えられるけど、俺は誰かに習ったんじゃなくて全部自分で編み出したことだから、自分では全部できるけどそれを人には教えられへんと。根底にある内容がなくて単に技術だけでやってることと、技術もやってんねんけど内実が伴ってることとは、明確に違うんでしょうね。
マヒト この本で重要なのは、その語られる順番にもあると思っていて。そこまで積み上げてきたものをひっくり返すような構成がすごく重要だったと思います。町田さんの文章の組み立て方における技術や技巧が一つ一つ丁寧に語られた後に、ある意味でそれを全部否定するかのように、結局「内実」と「心の揺れ」と、そこから始まる「お前自身は何がやりたいんか」みたいなものを問うてきて、ライブへと放たれる。
ライブへのこだわり
町田 「ライブ」というのはこの本の一つのキーワードですね。私は3年前にミュージシャンを名乗るのをやめてしまったのですが、それはバンドでアルバムを作る時、レコーディングで編集というか推敲というか、正解みたいなものに近づこうとする感じに嫌気が差してしまったんです。
マヒト 今はボーカルも全部ピッチを直されて、その場所で実際に鳴った音からツギハギにエディットされて、ミュージシャンたちも正解に向かうことが板についちゃった感じがするんですよ。
町田 バンドでそれやられると苦痛でしょうがないんですよね。夏目漱石の『吾輩は猫である』を読んだ時に、「あ、これライブやんけ」と思ったんですよ。あれはストーリーはあんまりなくて、漱石の頭にあったことがそのまま猫を通じて出てきているわけですね。猫という楽器を漱石が演奏して、その音色があの文章みたいな感じ。漱石がムカついてる感じとか、おもろがってふざけてる感じとか、友達とバカなこと言ってる感じが、息遣いとして伝わってくる。小説って大仰な構想のもと緻密に練り上げたようなもんかなて思ってたけど、なんだ、ライブやってるだけやんけって。
マヒト 今回聞いてみたかったのが、そもそもなぜ文章のハウツー本という体裁を選んだのか。最初の章は、文章力を身につけるためには多くの文章を読む以外に道はない、という結論から始まっていて。でも、この本自体が自分で迂回して蛇行してたどり着かなければいけないものをスキップさせてしまう危険性を孕んでいる。なぜそのスキップの技を見せようと思ったのかが気になるんです。
町田 結論から言うと、最終的にはスキップはないですよという話なんですね。いわゆるハウツー本というのは、小説を10本書いてやっと一本モノになっても、9本書いた時間を無駄だと考えて、最初から売り物になるもんを一本書くためにどうすればいいかを教えるためのものです。だけど本当は、売り物にならへんもんを9本書いて初めて、モノになる一本を書く力がつく。その失敗をスキップすることはでけへんよってことを言ってるわけです。たとえ一番近い道を行ったとしても、それは自分で行かないと意味がないんです。
僕は、本来あるべき理想や正しい状態なんてものはないと思ってるんですね。一番イライラするのは言葉の通じん奴ですよ。それは、言語能力が劣ってるとか語彙が少ないとかじゃなくて、むしろいっぱい言葉知ってるはずの奴が、「人が分かってないことを分かってない」ということに腹立つんです。だから、「今の奴らは間違ってるから、俺が正しいやり方を教えてやる」とかは全く思ってない。あるとすれば、雑な文章を読んだ時の個人的な憤りとか腹立ちとか、そういうもんですね。
「雑な感慨ホルダ」との付き合い方
マヒト 本の中で「雑な感慨ホルダ」という自分が無意識に作り出した依存先を取り除くところから始めるべきだ、という話があって。ただ、ものすごい量の情報とコマーシャルが注ぎ込まれてくる世の中で、果たして「雑な感慨ホルダ」を本当にコントロールすることが可能なのか、とも思ったんですよね。
町田 「雑な感慨ホルダ」というのは、実は人間の心って可塑性があるからどうとでも形作れるもんで、自分ではコントロールできないものが埋め込まれてしまっている。物心つくかつかないかのまだ善悪を弁別できない時に、これが善やで、これが悪やで、と言われたらそうなるという。それは情報量の多い現代だからというよりは、そもそも人間が根源的にそういうものというか。
若い時は先に希望があって夢を見てるから、夢によって現実が見えなくなるんですよ。でも、歳をとると先がないから夢がなくなるわけで、そうすると現実が見えてくる。夢から覚めた状態で、あん時思ってたことって実はこうやったのか、というのをたどっていくと、その根底に「雑な感慨ホルダ」があることに気がつくんです。
人は素晴らしい物語や作品に触れて感動するわけですが、その人を形作ってる根底にあるもんがものすごく雑なもんで、それが物語に組み込まれていくことでますます植え付けられていくと思うと、それって怖いことやなと思ったんですね。まあそれが人間やと言ったら人間なんやけども、このサイクルから解脱したいなという感じはありますね。
マヒト 先入観を取り除いていわゆるピュアな状態に戻すよりは、自分の中にもっとたくさんの情報やイメージを取り入れてもっとノイジーになって、全てのことに飽き切るほうがいいと思っていて。自分というものすべてに飽きた時、ようやく最初の「心の錦」や「揺れ」みたいなものが浮かび上がってくるんじゃないかって。
町田 それが本来のピュアな状態ということもできるけど、要するに自分はアホやっていうことを認められるかどうかってことだと思うんですね。自分は正しい発言、判断ができるとか、善悪を弁別できるとか、倫理的・道徳的に正しいとか間違ってるとか、人間は果たしてそういう判断の根拠を本当に持ってるのかな、という気がするわけですね。それを外側の物差しに問うんじゃなくて、自分の物差しに問うた時に、極めて曖昧やなって。結局そこにあるのって、自分が死なずに生き延びること、それから自分の快楽を求めること、これしかないなあっていう気は切実にしますね。
救済とは何か?
マヒト 町田さんの文章の中で「救済」っていう言葉があったじゃないですか。人間には救われない糸クズのような困難があるっていう、あの言葉がすごく好きで。「救済」というのはどういう感覚で使った言葉なんですか?
町田 気楽になるっていうことですね。歌う時ってどうですか。自分を救ってないですか?
マヒト 確かに、自分を救ってますね。
町田 本の中で、「今書いた一文字に影響を受けて次の文字が出てくる」っていう話を書いたけれども、今出した声によっても自分の次に出す声って変わると思うんですよ。同じ曲、同じメロディで同じ歌詞を歌っていても、その時出した声に影響を受けて次の声の出方も変わるわけじゃないですか。それをやることで、「ああ、俺も生きてるな」って感覚を取り戻せるというか。
いろんな情報に押し流されそうになった時に、自分の出した声によって他者感を得られるというか、もう一人の自分に出会うことができる。それは同時に、あの世にジャンプできるということなのかもしれない。ここにいながら我を忘れて魂を別のところに持っていけると。そういう意味では、声を出すことは文章を書くこととあんまり違わないと思うんですね。
マヒト この前、即興演奏家のフレッド・フリスという方が「即興演奏において準備をさせることが一番の悪だ」という話をしていて。要は、さっき町田さんがおっしゃっていた「この言葉を発したら次の言葉が変わる」という瞬間のピュア度を高めるために、準備してはいけないってことですよね。
その時、聴衆から「じゃあフレッドさんはどうして大学で教鞭をとるんですか?」という質問が上がったんです。つまり、教えるということが「雑な感慨ホルダ」として使われてしまう可能性もあるじゃないか、と。それに対してフレッドさんは、「私は『こうすればうまくいく』と教えたことは一度もない。ただその人が思いついた演奏を勇気づけたいんだ」と言ったんです。その「勇気づける」という言葉と、町田さんの「救済」にリンクするものを感じたんですよ。
『俺の文章修行』で町田さんがやってきたことをわかりやすく伝えているのって、読者に何か期待しているからだと思うんです。そこの真意というか、改めて教えること、伝えることって何なのかを町田さんに聞いてみたくて。
町田 一番にあるのは「一緒に笑いたい」ということですね。「俺こんなことおもろいと思ってんねん」と言ったら「あ、俺もおもろいと思ってるわ」と返ってくる、それに尽きる。それが僕にとっての救いだし、それが伝われば相手にとっての救いにもなるんじゃないかって。世の中の役には立たないかもしれないけど、表現ってそういうことちゃうかな。笑うだけじゃなくても、別にグッとくるでも泣くでもいいんですが、泣くはちょっと今売り物になりすぎてて、その辺のドラッグストアとかでも売ってる感じがするんで。
マヒト エンタメと救済、その二つには明確な線引きってあるんでしょうか。
町田 昔はあると思ったんですけど、今はないなと思いますね。そういう意味では救済はエンターテインメントだと思いますね。
マヒト 町田さんはエンタメと救済の二つをどう分けますか? 例えば人によってあれはパンクであれはロックだとか、これは純文学だけどこれはエンタメだとか、いろんな言葉でそれを呼び分けていると思うんですけど。
町田 僕は娯楽の反対側にあるのは芸術やと思ってたんですね。でも娯楽と芸術を分けるのって、それこそ「雑な感慨ホルダ」ですよね。自然は善で人工は悪みたいなのと同じで、娯楽は悪で芸術は善みたいな「雑な感慨ホルダ」が自分の中にあったと思う。でも突き詰めて考えてみると、自分の魂やルーツの中に続いている、命の連鎖に芸術があるかっていうと俺はあんまりないような気がする。桜が咲いてて、ああええな、綺麗やなとか、醜悪なもの見て嫌やなとか、そういう程度のもの。だからそれを芸術か娯楽かって分けるのはちょっと違うなって。
あの世(作品)を作る喜びを知って
マヒト 小説を書く作業を通して、「雑な感慨ホルダ」から抜け出して自分の解像度を上げていくじゃないですか。その鋭敏になった感受性のまま日常の世界に戻ると、いわゆる幸せと言われるものと反対側にあるような、人の嫌な部分とかに気づく解像度も上がってしまう。それって気が狂ってしまわないですか?
町田 作品を作るっていうのは「この世を写してあの世を作る」ってことだと思うんですよね。何も見えない状態で幸せか、見える状態で不幸か、どっちを選ぶかっていう。要は現実と作った表現が、どこまで別のものかって話だと思うんですけど、僕は同じだと思います。この世と似てるけどちょっと違うあの世というレイヤーを作ることだと思うんですよ。それは全然別のもんじゃないから、「ああ、終わった終わった」ってこの世に帰ってきて、「よっしゃユニバーサル・スタジオ・ジャパン行って遊ぼう」っていうのはできへんと思います。
だからあの世に足を踏み込んだ人間は、多分一生その苦い思いを抱えて生きていく。そんなんアホらしいから、普通にこの世にいた方がハッピーやっていう人生もあったはずなんですよ。それを16歳の時、誰も教えてくれなかった(笑)。あの世を作る面白さを知ってしまったら、この世はおもろないなと思って気が狂うのはもうしょうがないことだと思いますね。
* * *
続きは、『俺の文章修行』をご覧ください。
俺の文章修行
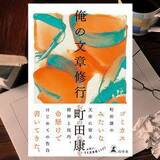
町田康の文体に宿るその精神と技巧。はじめての告白『俺の文章修行』について