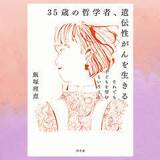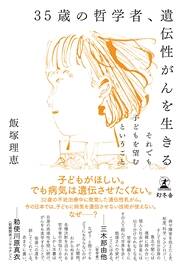32歳の不妊治療中に遺伝性乳がんが発覚した哲学者である飯塚理恵さんが、その治療の経緯と子どもを諦めたくない気持ちを綴ったエッセイ『35歳の哲学者、遺伝性がんを生きる それでも子どもを望むということ』が発売になりました。本書の一部を抜粋してお届けします。
父方? 母方? 遺伝性のがんについて最初に思ったこと
2022年6月、わたしのがんが、遺伝性であるということを告知されて、まず生じた疑問は、それは父方? 母方? という問いだった。告知後に受けた遺伝カウンセリングでは、家系図を作る作業があった。

その時点で、わたしが知っていた親族のがんの情報は二つだった。父が数年前に初期の前立腺がんになって治療中だということ、そして母方の親戚に乳がんの既往歴が一人いることだった。それだけでは、女性特有のがん(乳がん、卵巣がん)が顕著に多い家系とは思えなかった。
もし、わたしの病的遺伝子変異が母からの遺伝であれば、母の乳がん・卵巣がんリスクも高くなるので、母への影響が心配だった。早くこの疑問の答え合わせがしたかった。おそらく、母に比べて、すでにがん患者である父の方が検査はスムーズに行くだろう。しかし、HBOC(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)の遺伝子検査で、健康保険を用いるためには、次のいずれかの条件を満たしている必要がある。
・45歳以下の乳がんの女性
・60歳以下のトリプルネガティブ乳がんの女性
・2個以上の原発性乳がんの女性
・第3度近親者内に乳がんまたは卵巣がんの家族歴を有する女性
・男性乳がん
父は、いずれの条件にも該当していなかった。しかし、調べてみると、これらの条件に当てはまらない場合でも、PARPパープ阻害薬というBRCA1、2の遺伝子変異を持つがん患者によく効くことが期待できるがんの薬があり、その薬を用いることができるかを判断するために遺伝子を検査する、コンパニオン診断と呼ばれる方法があることがわかった。コンパニオン診断の対象であれば、健康保険を用いて遺伝子検査を受けることができるのだ。前立腺がんの治療中であった父は、現在使用している薬が使えなくなった場合にPARP阻害薬が効くかもしれないので、適応を調べるという目的でBRCAの遺伝子検査を行った。
2022年8月後半のある日、わたしは8時間に及ぶ乳がんの手術を終えて数日が経っていた。両胸に挿入された拡張器が痛くて、ベッドの上で動くたび呻き声を上げていた。そんなわたしの携帯が震えた。父からのラインだった。
「BRCA2は陽性でした、ゴメン」
わたしの最初の疑問には、父方からの遺伝であるという答えが導き出された。知りたかったことがわかってスッキリした気分はあったものの、メッセージの最後の部分を読んで、家族性腫瘍の現実も同時に襲ってきた。
父はなぜ謝ったのだろう。
謝罪とは、典型的には何か自身が責任を負うべきネガティブなことが生じたときにすることではないか。哲学の世界では、わたしたちの行為に道徳的責任が生じるのはどんなときか、行為を賞賛したり非難したりする実践はどんなときに適切かという問いが、長年議論されてきた。だが、どんな教科書を読んでも、自分が選択したわけでもコントロールできたわけでもないことに対しては、責任を負ったり非難されたり、謝罪したりする必要はないという点で多くの者の意見が一致している。遺伝子の変異というのは、まさに選択したわけでもコントロールできたわけでもないのだから、どんな哲学者も、謝罪をすべきことではないと言ってくるだろう。お父さんが謝る必要なんて少しもないのだ。
でも、哲学者ではない部分のわたしは、そこで謝ってしまう父の気持ちも理解できた。たとえ自分がしたことではなくても、そうではない現実を選ぶために、自分には何もできることがなかったとしても、がんになりやすい遺伝子変異が、自分を経由して娘に受け継がれてしまい、結果として、娘が32歳でがんになったという事実への深い悲しみが、ゴメンという言葉には表れている。