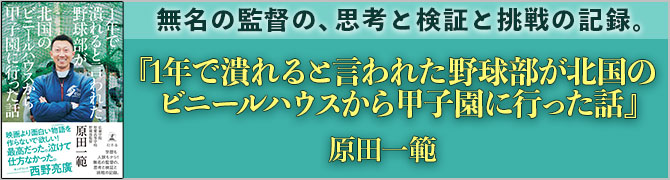発売前からざわざわ…、発売してからますますざわざわしている、芦花公園さんの新刊『パライソのどん底』。
ここでは、第1章「贄(にえ)」の章を特別公開。これまでになく艶めかしい、芦花公園発BL系ホラーをお楽しみください。
* * *
「りっちゃん、あけてー」
湿ったような臭いで目を覚ます。気付くと律は、祖父に抱きかかえられるような格好で寝ていた。外は暗くなっている。はっと飛び起きて時計を見ると、七時を回っていた。
「おじいちゃん」
祖父はぐっすりと眠っている。死んでいるのかと思ったくらいだ。もう七時だ、祖父の晩ご飯、それより、瑠樺は、瑠樺は。律はふらふらと立ち上がる。頭が割れるように痛い。
──ガタン
玄関でまた音がして、心臓が跳ね上がった。律の手は縋(すが)るように祖父の寝巻の裾を掴んだ。
「りーつー、ただいまー!」 明るい女の声。母だ。
「あらっ! やだー、律、あんたお義父様に夜ご飯食べさせてないでしょ!」
「ごめん……寝ちゃって」
「もう、気を付けなさいよ」
忙しない母の挙動に安堵しながら、朝感じた強烈な眠気を思い出す。そうだ、全て夢だったのかもしれない。おそらく、祖父に歯を磨かせたあとふたたび寝入ってしまったのだ。瑠樺は律が寝ていることに気付いて帰ってしまったのだろう。その方がずっと辻褄(つじつま)が合う。
母は食事の支度をしながら、何かを思い出したかのように手を打った。
「そうだ、玄関見てみてよ。いたずらだと思うけどすごいのよ、綺麗で」
もしかしたら瑠樺が何かメッセージを残していったのかもしれない。そう思うと申し訳なさが溢れた。明日学校で謝らなくては。律は土間に下りて扉を引いた。
「すごいでしょー、誰がやったのかしらね、お花畑みたいよね」

母の声がやけに遠く聞こえる。門から扉まで隙間なく、花が敷き詰められている。ポピー、アスター、ガーベラ、ユリ……とにかく多種多様な花が。季節はずれの花まである。目を凝らして律は気付く。違う。これは置いてあるのではない。地面から生えているのだ。
今は冬だ。にわかに心臓が速く脈打った。反対に体温が下がっているのが分かる。 街灯のない田舎で、月に照らされた色とりどりの花は、ひたすら美しく、不気味だった。
瑠樺に、昨日出迎えられなかったことを謝りたかった。玄関に咲いた花や、扉を叩いた何か(00)が、夢でも現実でも。しかし登校しても瑠樺はいなかった。瑠樺に会えなかったことだけは、事実だ。
その日は人生で一番退屈だった。
律は退屈しのぎに、昼休みと五限と放課後に杏子を抱いたが、心は満たされなかった。なにもかも瑠樺には遠く及ばない。それなのに彼女の体温に触れるたび、瑠樺の肌を思い出し、猿のように昂(たかぶ)った。
そんな日が一週間も続いた。律は気が狂いそうだった。自分で自分の体が制御できない。
何度そういうことをしても、体の熱は冷めず、立っていても座っていても夢を見ているような気分だった。
相変わらず、学校の田舎者たちは律に触れてこようとしない。瑠樺のいない律は路傍の小石のようなものだ、前のように。そう、ここへ来る前のように。
とうとう熱に浮かされた律は考えるようになった。瑠樺なんて最初からいなかったのではないかと。律が頭の中で考え出したひどく美しい生き物で、だから自分に都合よく振舞
っていただけなのではないかと。杏子が言っていた通りだ、嘘くさい、律のために美しい、
そんな──
「おい」
鋭い声が聞こえたのと同時に、律の隣を歩いていた杏子が突き飛ばされた。杏子の甲高い悲鳴が脳に刺さり、律はようやっと前が見えるようになった。
背が高く筋肉質な男が律の方をまっすぐ向いている。顔は逆光で真っ黒に潰されていた。
男は粗野な笑い声を上げながらしゃがみ、倒れた杏子に近付いて、顔を鷲掴みにした。
「これが『今回の』か?」
質問の意味が全く分からず固まっていると、男はさらに大口を開けて笑った。
「悪くない。悪くはないが、なんだ、随分ヘボだな、今回のは。お前こんなのが好みなの
か?」
「その子は違いますよ、礼本(あやもと)さん。見たことがあるでしょう? 忘れた?」 男のものであろう黒いバンから、小柄な女性が降りてきて言った。
「大体、あなたには確認を頼んだだけのはず。手を出すことは許可していません。放しなさい」
目が大きく、猫のような可憐さのある美人だった。体格や甘い顔に似合わない威圧感を備え、瞳に冷たい雰囲気がある。彼女はため息をついて、
「あなた、一体何をやっているの」
と杏子に言った。
杏子の方を見ると、礼本に突き飛ばされた姿勢のまま俯いて唇を震わせている。いつもふにゃふにゃ笑っている彼女からは想像もつかない表情だった。
女はその冷たい目線を杏子から律に定めて、口角をわずかに上げた。
「あなたが相馬律さんですね。私は森山神社のイミコを務めている中山林檎と申します」 森山神社。イミコ。中山林檎。言葉が耳を通り過ぎていく。そういえば小高い場所に古びた神社があって、そこからだと村が見渡せるのだと父が言っていたような気がする。律は黙って「イミコ」の次の言葉を待った。

「相馬さん、あなたは腹磯のアレに魅入られている、そうですね」
今度は言葉の意味がしっかりと脳に焼き付いて、同時に律のはらわたに耐えがたいほどの怒りが湧いてくる。瑠樺のことだ。瑠樺のことを「腹磯のアレ」と呼んでいる。綺麗な顔をしたこの女も、やはり下らない迷信を信じて瑠樺を迫害する田舎者なのだ。
怒りと同時に、何故か安堵もしていた。瑠樺は律の作り上げた妄想などではない、と分かったからだ。あの美しい瞳も声も柔らかな唇も甘い肌も白い脚も潤んだ粘膜も全て──
「その沈黙は肯定と見なしていいのでしょうか」イミコの冷たい声が思考を切り裂いた。
「分かりませんね、なんのことだか」
律は努めて平静に答えた。イミコの瞳は、答えを聞いても冷たく凍っていた。
「りんごちゃん、そんなお堅い聞き方しなくても、こう聞きゃ一発だ」
それまで黙っていた礼本と呼ばれた男が、にやにやしながら近付いてくる。彼は律の前に立ちはだかると、気持ち良かったか? と一言一言区切るように口を動かした。
「アレはお前の欲しいものを欲しい姿で与える。なあ、気持ち良かったよな。毎日毎日ヤってんだろ、お前も」
「違うっ」
律の顔が一気に熱を持った。その熱のまま目の前の男が焼け死ねばいいと律は思う。
律と瑠樺はそんなものではない。瑠樺は美しい。そんな下品な言葉を美しい生き物に浴びせることは許さない。瑠樺は律の美しい生き物で、こんな男が訳知り顔で語っていいようなものではない。
「何が違うんだよ。お前がアレとベッタリなのは……」
「そんなのは下品な妄想だ! 好きだから……愛してるから」
礼本は鼻で笑って、
「愛してる? じゃあ具体的にどこが好きなんだ? 体と顔だろ、それ以外であるのか」「笑顔っ」
口から、出まかせの言葉がすらすらと出た。これは嘘だ。瑠樺の魅力は笑顔などではない。瑠樺そのものだ。しかし、この男が「体と顔」という言葉を使って瑠樺を侮辱するのは絶対に嫌だった。
「どんなときでも、いつも笑ってる。優しく笑ってる。それが、すごく綺麗で……」
「後付けだな。それに、いつも笑ってるのはアレの特性だ。アレはそういうふうにできてんだよ」
律は拳(こぶし)を振り上げて礼本を打とうとしたが、易々と手首を掴まれ、逆にひねり上げられてしまう。
「アレは俺のお下がりだ。俺だけじゃない、よそからここに来た男、全員のお下がりだぞ」
「うるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさいうるさい」
耳を塞(ふさ)いでしまいたかったが、掴まれた手首がそれを許さなかった。礼本は滔々(とうとう)と語る。
瑠樺がどんな声で鳴くか、どんなふうに腕を絡ませるか、どんなふうに舌を使うか、どんなふうに受け入れるか、どんなふうに──
「口でするのもなかなかだろう」と言って礼本は目を細める。俺がしつけたんだと自慢気に頷きながら。
律は嘔吐していた。礼本が吐瀉物を避けるように飛び去り、手首が解放される。そのまま地面に膝をついて、胃の中が空になるまで吐いた。
頭には「お下がり」という文字が漫画のオノマトペのように浮いて、点滅して、こびりついた。そうだ、瑠樺は慣れていた。初めてのときもすんなりと受け入れて。名も知らぬ大勢の男たちと、蛇がのたうつように絡まり合う瑠樺を想像する。お下がり。きっと誰にでもあの美しい犬歯を見せてねだるのだ。お下がり。白い濁流が脳を侵していった。お下がり。
散々吐いて胃液も出尽くした頃、あいつはそんな男じゃない、と呟いた。誰に聞かせるわけでもなく、自分を鼓舞するための言葉だった。瑠樺が何人と交わっていようと、誰にでも股を開く阿婆擦(あばず)れと呼ばれるような、そんな男ではない。瑠樺は世界で一番美しいのだから。
意外なことに、その一言で礼本の顔色が変わった。何の表情もなかったイミコでさえ、驚きが顔に出ていた。不快な二人組の動揺を見て、少し気分が軽くなる。
「男? 今回のアレは男なのか?」
(つづく)
パライソのどん底の記事をもっと読む
パライソのどん底

男の首筋に浮き出す血管を数えたことも、くっきりとした白い喉仏に噛みつきたいと思ったこともなかった。“美しすぎる彼”に出会うまでは――。それぞれの“欲望”と、それぞれの“絶望”が絡まり合い、衝撃の結末へ。
「ベストホラー2022《国内部門》」(ツイッター読者投稿企画)で1位・2位を独占した芦花公園による、切なさも怖さも底無しの、BL系ホラー!
* * *
“絶対に口にしてはいけない禁忌”を抱えた村に、転校生・高遠瑠樺がやってくる。彼のあまりの美しさに、息を呑む相馬律。だが、他の誰も、彼に近づこうとしない。そして、律だけに訪れる、死にたいほどの快楽……。
ある日、律の家の玄関が、狂い咲きした花で埋め尽くされる。すると、”花の意味”を知る、神社の“忌子”から、「アレに魅入られると、死にますよ」と告げられる―ー。
この村で、住民がひた隠しにする「伝承(ひみつ)」とは?
俺の心と体を支配し、おかしくした、「存在(アレ)」の正体とは?