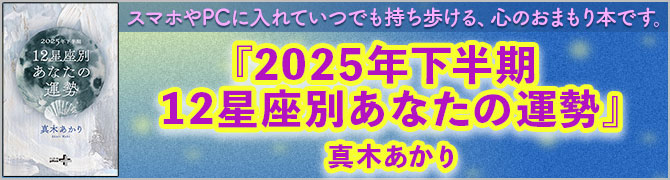いま、テレビで見ない日はない、ウイルス学の第一人者、岡田晴恵氏。
実は、岡田氏は、10年前に自身の小説の中で、「弱毒性インフルエンザ」の流行によって起こるパンデミックを描いている。
なんと、小説の中で繰り広げられる社会的混乱の数々は、新型コロナウイルスによって起きている、今のパンデミックの様相そのものだ。
日本は……世界は……、いったいこの先、どうなるのか?
岡田氏の小説には、人類が生き延びるヒントがあるかもしれない。
小説『隠されたパンデミック』より、新型の「弱毒型」インフルエンザウイルスによってパンデミックに陥った日本の姿を描いたシーンを、公開する。

* * *
――主人公は、新型インフルエンザ対策に奔走しているウイルス学者・永谷綾。致死率の高い「強毒型」インフルエンザがもし起こってしまったら、社会が崩壊する! 危惧した永谷は、厚労省の新型インフルエンザ対策の不備を追及し、本省を追われてしまった。そこへ、「弱毒型」のインフルエンザ(H1N1)が発生!――
本格的パンデミックの悪夢
この新型インフルエンザH1N1(弱毒型)は、はじめ、小中学生に多くの感染者を出し、次に保育園児にも増えてきて、家族内感染を起こし、梅雨が明けても流行は終息せず、小流行と集団感染を繰り返しながら、そのまま秋に突入していった。そして、11月の気温のさらなる低下とともに、本格的に、全国一斉に火の手を上げた。乾いた藁(わら)に火が点(つ)いたかのように、次々と患者が出る。
新型インフルエンザの患者の報告数が増え、流行が拡大し始めたごく初期には、ほとんどの人々は、5月や6月の先触れのような、あの大したことのなかった流行を思い出して楽観視をした。しかし、それが1~2週間もすると、すぐ自分の直面する問題となって目の前に現れ始めた。
自身の職場でも、子供の学校でも、身近な人々の中で、発熱して寝込む人の噂が出ていた。そして、自分も家族も、感染の当事者になるかも知れない危険が実感された。
春夏の豚ウイルス由来の新型ウイルスは、まだ完全なヒト型ウイルスに変化していなかった。鳥インフルエンザウイルスの性質を保持した豚型ウイルスが人の世界に侵入してきただけで、まだ大流行の前触れ程度だったのだ。だが、今のウイルスは、南米、オーストラリア、アフリカ等の南半球での冬季に、人の社会で1シーズン流行し、その間に“完全なヒト型”に順化して、北半球の冬季に向かって帰ってきた。7月の時点で、冬を迎えていたニュージーランドでは、一人の感染者が2人に新型ウイルスを伝播すると試算されていた。さらに、この冬にはニュージーランド国民の78%がこのウイルスに感染すると推定されていた。秋以降、日本でもそれが現実となったのだ。
11月、流行が日本国内でさらに本格化すると、2週間でその地域の住民の3分の1が感染するという事態が起きた。
ひとたび、学校にウイルスが侵入すれば、2、3日後にはたくさんの病欠児童の報告が、養護教諭の元に寄せられる。中には、発熱して病休する担当の教師も出た。
さらに、中学校、高校、大学等で若い世代の集団感染が多発した。人口が集中し、地下鉄等の交通機関が発達している都会では、特に感染の拡大が速い。遠距離通学している生徒がいる私立中学高校は、通学時の感染が、直面する重大問題ともなった。
公立の学校でも、養護教諭は校長と協議し、校長は教育委員会にも連絡をして、急きょ、学校は休校となった。子供たちには、自宅でおとなしく勉強するように指導し、用意してあった自宅学習用のプリントを担任教師から配布させた。しかし、その子供たちの中に、すでに感染した子供たちも多く含まれていたため、数日内に自宅で発熱して、家族にもうつすことになった。夏の間にくすぶるように進んでいた現象が、何千倍もの大規模な形で起こっていた。
過去の新型インフルエンザの流行の経験でも、学校が地域の流行の起点となったことが記されている。1918年のスペインかぜの時も、学校と軍隊の“人の集団”が、ウイルスを地域へ拡大させた。迅速な休校措置がとられなければ、学校のような集団生活の場は、インフルエンザウイルスの一大伝播場所になりかねないのだった。

しかし、6月以来、国によって、H1N1型新型インフルエンザに対しては、基本的には季節性インフルエンザと同様の対応をとると変更された。「学校、事業所などの現場も、自治体が中心となって、それぞれの計画に沿った独自の裁量で、現場状況に見合う判断をし、現場対応を決める」とされている。感染予防、拡大予防の対応のほとんどが現場に任されている。言い換えれば、その組織内の判断で決めねばならない。あらかじめ新型インフルエンザの理解や対応計画が、学校や企業でできていなかったところは、混乱を招くことは自明であった。そして、地域の自治体や学校で、対応にばらつきが出てくることは、目に見えていた。
新型インフルエンザには、迅速な状況判断と、適切な対応を実施する決断が必須だ。流行拡大が非常に速いので、校長や社長、自治体の、一日の判断の遅れが、ウイルスの拡大を招いてしまう。
新型インフルエンザ流行時に現場の議論を整理しやすくし、円滑な現場判断ができるようにするためにも、厚労省は、対応の目的と到達目標、それを実施するための基本的な指針や判断基準を、自治体等に具体的に明確に示しておくべきであったが、自治体の現場がその状況に応じて判断するものとしてしまったため、それはほとんどなされていなかった。
流行時の医療の確保等をはじめとして、現実の対応は、大まかな方向性が厚労省から示されただけで、すべて地方自治体と現場に任された。
春に発生した新型インフルエンザ対策では、「柔軟に対応」という文言がよく使われたが、“柔軟性”の持たせ方を示すことは、各自治体に責任を負わせるということでもあったのだ。本来、柔軟性の持たせ方には、合理性がなければならないはずだ。それは、国の専門家委員会等が示すべきもので、現場判断にゆだねるのは無理があった。
また、季節性インフルエンザと同様に対応するということは、多くの場合、学校等の集団やクラスなどで、多数の患者や欠席者が出てからの判断となる。すなわち、ウイルスが学校に侵入してから対応するケースがほとんどとなる。ところが、インフルエンザウイルスは、発熱などの症状の出る前日から、感染者が自覚せぬままにウイルスを排泄して、他人にうつすものであり、従って、患者が確認されたときには、その周囲にはすでに感染者がいるのは自明のことなのだ。
そうやって、兄弟姉妹は、たとえば、弟が小学校で感染してくれば、家で2、3日以内に、兄や姉、妹にもうつる。兄は同地域の中学校に潜伏期にウイルスを持ちこみ、姉はバスと電車で地域を越えて、高校に通学していく。妹は保育園で友達に感染を広げてしまう。──こんなことが日常的に起こりうる。子供が発症すれば、母親もパートを休んで面倒を見ざるをえない。それは、家計へ深刻な影響を与えるし、急な欠勤はパート先にも痛手だが、どうにもならない。そうこうしているうちに子供たちから両親への感染も起こってくる。
完全なヒト型に変化した秋冬の新型ウイルスの、人から人への伝播効率は、初春の“新型もどき”のウイルスに比べて飛躍的に上がっていた。家族の一人が感染したら、1週間以内にほぼ全員が感染してしまうという事態を招いたのだ。
感染した人々の中で、高齢者の中にはごく軽い症状の人もいたが、多くの人々が、38度以上の発熱を経験し、その後、関節痛や筋肉痛が出て、さらに咳等の呼吸器症状が出た。この程度の病態は、いわゆる“軽症”という部類に入るのだが、季節性インフルエンザよりは明らかに重い症状である。たとえウイルス自身の病原性は低くても、感染を受けた人の方に全く免疫がなければ、それなりの重い病気となるのだ。
大人の38度の熱は、結構つらいものだ。また、中には嘔吐や下痢をする人もいて、小児を中心として、これはややもすると脱水症状を起こす。多くの患者に、生命の危険は低いとは言え、市販のかぜ薬を飲んで在宅安静で回復を待つだけで対応できるとは思えない。

人々は病院や地元のかかりつけ医を頼った。こうして、多くの患者が、3時間、4時間待ちの外来の受診の列に並ぶことになった。町の医院の待合室は、修羅場と化した。待つ間にも具合が急に悪くなる患者も出た。
特に乳幼児などの小児科医院は、別の感染症による風邪症状の患者と入り乱れて、患児が文字通り、待合室からあふれ出した。駐車場の車の中で、母親と順番を待つ、熱にうかされた子供たちもいる。その母親にも、新型ウイルスは感染を広げていく。
しかし、それだけではない。問題は、医師と看護師への感染だ。これら医療従事者にも、新型インフルエンザウイルスは院内感染を広げていく。院内感染を防ぐには、パンデミックワクチンの早期接種が必須である。
この年末までに国が製造供給できる新型インフルエンザH1N1型ワクチンは、年内に1700万人分程度となっていた。これは、当初発表された「秋以降、2500万人分くらいを用意する」という見込みを大きく下回る数字だ。しかも、11月のはじめには、まだその新型インフルエンザ用のワクチンは、全国のほとんどの病院には届いていない。そのワクチン接種の前に、新型インフルエンザの大流行がやってきてしまった。
そもそも、ワクチンが届いても、十分な免疫を得るためには、3週間の間隔を空けて2回の接種が必要であり、合計で1か月くらいの時間がかかる。一度目の接種で免疫記憶を誘導し、2回目の接種でより強い免疫とする必要があるためだ。
だから、「先生! 新型インフルエンザのワクチンをうちの子にお願いします」と訴える母親の切迫した要望にも応えることはできない。医師たちは、母親たちのそんな声を、毎日外来で何十回と聞くことになる。中にはヒステリックに叫ぶ若い母親もいた。保健所でも、パンデミックワクチンの問い合わせが殺到しているという。
現段階で接種可能なワクチンは、ほとんどの医療機関では、まだ季節のインフルエンザ用のワクチンのみだった。これは、新型インフルエンザには残念ながら効果はなかった。結果として、押し寄せる患者やワクチン希望者から、医師にも多数感染し、医療を担う現場は大きな痛手を被った。
一人の医師で開業していた町の医院やクリニックでは、院長が急病となれば、休業せざるをえない状況に追い込まれる。そうなると、医師が複数いる総合病院の外来や救急医療に、大勢の患者が藁にもすがる思いで殺到することになる。しかし、病院も普段からぎりぎりの医師などのスタッフの数で診察をまわしている。その中の一人でも二人でも感染すれば、医療行為には大きな影響が出る。
感染爆発〈パンデミック〉の真実の記事をもっと読む
感染爆発〈パンデミック〉の真実

世界的な新型コロナウイルスの大流行で、我々はいまだかつてない経験をしている。
マスクやトイレットペーパーが売り場から消え、イベント自粛や小中高休校の要請が首相から出され、閉鎖した商業施設もあれば、従業員の出社を禁止する企業も出ている。
そこで毎日、メディアに引っ張りだこなのがウイルス学の岡田晴恵教授。
なんと岡田氏は、10年前に自身が書いた小説の中で、まさにこうなることを、予言していた!
そこで、この2つの小説、『H5N1 強毒性新型インフルエンザウイルス日本上陸のシナリオ』『隠されたパンデミック』を、緊急重版かつ緊急電子書籍化した。