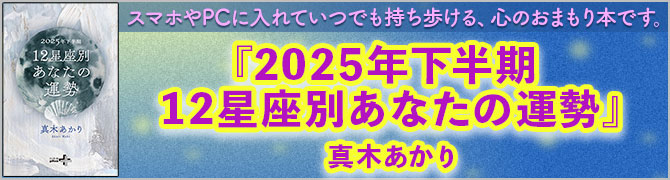書物、とりわけ人文書の衰退が危惧される中で刊行された、國分功一郎さんと互盛央さんの共著『いつもそばには本があった。』(講談社選書メチエ)。対談でも往復書簡でもなく、「観念連合」をキーワードに、お二人が自らの経験を振り返り、100冊を越える書物をめぐる記憶のネットワークを伝えています。この情熱あふれる稀有な書から、國分さんがハンナ・アレントについて触れた一編「実存主義と人文学」を2回に分けてお届けします。
* * *
そんなに互さんに損な役を押しつけていたかなぁとちょっとだけ反省しつつも、しかしいつも通りにいきたい。今回は連想で書くというのが採用された方法なので。
互さんは藤田博史の、ある意味ではドグマティックとも捉えられかねない、しかしある種の潔さをもった、「人間が人間になる」あるいは「これが人間である」というテーゼを受けて、「人文(humanities)」なるものに言及された。これについては最近思うところがあるのでそのことを書いておきたい。取り上げたいのはハンナ・アレントである。
私が大学生だった1990年半ば、アレントはちょうど人気が出始めたころだった。私がそれを強く意識していたのは、政治学科の学生だったからかもしれない。アレントは政治学において盛んに論じられていた。そして私は、そこで論じられているアレントに強い反発を抱いていた。
マルクスをここまでケチョンケチョンに叩いている彼女を政治学者が積極的に評価することの意味が全然分からなかった。単に彼らも反マルクス主義だったのだろうか。そして何より、アレントの重要概念、「公的空間」がやたらと持ち上げられていることが全く理解できなかった。それはほとんど「お行儀よく振る舞え」という程度のものに思えた。
アレントの言う公的空間はその成立のためにいくつもの条件を必要とする。そのような空間が仮に可能だったとしても、そこから排除される者に目を向けるのが政治学の役割ではないのかと思っていた。それと――これはやや議論の余地があるとは思うが――公的空間の成立にはある種の「徳」のような価値の共有が前提になる。これも当時の私には到底受け入れがたかった。それは単なる伝統的価値観の押しつけになる可能性があるからである。政治とはそのような囲いをはみ出してしまうものであり、そうしてはみ出してしまうものにこそ目を向けるのが政治について考えることだと当時の私は信じていた。
あまりに話題になっているから『人間の条件』の読書会を開いたこともあったのだが、結局、共感はできなかった。そのような私のアレント観はずっと続き、『暇と退屈の倫理学』でのアレント批判にまでつながった。同書で私はアレントのマルクス読解を強く批判した。
だが今は違う。自分が専門的に研究している哲学者だと言いたいぐらいにアレントにのめり込んでいる。日本アーレント研究会にもご招待いただいて講演をしたこともあるし、新聞の連載では毎回アレントを取り上げている。アレントの保守主義的な側面への警戒心が弱まったわけではない。そのことはいつも強調している。ではなぜかと言えば、少しかっこよく言うと、状況の変化が私にアレントに向かうことを強いたのである。
アレントが強調していた政治制度や価値といったものが、とてつもないスピードで本格的に崩壊していくのを、私はこの5年の間に目にしてきた。それは、ナチスドイツの到来を準備した1920年代のドイツ、本格的な大衆社会が現れ始めた1950年代のアメリカでアレントが見た光景とどこか似ているのではなかろうか。彼女が指摘した現象がいま純粋な仕方で実現されつつあるのではないか。私は本当にそういうことを考えていた。だから『人間の条件』を読み直し、大著『全体主義の起源』を再び書庫から取り出すことになった。勤務校のゼミでも『革命について』を輪読し始めた。
ただ、これはあくまでも状況の話である。アレントに対する見方が変わるためには別のちょっとした出来事が必要であった。今まで知らなかったアレントに出会う必要があった。
アレントを読み直していると、どうも政治学の中で論じられていたアレントとは違う側面が目についた。たとえば『全体主義の起源』のあとがきでアレントは「孤独(solitude)」を論じている。孤独とは私が私自身と一緒にいることである。私は私自身と一緒にいることで私自身と対話する。そうした対話こそ、思考することに他ならない。つまり思考には孤独が必要である。だが、自分自身と一緒にいることができない人がいる。その人はだから誰か自分と一緒にいてくれるひとを探し求める。その時、その人が感じているものこそ「寂しさ(loneliness)」に他ならない。寂しいとは自分と一緒にいられないということ、孤独に耐えられないということだ。そして寂しさは人間にとって最も絶望的な経験である。全体主義はこの絶望的な経験を利用したのである……。
ここに現れているアレントは私が昔聞いたアレントとはどこか違っていた。それは「政治学者アレント」というイメージには収まり切らない語り口のアレントだった。
(後編に続く)
* * *
9月6日(金)より、國分功一郎さんの連続講座「ハンナ・アレントと哲学」(全4回)が始まります。詳細は幻冬舎大学のページからどうぞ。
いつもそばには本があった。

1冊の本には、たくさんの記憶がまとわりついている。その本を買った書店の光景、その本を読んだ場所に流れていた音楽、そしてその本について語り合った友人……。そんな書物をめぐる記憶のネットワークが交錯することで、よりきめ細かく、より豊かなものになることを伝えるため、二人の著者が相手に触発されつつ交互に書き連ねた16のエッセイ。人文書の衰退、人文学の危機が自明視される世の中に贈る、情熱にあふれる1冊!