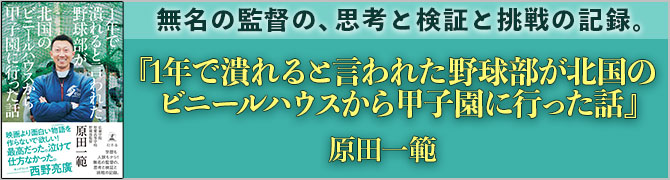外出自粛で増える自宅での時間。それは自分を見つめなおすのにもってこいです。今日は、人間の実存について考える過去記事をご紹介します。
* * *
書物、とりわけ人文書の衰退が危惧される中で刊行された、國分功一郎さんと互盛央さんの共著『いつもそばには本があった。』(講談社選書メチエ)。対談でも往復書簡でもなく、「観念連合」をキーワードに、お二人が自らの経験を振り返り、100冊を越える書物をめぐる記憶のネットワークを伝えています。この情熱あふれる稀有な書から、國分さんがハンナ・アレントについて触れた一編「実存主義と人文学」を2回に分けてお届けします。
* * *
アレントは間違いなく哲学者であると思うが、彼女自身は、自分は哲学者ではなく政治学者であると言い続けた。そこには彼女が下した哲学の伝統に対する否定的評価が関係している。哲学は自らを高尚なものと位置づけたために、政治という「人間の事柄の領域」に関わる物事をさげすんだ。それによって政治は然るべき分析と評価を受けることができなくなってしまったというのがその評価の主な内容である。アレントが言っていることは分かる。それに「政治学者アレント」は確かに存在している。けれども、孤独を語るアレントはどこか違う。
あるいは『革命について』で、心という「暗闇の場所」を語るアレントを取り上げてもよい。心は暗闇を必要とするとアレントは言う。心の中のいかなる動機も自分にとっては不明瞭であり、結局は解明しきれないし、それを無理矢理に公にしようとするならば、人はかならず偽善者になる。行為や言葉の背後に潜む動機は、公の場に持ち出されるならば破壊されてしまう。ロベスピエールがやったのは、革命家たちに心の裡にある動機を公言させることだった。だが、動機の解明を突き詰めれば、彼らは偽善者として現れざるを得ない。どんな動機も公になれば嘘っぽいのである。だから彼らは断頭台に送られることになる(就職活動で志望動機を何度も尋ねられる学生たちは、ロベスピエールの前に連れ出された革命家のようなものだ。自分でも動機など分かるはずがないのに、それを公にすることを強制されているのである)。
このような語り口で人間に迫るアレントの姿をどう表現したらよいだろうか。アレントの著作には、このような語り口でしか実現できないと思わせる人間への接近がある。それをどう表現したらよいだろうか。ヒントになったのは、一緒に『統治新論』を作っていた時に大竹弘二さんがふと口にした一言だった。ヤスパースやハイデッガーのもとで学んだアレントは、最後まで彼らから学んだ実存主義を捨てなかった――大竹さんはさらりと口にした。そう、それだ。アレントにあるのは実存主義である。アレントはこの実存主義によってこそ、人間に迫ることができた。彼女の中で実存主義と政治学が独特の仕方で組み合わさっていて、それが、本人は何と言おうとも、彼女を哲学者たらしめているのだ。
実存主義はこれまでのその歴史上の形態がいかなるものであったにせよ、人間なるものに迫る上で欠かせない思想だと私は思っている。そこに存在してしまっている実存、さまざまな喜びと苦しみを抱えてそこに生きてしまっている実存、それを問うのが実存主義である。心に暗闇を抱えながら、時に、どうしても寂しさを感じずにはいられない人間なるものの実存に迫るアレントは実存主義者であり、それを問う時、彼女は「人文学」をやっているのだと思う。だから私は人間に迫らんとする人文学は常にどこかに実存主義を抱えていると思うし、抱えていなければならないとすら思う。そのように実存主義を眺めるならば、構造主義によって実存主義を蹴散らしたと言われるラカンにですら、どこか実存主義を読み取ることができるように思える。実存主義はその重苦しい雰囲気によって定義されるべきではない。扱うものがどうしても重苦しいが故に、重苦しさを醸(かも)し出しているにすぎない。
実存主義を捨てなかったアレントというイメージを得ることで、私は政治学者アレントにも正面から向き合うことができるようになった。政治学者アレントについての話を耳にしても、その裏、あるいは、その脇にある実存主義的側面を思い起こすことができるので、自分の中でバランスをとることができるようになった。
そうやって改めて彼女の主著『人間の条件』を読み直した時にもひとつヒントになる言葉があった。同書のドイツ語版はアレント自身が手を入れた翻訳なのだが、そのドイツ語版を翻訳した『活動的生』に付された訳者、森一郎先生の一言である。森先生はこの本をハイデッガーの『存在と時間』に並ぶ20世紀の哲学の古典と記されていた。そうだ、そのように読めばよかったのだ。『人間の条件』は決して政治学や政治思想の領域に留まる本ではない。それは実存主義者であり政治学者であるハンナ・アレントという哲学者が書いた哲学書である。そのことは彼女が書いたどの本についても言えるだろう。
哲学は人文学には収まらないのではなかろうか。哲学が文学部に存在しなければならない理由もどこにもない。少なくとも私が好きな哲学者はいずれも、政治学のような社会科学的なものの見方と実存主義的な感性を備えている。
* * *
この國分さんからの投げかけを受けての互さんの「観念連合」はぜひ『いつもそばには本があった。』(講談社選書メチエ)でお読みください。
いつもそばには本があった。の記事をもっと読む
いつもそばには本があった。

1冊の本には、たくさんの記憶がまとわりついている。その本を買った書店の光景、その本を読んだ場所に流れていた音楽、そしてその本について語り合った友人……。そんな書物をめぐる記憶のネットワークが交錯することで、よりきめ細かく、より豊かなものになることを伝えるため、二人の著者が相手に触発されつつ交互に書き連ねた16のエッセイ。人文書の衰退、人文学の危機が自明視される世の中に贈る、情熱にあふれる1冊!