

開店から1年5か月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得したシェフがいる。大卒で企業に務めた後、料理学校に通い、26才で仏料理店の門を叩いた遅まきのスタート。しかし塩1粒、熱0.1度にこだわる圧倒的情熱で、修業時代から現在に至るまで不可能の壁を打ち破ってきた。心を揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
フランスに生まれフランスに育ったフランス人シェフでも生涯の憧れであるミシュラン三ツ星を、なぜこの日本人は手にすることができたのか?
アンコール御礼!
トワイライトエクスプレス 瑞風で供される食事を担当する料理人の一人でもある、天才シェフ・米田肇を追ったノンフィクション『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みを全4回でお届けします!
* * *
「なんて表現したらいいんでしょうね、あの感じは。ミシェルの包丁を握る手のどこにも力が入っていない。剣の達人が棒ですっと肉の表面を撫でたら、肉が切れてたみたいな感じだった。思わず彼が切った肉の断面を見たら、これが何と言えばいいか、すごく美しいんです。頭を抱えました。自分では、切ることに自信を持ってました。そのときだって、いつも通り完璧に切ったんです。どんなことであれ、自分の仕事に関して、どうしたらもっと良くできるのかって、いつも考えています。包丁の使い方も工夫を凝らし続けてきました。修業を始めたときから、まだ何もできていない頃から、今日できなくても、明日はできるようになるためにはどうしたらいいんだろうって。考えて、考えて、工夫して、工夫したことをノートに書いて、練習して、それでもできなくて、でも、そこで諦めずに練習を続けていると、ある瞬間に、ぱっとできるようになる。これをしたら手の動きが速くなる、これをしたらもっと上手に切れるようになる、と。そういう発見を積み重ねてやってきました。そして自分でもかなりできるようになったと思っていたところだったんです。だからこそ、新しい店に入っても、自分はすぐに部門シェフを任されたんだって、密かに自負していました。自分が世界一とは言わないけれど、本心を明かせば、世界一とそれほど大きな差はないというところくらいまでは来ていると思ってたんです。ところが、とんでもなかった。そのとき、これは怖い世界だなって思いました。包丁のことだけじゃないということに気づいたんです。今回はたまたま包丁に目が行っただけのことであって、ミシェル・ブラスが見ている世界というのは、お皿の選び方から、盛りつけから、火入れから、何から何まで全部、そのレベルでやってるんじゃないかって思ったんです。私には見えてなくて、ミッシェル・ブラスにだけ見えてる世界があるんじゃないか。少し包丁が上手く使えるようになったくらいのことで、どうして私は慢心なんかしてたんだろう。しかも、その私が鼻にかけていた包丁の技術も、ミシェルの目から見たら児戯に等しかった。そう思ったら、急に怖くなった。自分はなんという世界に挑んだんだろうって」
ミシェルは包丁を肇に返すと、そのままどこかへ行ってしまった。
それで話が終わったわけではない。
翌日、肇がふたたび鳩を用意していると、目の端にミシェルが近づいて来るのが見えた。昨日と同じように、少し離れた場所で立ち止まって肇の手元を見つめているのが、気配でわかった。
心臓が早鐘のように鳴った。鳩肉を押さえる左手にも、包丁を持つ右手にも、ミシェルは余計な力を加えていなかった。その動きを思い出しながら切った。手元に感じる視線が、痛かった。
「ノン」
短くそれだけ言って、ミシェルはすっと離れていく。
何度も、同じことが繰り返された。肇が肉を切っていると、ミシェルが近づいて来てじっと見つめる。首を横に振る。
「ノン! セ・パ・ビヤン」
そのうちミシェルがこちらに歩いてくるだけで、背中を嫌な汗が流れるようになった。
喉はカラカラだ。それは、肇には妙に馴染みのある感覚だった。調理師学校を出て最初に修業に入った大阪のあの店で、シェフが近づいて来たときのことを思い出した。こういう汗をかくのは、あのとき以来だ。
ミシェルの手の動きは、脳裏に焼きついていた。生肉とはまた別の、火を通した肉の切り方があるようだった。押して切るのではなく、刺身のように引いて切る。刃が肉にあたるまではゆっくりしているが、切り始めると速い。その動きのどこにも迷いがない。
その動きはわかったし、自分も同じように手を動かしているのだが、何かが微妙に違う。その微妙な違いが、何もかもをぶちこわしにするくらい大きかった。
ミシェルのように切ると、どうしても肉が動いてしまうのだ。
どうしてそれができるようになったのかは、よくわからない。ただ、ミシェルに見つめられ、背中に冷や汗をかきながら何度も何度も手を動かしているうちに、いつのまにかできていた。
冷や汗をかきながらミシェルの目の前で肉を切り続け、5日目か6日目のことだ。切ることを忘れ、無心で包丁を動かしていた。肉がはらりと、3つに分かれた。
思わず顔を上げると、ミシェルが小さく頷いた。頰に満足そうな笑みが浮かんでいた。
「切ろう切ろうとしているうちは駄目だったんです。切ることを忘れて、切るというか。あくまで感覚的な話だけれど、切るんじゃなくて、境目みたいなものがあって、そこで肉を分けるという感じに近い。自分でもその感覚がつかめたと思った瞬間があって、それからミシェルはもう来なくなったんです。次に声をかけられたのは、確かミシェルが明日は帰国するという最後の日でした。『ハジメ、ちょっと』って呼ばれて、そんなことめったにないから、何だろうと思ったんですけど。厨房の片隅で、ミシェルにこう言われました。『これで完璧だと思ったら、それはもう完璧ではない。この世に完璧というものはない。ただ完璧を追い求める姿勢だけがあるんだよ』って。
それを聞いたとき、ここでの修業は終わったと悟りました。もう辞めなきゃいけないって。辞めることは決めてたわけだけど、その決断は間違ってない、自分はもう辞めるべきだと改めて確信しました。ミシェルから学ぶことはもうないと思ったわけではありません。そこにいれば楽しいし、仲間もいるし、仕事のやりがいもある、なによりもミシェルが次から次へと生み出す新しい料理を間近に見ることができる。だけどそれは、あの人がやっていることとは違うんです。私も、あの人のようにあがかなきゃいけないと思ったんです。あれだけ成功して、世界から認められているのに、一皿の料理をお客さんに出す直前まであの人はあがいていた。料理人の世界の頂点にいるのに、まだ先があるという目をしているんです。すごいと思った。じゃ、自分はなんなんだろうと考えると、もう自分でやるしかないと思ったんです。『完璧だと思ったら、それはもう完璧じゃない』。だから、彼はあがき続けてるんです。お前ももっとあがきなさいって、あの人に言われた気がしました」
その日から3ヶ月後の2007年3月1日に、肇は『ミシェル・ブラス』を辞め、妻と二人で兵庫県の実家に戻り、自分の店を開業するために物件探しを始める。
陽子のお腹には、二人の初めての子供が宿っていた。
肇は34歳になっていた。
少年時代の彼が想像した通り『ジャガイモとか、タマネギの皮、むきばかり』の修業時代をついに乗り越えて『いちりゅうの料理人』になるという夢を実現する未来が、ついにやってきたのだ。
もちろん、それはそんなに簡単に実現できることではないのだけれど。
(「第六章 これで完璧だと思ったら、それはもう完璧ではない。」より)
※この連載は、『天才シェフの絶対温度 「HAJIME」米田肇の物語』の試し読みです。
つづきは、書籍をお手にとってお楽しみください!
天才シェフの絶対温度
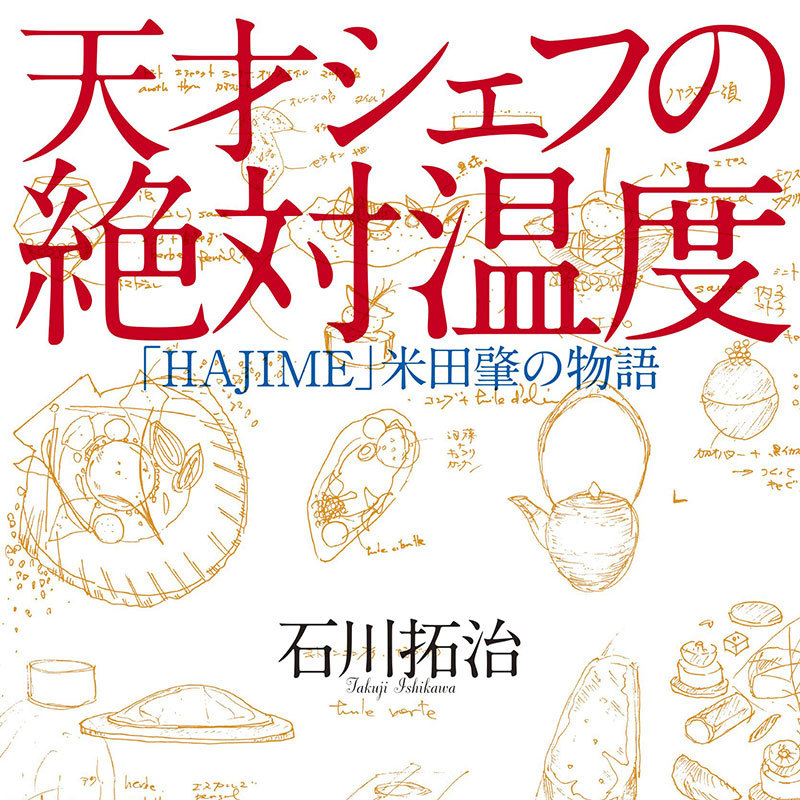
開店から1年5ヶ月の史上最速で、ミシュラン三つ星を獲得!
心揺さぶる世界最高峰の料理に挑み続けるシェフ・米田肇のドキュメント。
















