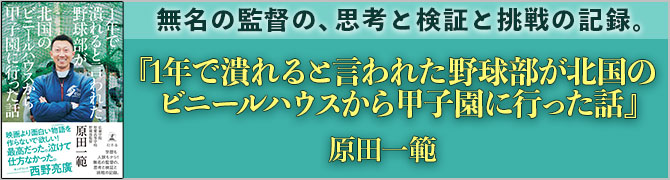2017年最初のキャラノベは、『露西亜の時間旅行者 クラーク巴里探偵録2』。明治時代のパリ、曲芸一座で働く敏腕番頭・孝介と料理上手で一途な見習いの晴彦が、贔屓筋から持ち込まれた難題を解決します。このシリーズの第1弾である『クラーク巴里探偵録』の試し読みを3回にわたってご紹介! ストーカー退治を請け負う「凱旋門と松と鯉」をお楽しみください。
◇登場人物紹介
片桐孝介 無口で几帳面。曲芸一座の贔屓客を相手にする名番頭
山中晴彦 家事が得意で世話好き。座長にスカウトされた料理番
座長 美しい傘芸を披露する曲芸一座のボス。無類の女好き
* * *
「大使館にも近いから、寝坊しても安心ですね」
晴彦は今、歩いてきた大通りを振り返った。
この通りをまっすぐ歩いていけば日本大使館に辿り着く。
「こんないい地所に下宿屋を持てたんだから、ここのマダムはだいぶ金を貯ためてたんだろうな。それとも死んだ旦那が年寄りの小金持だったか。下宿人が若い男ばかりとなると、パトロンに金を出させたわけでもないだろうが」
「下世話ですよ、孝介さん」
「育ちが悪くてな」
そのときちょうど玄関が開いて本多が顔を出した。
「二人とも、よく来てくれたね。刻限通りだ」
中に足を踏み入れた途端、晴彦は目をみはった。
壁一面に絵葉書が飾られてあったからだ。
天使や幼い少女、美しい景色に花束といった絵柄の物が多い。
「マダムのご趣味ですか」
孝介が訊ねると、本多が笑ってうなずいた。
「こっちはもっと凄いよ」
そう言って本多が食堂に二人を案内した。
部屋の中央には大きな楕円形の卓子が置かれており、その上に季節の花が飾られているのはどこの家でも同じだろうが、違うのは、こちらの壁にもぎっしりと絵葉書が並んでいるところだ。
晴彦は唸った。
「壁紙が見えませんね」
「圧巻だろう」
本多が片目をつぶって続けた。
「マダム・クラリスはつつましい方で、何であれ贅沢などしないんだが、絵葉書にだけは別でね。浮ついたところのない女性なのに、絵葉書のこととなると夢中になってしまう。その様子が少女のように愛らしいんだ」
本多にかかると、どんな話題でも最終的にはマダムの賛美になってしまうようである。
壁に視線を走らせて孝介が言った。
「日本の絵葉書も多いですね」
「戦争に勝ったせいか、また日本ブームが起きていてね。右肩上がりで輸入量が伸びているそうだよ」
露西亜との戦争は昨年終結し、講和条約が結ばれていた。
戦時中から、それぞれの戦地で勝利を収めるたびに記念の絵葉書が作られていたのを、晴彦は覚えていた。
「ところで今日は、忙しいだろうにすまなかったね」
さしてすまなそうに見えない本多に、孝介が首を横に振った。
「とんでもありません。本多さんにはいつもお世話になっているのですから。少しでもお役に立てれば嬉しいです」
「それにしても、那須一座は相変わらず凄い人気だね。券が取れなくてなかなか観にいけないんだよ。僕が座長の傘芸の話をしたら、マダムがそりゃあ羨うらやましがってね。一度は観てみたいと言っていたよ」
すかさず孝介が胸の隠しから券を二枚取り出した。
「招待券です。是非、マダムと一緒にいらしてください。本多さんから日本の衣装や背景の説明をして差し上げれば一層楽しめることでしょう」
「いいのかい」
本多が嬉き々きとして手を伸ばしたのと、食堂の扉が開いたのは同時だった。
「マダム・クラリス」
本多が嬉しそうな声を上げる。
栗色の髪を結い上げた小柄な女性が入ってきた。
肩から腕にかけた部分がたっぷりとふくらんだブラウスを着て、腰から流れるような長いスカートをはいている。
そして本多が自慢するだけあって美しい女性だった。
「マダム。こちらが私の友人で那須一座の方々です」
「お会いできて光栄です」
晴彦と孝介はそれぞれに挨拶した。
「こちらこそ光栄ですわ。クラリス・エイメと申します。──あのう、お二人とも綱渡りをなさいますの?」
クラリスが目を輝かせて晴彦と孝介を見上げた。
「申し訳ありません、マダム。私たちは裏方で、舞台には立ちません」
「そうなんですか」
孝介が謝ると、クラリスが素直にがっかりした表情を見せたので、本多がすかさず招待券の話をすると、その顔がぱっと明るくなった。
「まあ、まあ。滅多に手に入らない券を二枚もいただけるなんて、嬉しいですわ。父もきっと喜びます」
その一言で本多の野望は打ち砕かれたが、そこは外交官、すぐに体勢を立て直してクラリスに笑顔を向けた。
「本当にマダムはお父さん思いでいらっしゃる」
だが、クラリスは小さく首を振った。
「下宿屋の仕事が忙しくて、満足に親孝行もできないんです。親子二人こうして食べていけるのですから、文句を言っては罰ばちが当たりますけれども……。でも、父だってせっかく田舎から巴里に出てきたんですから、いろいろ見て回りたいと思っているに違いないんです」
「マダムのお気持は充分伝わっていると思いますよ。この界かい隈わいでも、マダムのような娘を持てるなんて幸せな父親だと評判なのですから」
力をこめてそう言った本多に、クラリスが「メルシー」と言って照れたような表情を見せた。
「そうそう、そうでなくては。マダムは笑顔が一番ですよ。その太陽のような笑顔を覆い隠す雲を吹き払う風に、私はなりたいのです」
「まあ、ムッシュウ・ホンダ」
本多がさり気なくクラリスの手を取って続けた。
「そのために、那須一座のお二人もお呼びしたのです。彼らは世界中で公演を行っていますから、様々な人生を見聞きしておりますし、また一筋縄ではゆかぬ問題も乗り越えてきているのです。私はもちろん全力を尽くしますが、きっと彼らもマダムの力になってくれるでしょう」
巴里にいると日本の男もこんなに口がうまくなるのか、と晴彦は感心した。
これなら日本男児がシャンゼリゼで歌いながら踊る日も近いに違いない。
「一ケ月ほど前のことでした」
四人が卓子を囲むようにして腰を下ろすと、クラリスが組んだ指に視線を落としたまま話し始めた。
「部屋が空いていないかと言って、若い男の方が訪ねてきたんです」
この近所で良い下宿屋がないか探していたところ、クラリスの下宿を勧められたという。
だが、あいにく部屋はすべてふさがっていた。
クラリスがそう答えると、男は残念そうな様子を見せたが、もし空きができたら是非置いてほしいので、と部屋代や食事の時間等を訊ねた。
特に、どんな下宿人がいるのか熱心に知りたがっていたが、同じ屋根の下で暮らすことになれば誰でも気になることなので、そのときはさほど気に留めなかった。
男は礼を言って帰っていったが、見送った後、クラリスは男が住所を置いていかなかったことに気づいた。
そもそも名前すら、男は言わなかった。
これでは連絡できないではないかとクラリスは呆れたが、おっちょこちょいな人もいるものだと思っただけで、その男のことはそれきり忘れていた。
「それから一週間くらい経った頃だと思います。肉屋のエンマさんが、私のことをいろいろと訊きにきた男がいると教えてくれたんです」
本多がふんと鼻を鳴らした。
「あの丸太のようなお内儀ですね。一日中、人の噂話ばかりしているという話だ。マダムがつきあうような女じゃありませんよ」
「そんなことありませんわ。エンマさんはいい方です。いつもお肉をおまけしてくれますし」
「おまけ」に力をこめたクラリスに、晴彦は思わず噴き出した。
「あらまあ、私ったら」
そう言って顔を赤くしたクラリスを見て晴彦は目を細めた。
本多などすっかり鼻の下が伸びている。
そんな中、唯一態度も表情も変わらないのが孝介だった。
「その男はどんなことを調べていたのですか」
孝介が訊ねると、クラリスはうつむいたまま、しばらくためらっていたが、やがて小さな声で言った。
「エンマさんがおっしゃるには、その──下宿人の方やこの辺りのお店で、私と特別に親しい方はいないかと」
「あの丸太め」
本多が音を立てて立ち上がった。
「待ってください、ムッシュウ・ホンダ。エンマさんは言ってくださったそうです。この下宿屋には私の父も同居しているし、そんなふしだらなことはないと」
本多が再び乱暴に腰を下ろした。
孝介が続ける。
「エンマさんが言っていた男と、部屋を借りにきた男は同じ人物でしょうか」
「ええ、私、顔を見たんです」
クラリスが肉屋で買い物をしていたとき、エンマが小声でささやいたという。
──ほら、例の男だよ。隣の店の前に立ってる。
クラリスが他の棚を見るふりでそれとなくうかがうと、若い男が窓硝子越しに店の中をのぞきこんでいるところだった。
その顔には確かに見覚えがあった。
顔色の変わったクラリスを見て、エンマが声をひそめた。
──知った顔かい。
──先日、下宿先を探しにいらした方です。
──うまい口実だ。
エンマが一人合点してうなずいた。
──きっと、あんたに気があるんだよ。最近、この辺りでちょくちょく見るからね。大方、他の店の連中にも聞いて回ってるんだろう。この節、巴里にもおかしいのが増えてきたよ。気をつけな。
エンマが心配と好奇心の入り混じった顔で言った。
「その頃から、私もその方をしょっちゅう見かけるようになりました。私がいつも行くお店や時間をよくご存知のようで……」
声を震わせたクラリスを気遣うように、孝介が優しく訊ねた。
「その男は貴女に話しかけてくるのですか」
「ええ。と言っても、たいしたことは話しません。先日はどうも、とか、良いお天気ですね、といった程度です」
「しかし貴女はその男に何か不審を感じていらっしゃる」
「何がおかしいというわけではありませんの。こちらのムッシュウ・ホンダのように──」
そう言ってクラリスが本多に微笑ほほえみかけた。
「上品で、教養ある方だと思いました。ただ、どことなく怖いような気がするんです。うまく言えませんが」
「このようなことをおうかがいして大変申し訳ありませんが、こういったことは以前にもありましたか」
「何度か……」
赤くなったクラリスが小さくなってうなずいた。
本多は面白くなさそうな顔をしているが、この美女なら言い寄ってくる男など掃いて捨てるほどいるに違いない。
「ですけれど、私、下宿屋の仕事が忙しいですし、夫のことを忘れられないんです。その──好意を打ち明けてくださる方もいらっしゃいましたが、その都つ度ど、きちんとお断りしてきました」
「これまで貴女に好意を寄せてきた男たちにも、その男と同じような怖さをお感じになりましたか」
クラリスが首を横に振った。
晴彦はそっと横目で孝介の様子をうかがったが、さすがに彼も考えあぐねているようである。
美貌の女主人についてあれこれと聞き回り、彼女のまわりに頻繁に姿を見せる男がいる。
だが、何かされたというわけではなかった。
今のところは気にしなければそれですむ話だが、いずれどうなるか分からないし、何よりクラリス本人が気味悪がっている。
結局、はっきりとしたことは言えないが、こちらでもできるだけ調べてみると言って二人は席を立った。
食堂を出ようとするとき、孝介が立ち止まった。
「あれは日本の物ですね」
部屋の中央にある暖炉の上にも数枚の絵葉書が飾られていたが、その中の一枚が一際、目を引いた。
松と鯉の絵柄は、晴彦の目にも簡素で美しかったが、周囲の絵葉書が華やかなだけに異彩を放っている。
「亡くなった主人が送ってくれたものなんです」
クラリスが絵葉書を手に取って視線を落とした。
「私のために珍しい物を手に入れようとして、いつも骨を折ってくれていました。観光客の多い場所で給仕ギヤルソンをしてましたから、いろんな国の方から絵葉書を譲り受けることができたんです。もちろん、日本の方からも」
「そうでしたか」
「郵便受けに入っていたら驚くだろうって、わざわざ投函するんですの。切手代が勿もつ体たいないわって言っても笑って聞かなくて。──そう、覚えてますわ。この絵葉書が届いた日は雨でした。私、大慌てで乾かしましたもの」
差し出されて、孝介が受け取った絵葉書を、晴彦もまた脇からのぞきこんだ。
消印はすっかりにじんでいたが、クラリスの住所と名前、そして夫の名前だろう、アランという署名がくっきりと読める。
「私、不思議とこの絵柄が好きなんです。何だか心が落ち着くようで──」
「いえ、分かりますよ」
孝介はそう言って微笑むと、下宿屋を後にした。
「雲をつかむような話ですね」
言いながら晴彦はため息をついた。
「ちょっと考えすぎという気もしますが、美人は美人なりの悩みがあるのかもしれませんね」
「お前、ああいう女が好みか」
孝介が横目で晴彦を見た。
「孝介さんだって綺麗だとお思いになったでしょう」
「気がつかなかった」
「素直じゃありませんね」
「顔が綺麗だからって、心まで聖女のようだとは限らないさ。腹の底までは読めないからな」
晴彦の脳裏にふと、座長の言葉がよみがえった。
知らず歩みが遅くなる。
──ガキの頃から嫌な目にばっかり遭ってるからな。人に期待なんかしねえようになってるんだが、その分、信じたら弱いのさ。
欧州興行界でもその名が鳴り響く那須一座の番頭として、普段の孝介は絶対の安心感を与えてくれる存在だったが、時おり彼が年下なのだということを、晴彦は思い出すことがあった。
孝介の厳しいまでに突き放した態度を見ていると、強くならなければ生き抜いてこられなかっただろうこれまでの道程を思って、かすかな哀しみも感じた。
先を歩いていた孝介がふいに振り返って言った。
「マダム・クラリスについて調べてみよう。ハル、手伝ってくれ」
晴彦は驚いて駆け寄った。
「つきまとっている男のほうじゃないんですか」
「そっちは手がかりがないからな。とりあえずマダムだ」
「ですが、マダムは通りすがりの男に岡惚れされて困っているだけでしょう。どうしてマダムを?」
孝介の口元が皮肉そうに歪んだ。
「お前、どうせ調べるなら美女のほうがいいだろう?」
※この連載は、『クラーク巴里探偵録』p.112~の試し読みです。続きは、ぜひ書籍をお手にとってお楽しみください。