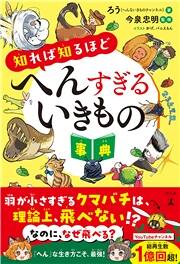いきものの解説が人気のYouTubeちゃんねる「へんないきものチャンネル」の“中の人”、ろうさんの新刊『知れば知るほどへんすぎるいきもの事典』から、興味深いいきものの豆知識をピックアップしてお届けする本企画。
今回は、ちょっと趣向をかえて、いきものにまつわる“税金”のお話。
驚くべき税金の背景には、明治時代に起こったある「バブル現象」があったのです。
* * *
ただ飼っただけで?「うさぎ税」が取られる時代があった?
消費税、所得税、住民税、贈与税などなど……税金にはたくさんの種類があるよね。
「お金が追加で取られるなんて……」と不満に思う人もいるかもしれないけれど、そのお金が回りまわって、みんなの生活を支えているんだ。
でもね、じつは明治時代には、現代では考えられないような、変な税金があったんだ。
それはなんと、「うさぎ税」。
飼育されているうさぎの数に応じて、1匹につき月1円(現在の約1万円)を支払わなくてはいけなかった。
確かにうさぎはとてもかわいくて見とれてしまう生きもの。
国が「かわいくてかわいくて、仕事も手につかない! これでは困るな~」とうさぎ税を作った……わけではなく。
お金目当てで飼育する人を減らすのが目的だったんだ。

流通量も少ないうさぎは高価で、庶民の手が届くペットではなく、一部の裕福な商人しか飼っていなかった。
さらに明治時代に入ると外国種のウサギが流通するように。
毛皮を毛布にしたり、食用にしたりもできると、需要が高まった。
東南アジアなど海外から輸入された珍しい子ウサギは、およそ20万円、最高では1200万円という超高額で売られることになり、「うさぎは稼げるぞ!」と、うさぎビジネスに人が殺到!
当初は絵画のように、一部の富裕層が参加するオークションのような取引がされていたんだけど、一般の人も本業を投げ出してうさぎで一儲けしようとしたため、社会的な混乱が起こったんだ。
このパニックを抑えるために、うさぎ税が導入されたんだけど……届け出をせずに飼育してウサギを売買する闇取引が絶えなかった。
東京府はその後、うさぎの競売を禁止。
過剰に繁殖したうさぎは、今度は売れ残って値下げ競争が起こった。
そうしてバブルが弾け、うさぎ税は廃止となったんだ。
ちなみに、日本には「犬税」、中世のフランスには「カエル税」といった税もあったんだとか!
知れば知るほどへんすぎるいきもの事典の記事をもっと読む
知れば知るほどへんすぎるいきもの事典
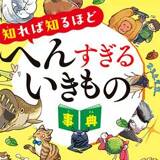
へんないきもののネタを50集めた児童書『知れば知るほどへんすぎるいきもの事典』の試し読み記事です。
たとえば……
・牛66頭を襲ったヒグマは、実は、熊同士の闘いに負けていた〈OSO18〉
・プロボクサーより早いパンチを繰り出す海の生きもの〈モンハナシャコ〉
・噛まれたら10分で死んでしまう殺人グモ!? 〈シドニージョウゴグモ〉
・体が大きいのに泳ぐスピードも速い人食い魚〈ムベンガ〉
・世界で唯一、血液を食べものにする鳥〈フィンチ〉
・人間の貴重品をあえて狙う泥棒ザル〈カニクイザル〉
などなど……面白いいきものの生態がたくさん! 子どもと一緒に大人も楽しめます!