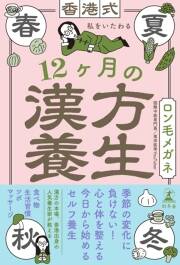漢方の本場、香港出身の人気養生家でYouTubeチャンネル@rongemeganeで東洋医学の知識を発信しているロン毛メガネさん。新刊『香港式 私をいたわる12ヶ月の漢方養生』では、24節気ごとに取り入れたい食べ物、生活習慣、ツボ、マッサージなど、季節の変化に負けないセルフ養生を詳しく紹介しています。本書より、一部をお届けします。
* * *
10月の節気は、寒露と霜降です。この時期を「深秋」または、「晩秋」と呼びますね。
香港では、陰暦の9月9日に「重陽節」という祝日があり、その由来は陰陽思想の古典『易経』に記されています。昔の人は奇数(1、3、5、7、9)を「天数」、偶数(2、4、6、8)を「地数」と呼び、中でも数字の9を「陽数」と呼んでいました。9月9日は9が重なるので、「重陽節」または「重九節」と呼ぶわけです。面白いですね。
そして、重陽節といえば、香港では遠足や山登りをしたり、広い公園で凧揚げをしたり、菊のお花見をしたりするという風習があります。陽が重なる日に大自然に触れることによって、邪気を追い払う、運気を良い方向に運ぶ、厄払いをするという意味があるようです。
寒露の生活習慣と食事のヒント
香港では「中秋過後夜夜涼」という言葉があって、中秋を過ぎると徐々に寒くなっていくという意味です。
寒露に入ると、乾燥だけではなく、寒さが一層深まっていきますね。白露の時よりも朝と夜の気温が下がってきて、結露が増えてくる頃なので、寒露と呼ぶわけです。
生活習慣
この時期、体の陽気は内側に戻り、夏とは違って陽気が外側に向かって積極的に活動しなくなります。そろそろ陽気の消耗を減らすように意識し、陽気を体内に蓄えて、冬を迎える準備をする頃です。
前にも書いたのですが、秋は悲しくなりやすい、切ない気持ちになりやすい季節なので、大自然に触れることを意識すれば、体を動かすことができて、心を癒やすこともできます!
東洋医学では、心の健康は体の健康に影響を与えると考えるので、もしこの時期に悶々としたり、うつ気味でやる気が出なかったら、一人でもいいのですが、秋は悲しくなりやすくて、寂しさを感じやすいので、ぜひ友達を誘って公園や山に行きましょう。
そして、秋分に引き続き運動をしてください! 東洋医学では、「動則生陽」という言葉があって、体を動かすことによって陽気が生まれると考えます。
夏のように自然界に陽気が溢れているわけではないので、陽気を養うために、秋は運動量を少し増やしてみるといいです。しかし、試合のような、誰かと競争するような運動は控えましょう。
誰かと争うと心が落ち着かないですよね。秋にする運動は、動きがゆっくりで、激しくない、何も考えなくてもできるものがいいので、ストレッチやヨガ、お散歩、水泳、ジョギングなどがおすすめです。
食事
この時期は、乾燥がさらに強くなってくるので、秋分に引き続き、体を潤してくれる白い食べ物を取り入れましょう。
白い食べ物と聞いて、乳製品でもいいじゃないか!? ヨーグルトを食べて腸内環境を良くして、体を潤すこともできれば最高! と思う人がいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。もちろん、乳製品には体を潤す力があります。ただ、その効果は胃腸が絶好調で、元気な人に限ります。5月の養生でも触れましたが、乳製品は湿気を吸収してベタベタする性質があり、かえって胃腸にとって負担になります。
たまに食べるのはいいかもしれませんが、毎日乳製品を食べたり飲んだりするのはあまりおすすめできませんね。
しかも、アジア人の7~9割は乳糖不耐性なので、実は乳製品は向かない人がとても多いです。
腸内環境を整えたい、体を潤したいと思ったら、乳製品ではなく、ぜひ温かいお味噌汁に豆腐やれんこんを入れてみてください。
そして、寒さが強くなってきて、「寒燥」の状態になりやすく、喉や鼻の不調が出やすくなります。例えば、喉が痛い、喉が乾燥して痒い、鼻が乾燥する、空咳が出る、喘息気味などですね。これらの症状が出た人は、生姜、にんにく、ネギなど体を温める食材を控えましょう。
乾燥しているところに火をつけると燃えやすくなるように、体も潤いが足りなくて乾燥している時に生姜のような温める力が強い食べ物を食べると、体の内側が火事になり、炎症やニキビなどを引き起こす恐れがあります。
特に冷え性の人は、この時期に体を温め始めると思いますが、要注意です。夏の章でも書きましたが、冷え性の改善に取り組むのは三伏天の間がベストタイミングなので、冷え性の人は、秋冬ではなく、夏に生姜やにんにくなどを取り入れましょう!

香港式 私をいたわる12ヶ月の漢方養生の記事をもっと読む
香港式 私をいたわる12ヶ月の漢方養生

香港出身の人気養生家、ロン毛メガネさんの新刊『香港式 私をいたわる12ヶ月の漢方養生』が9月29日に発売となりました。本書より、試し読み記事をお届けします。