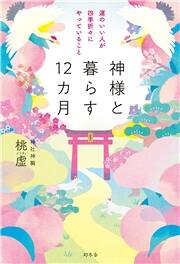この季節、「菊の花」を食すことを、考えてみましょう。最後に簡単な食べ方も紹介されています!
神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。
* * *
花を食べる
現代で菊の効能を体に取り入れるなら、食用の菊花でしょうか。
おもに薬用として栽培されてきた菊の花を、「食べる」という文化が発生したのはいつごろからか、はっきりとはわかっていませんが、江戸時代の文献には菊花を使った料理が記されていて、俳人の松尾芭蕉のお気に入り食材だったとも言われています。
9月9日の重陽の節句の時には「寿」という黄色い菊の品種が出まわり、各家庭で菊料理を食べて健康と長寿を願ったそうですよ。
へえへえ。と感心したところで、ざっと、食用菊の栄養とその効能をあげてみますね。
ビタミンE:強い抗酸化作用。
ビタミンK:骨の健康。カルシウムの吸収を助ける。
ビタミンB1:糖質の代謝。
ビタミンB2:皮膚、粘膜、髪、爪などの再生。
葉酸:細胞の生産と再生。
クロロゲン酸:強い抗酸化作用。
やはり、目立つのは「強い抗酸化作用」、アンチエイジング効果ですね。
お刺身(関西では「おつくり」と言います)の「つま」に、小菊の花が使われていることがありますよね。彩りに加えて、菊の精油には解毒作用があるからだそうです。花びらをちぎってお刺身にふりかけるなどして、食べるとよいそうです。
材としての菊花は、スーパーなどで、花の部分だけを摘んだものや、花びらだけのものがビニール袋やパックに入れて売られています。
食べるのは花びらの部分だけ。沸騰したお湯に、酢を少々入れて、花びらをさっと湯がきます。
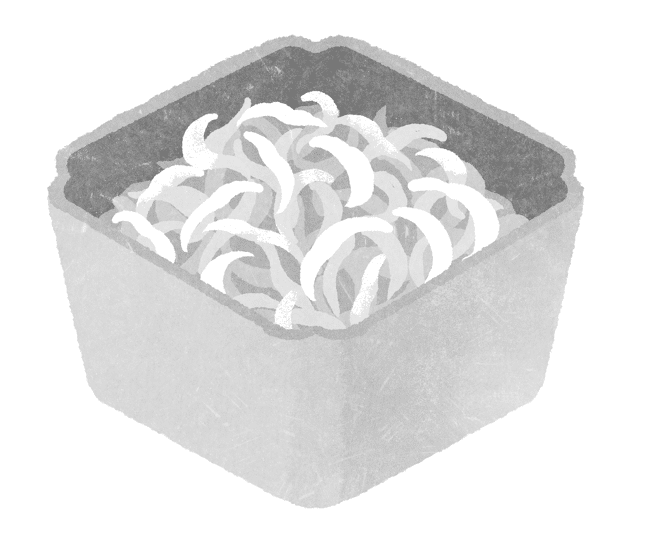
すると菊の花の色が清らかに、あかるく発色します。「湯がく」とは、余分なものを取り去って本来の清らかな色を出す日本の調理法。ここにも「清め」の概念があります。
湯がいた菊の花はざるに取って冷水にさらし、ぎゅっとしぼって水気を切り、お醤油かけて食べてもおいしいですし、ごはんにまぜたり、ほうれん草とまぜたり、なめこや大根おろしと和えたりします。ごま和え、くるみ和えも、おいしくて栄養があります。酢の物もいいですね。
(つづく)
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること
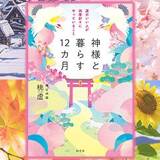
古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!
* * *
神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。
- バックナンバー
-
- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...
- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...
- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...
- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...
- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...
- 神々がしていることを真似すると、運が開く...
- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...
- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...
- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...
- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...
- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...
- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...
- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...
- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...
- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...
- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...
- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...
- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...
- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...
- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...
- もっと見る