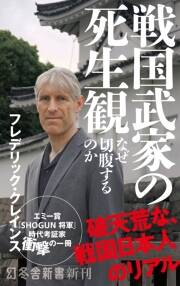ハリウッドにて制作が決定している『SHOGUN 将軍』シーズン2。新キャストとして、Snow Man・目黒蓮さん、水川あさみさん、
シーズン1にひきつづき、
* * *
浅井長政の配慮が伝わる「最期の感状」
主従の関係が倫理規範によってほぼ固定化されていた江戸時代とは異なり、より人間的な関係性が重視されていた戦国時代の主君には、当然ながら、家臣の忠義をつなぎとめるだけの個人的な魅力が求められていました。
軍事的な才能だけでなく、指導者としての求心力が問われていたといえます。戦国の武士たちを心服させた武将とは、どのような人物であったのでしょうか。
たとえば、北近江の浅井長政は、その誠実な人柄が家臣たちから慕われたと伝わっています。実際、元亀四(一五七三)年八月二九日付で家臣の片桐直貞(のちに豊臣秀頼の家老を務めた且元の父)に宛てた感状には、そうした評価を裏づけるような痕跡が示されています(石川武美記念図書館蔵)。
この感状は織田軍の攻撃を受けて小谷城が落ち、長政が自刃する前日に記されたと見られ、研究者の間では「浅井長政の最期の感状」としてよく知られる史料です。
書状のなかで、長政はすでに本丸を残すのみとなった敗勢にもかかわらず、自分に付き従ってくれた直貞を「忠節抽んぜられ候」として称賛し、その比類のない勇敢な覚悟に対する感謝の気持ちは書き尽くすことができないと述べています。
注目すべきは、この感状が縦一〇センチ弱、横二三センチの当時としては小さな紙片に記されていることです。これは、織田軍に包囲された小谷城から脱出しなければならない直貞の苦難を慮り、懐中に隠しやすいようにと工夫された長政の心遣いであったと考えられています。
当時、主君から与えられた感状は、再び仕官する際に自身のキャリアを証明する役割も果たしていました。間もなく城が落ち、みずからも命を絶たなければならない絶望的な状況のなかで、長政は家臣が無事に生き延びることを願い、未来の再就職先への推薦状を与えたのです。こうした主君のためなら、命懸けの奉公もいとわないと考える武士は少なくなかったでしょう。

別所長治はなぜ信長に反旗を翻したのか
浅井長政の事例と同様に、主君と家臣たちの強い絆を想い起こさせるのは播磨の別所長治の逸話です。

別所家に仕えていた来野弥一右衛門が主家の事績を後世に伝えるために記したとされる「別所長治記」と、秀吉の御伽衆の一人であった大村由己による『天正記』のなかの「播州御征伐之事」に依拠して、物語風に紹介します。
初めて織田信長に拝謁したのは、天正三(一五七五)年、別所長治が一七歳になる年の秋のことであった。上段から浴びせられる強い視線を全身に感じながら、長治は父と同様、信長に忠節を尽くすことを誓った。
小さな勢力が割拠していた播磨において、三木城を本拠として東八郡に勢力を広げていた別所家は近隣で最も有力な大名であった。彼の父安治は、信長が足利義昭を奉じて上洛したころから織田家に従い、その武勇が信長に称賛された。だが、元亀元(一五七〇)年に亡くなったため、長治が二人の叔父の後見を得て、一二歳で家督を継いだ。
天正四年も京都に信長を訪ねて変わらぬ忠義を示した長治は、天正五年二月、信長が雑賀衆の征伐に出陣すると、叔父を名代として軍勢を紀伊へ差し向け、織田軍に加勢した。彼は、信長のもとで家運を切り拓こうとしていた。
ところが、同年、播磨の平定という使命を帯びて羽柴秀吉が赴任してくると、長治は信長に不審を感じた。秀吉の尊大な振る舞いを見ているうち、信長は別所家を利用しようとしているのではないかという疑念が生じたのである。とりわけ許しがたく思われたのは、秀吉が別所の家臣を下僕のようにあしらったことであった。
織田には従ったが、羽柴の家臣になった覚えはない──。
成り上がり者の高慢な言動には憤りを覚えたが、長治は感情を抑え、秀吉への協力を続けた。だが、天正六年、信長から中国地方を支配する毛利家の討伐を知らされ、その先鋒を務めるよう要請されたとき、彼は信長のもとで家運を切り拓こうとした自身の思惑がはずれたことを悟った。
信長は、中国地方の平定を終えれば、彼に播磨一国の支配権を与えると約束したうえ、さらなる恩賞も提示した。しかし、それが方便にすぎないことは、秀吉の思い上がった振る舞いが証明していた。すでに秀吉は播磨の国衆を家臣と同様に見ており、毛利家を討てば、用済みになった別所家も滅ぼされるのは明らかであった。長治は、重臣を集めて評議を重ね、織田家と手を切り、毛利家と結ぶことを決断した。
信長に反旗を翻した長治は、三木城を足場として秀吉に攻撃を仕掛けた。予想外の事態に秀吉は驚き、混乱したが、間もなく態勢を立て直すと、反撃に転じた。そして、野口と神吉の城を落とした。
三木城の支城を一つひとつ潰していった秀吉軍は、徐々に優勢を拡大した。対して、挽回をはかった長治は平山で合戦に挑み、弟の小八郎とともに奮戦した。
だが、兵力に勝る秀吉軍に大敗を喫して、多くの家臣を失ってしまった。残兵をまとめた長治は三木城に立て籠り、以後城門を固く閉ざして、毛利家からの援軍を待つことにした。
軍馬も食べ尽くす極限の飢え、籠城戦の地獄
徹底抗戦の構えを見せた別所軍に対して、秀吉は容赦なく包囲を狭め、三木城は完全に封鎖されてしまった。毛利家との連絡を遮断されたものの、主君の決断を支持していた将兵の戦意は衰えなかった。しかし、米蔵の蓄えが尽きると、別所方は籠城戦の過酷さを思い知ることになった。彼らは、糠や藁、草を食べて飢えをしのいだ。やがて、家畜や軍馬も食べ尽くした。城内は地獄になった。
痩せ衰えた別所方は動くこともできず、夜が明けると多くの者が死んでいた。人の道にはずれた恐ろしい光景が各所に見られ、そのうちかろうじて体を動かすことができた三〇〇名の若者たちが最後の抵抗を試みたが、その多くは鎧の重みにさえ耐えきれず、秀吉軍の弓矢の的にされるだけだった。
籠城を始めてから二回目の元旦が過ぎた天正八年一月一五日、長治は秀吉軍の浅野弥兵衛(長政)に書状を送り、降伏を申し出た。それ以上、家臣に極限状態を強いることが耐えがたかったのである。命を落とした者は、すでに数千名を数えていた。書状には、彼と弟の友之、叔父の別所吉親の三名が腹を切ることで、まだ生きている者たちを許してやってほしいと記されていた。
弥兵衛から報告を受けた秀吉は、彼の書状に目を通し、
「よい大将じゃ。家臣思いの、みごとな大将じゃ」
と言って落涙したという。そして、彼の申し出を認めるという返書とともに、二〇樽の酒と肴を城内に送った。
切腹の時刻は一七日申の刻(午後四時ごろ)と決められた。長治は、妻子や家臣たちとの宴を催し、残された時間を惜しんだ。
そして、当日を迎えると、まだ夜が明けきらないうちに長治は三歳の世継ぎを膝に乗せ、その後ろ髪を撫でてから小さな胸を突き刺した。続いて、その刀で妻の心臓を貫いた。弟の友之も、同様にして妻を一足先に旅立たせた。
妻子との別れを終えた兄弟は客殿の広間の畳に並んで座り、それぞれの準備を始めた。長治は少しも気色を変えることなく、むしろ穏やかな表情で笑みさえ浮かべていた。
「お供をする者もなく、無念でございます」
介錯を務める三宅治忠はそう言って、彼の後ろに控えた。
長治は腹に刀を突き立てると、作法に従って十字に切った。その姿を見届けた治忠は、彼の首を切った。友之も、刀や脇差、衣装を形見として周囲の者に分け与えた後、兄の後を追った。長治は二三歳、友之は二一歳であった。
翌日、城内の人々は約束どおりに命を助けられ、兄弟と吉親の首は秀吉によって京都の信長のもとへ送られた。
兄弟の辞世の句が伝えられている。
長治の辞世
いまはただ恨みもあらず諸人の 命に代わるわが身と思えば
友之の辞世
命をも惜しまざりけり梓弓 末の世までの名を思う身は
* * *
戦国武士の死に対する覚悟と美学について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『戦国武家の死生観』をお読みください。
戦国武家の死生観の記事をもっと読む
戦国武家の死生観
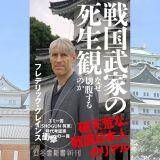
エミー賞「SHOGUN 将軍」
時代考証家・衝撃の一冊
戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。こうした戦国独特の価値観を古文書から読み解き、その知見をドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証に存分に活かした歴史学者が、戦国武士の生きざまを徹底検証。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。