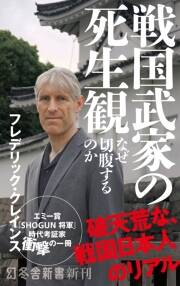ハリウッドにて制作が決定している『SHOGUN 将軍』シーズン2。新キャストとして、Snow Man・目黒蓮さん、水川あさみさん、
シーズン1にひきつづき、
* * *
武芸だけでなく、文化的教養も求められた戦国の武将たち
武士といえば刀の達人というイメージが現代では一般的です。たしかに、武士たちは武芸に長けていましたが、その一方で文化的活動にも熱心に取り組んでいました。次のような和歌が残されています。
歌連歌乱舞茶の湯を嫌ふ人 そだちのほどを知られこそすれ
この歌は、和歌、連歌、能楽、茶の湯といった芸道に優れていなければ、武士として失格であるという意味です。細川幽斎(藤孝)の作と伝えられていますが、真偽は定かではありません。とはいえ、この歌は当時の武士の精神をよく表現しています。

一見すると、戦国武士の荒々しい気質とは相いれないように思われるかもしれません。しかし、情緒豊かであったからこそ、その感情を表現する文芸に熱中したのではないでしょうか。
茶の湯は基本的に、戦国武士の人間関係と密接にかかわっていました。迎える側と訪問者がいて初めて茶の湯が成立します。戦国武士はよく仲間を訪問し、そのおもてなしとして茶の湯が発展したと考えられます。
また、能楽も武将たちの間で大人気でした。ただ観るだけでなく、自分で舞うことが重視されました。細川幽斎・忠興父子が能を演じた記録は、数え切れないほど残されています。秀吉も能にのめり込み、自分が主人公として描かれる演目を複数作らせました。これらは「太閤能」と呼ばれています。
武将たちが最も愛した和歌の世界
しかし、武将たちにとって最も特別な文芸は和歌でした。和歌は、この世の儚さを表現するのにぴったりの媒体だったのです。武士たちは熱心に和歌を詠みました。仲間との歌合や連歌会もあれば、一人でも創作しました。出陣する前にも、そして死ぬ直前にも歌を詠みました。当時の史料を見ると、必ずといってよいほど和歌が登場します。
彼らの和歌は、現代人が想像しがちな戦闘的なものではありませんでした。秀吉の辞世の句「露と落ち露と消えにし我が身かな なにはの事も夢のまた夢」のように、人生の無常や自然観察に焦点を当てたものが中心でした。
自分の和歌を編集した家集を残している武将も少なくありません。こうした家集に収められた歌を通覧すると、驚くほど率直で繊細な表現に満ちていることがわかります。たとえば、もともと古河公方の足利晴氏と義氏に奏者衆として仕え、後に北条氏の家臣となった一色直朝は「桂林集」という家集を残しています。その代表的な歌の一首は、次の通りです。
さやかなる月には猶もくもるらん 心ある人の秋の夜のそら
この歌は「澄みわたる月夜でさえ、やはり曇ってしまうのだろうか──人の心が晴れない、秋の夜空よ」というような意味です。この歌は、秋の夜に輝く美しい月と、それを見ても晴れない人の心を対比しています。自然の美しさと、悲しみや憂いを抱えている人間の感情の間にあるギャップを表現した和歌で、「うき身にはなかむるかひもなかりけり 心にくもる秋のよの月」という『新古今和歌集』に収められている慈円の作品を思い起こさせます。
この歌からは、戦国時代の武将が単なる武勇だけでなく、繊細な感性と深い洞察力をもっていたことがわかります。ゆううつや不安といった気持ちすらうかがえるでしょう。彼らは常に死と隣り合わせの生活の中で、自然や人生の儚さを鋭く観察し、それを美しい和歌として表現していたのです。一色直朝の歌は、繊細な武将の内面世界が垣間見える貴重な作品といえるでしょう。

武芸と歌の心を兼ね備えた「鬼武者」新納忠元とその妻
武家の歌のなかでとりわけ筆者の印象に残るものとしては、新納忠元とその妻の和歌があります。忠元は島津家の武将として数多くの合戦で武功を挙げた「鬼武者」として知られていました。秀吉の九州出兵のとき、島津の降伏に反対し、最後まで抵抗した一人であるほど勇敢な武将でした。
慶長一四(一六〇九)年二月に、忠元は妻を亡くしました。彼女は次の辞世の句を詠んでいます(「新納忠元勲功記」)。
弥陀頼む心さやけき有明の 月諸共に西へこそゆけ
「阿弥陀仏を頼りにする私の心は清らかです。有明の月と共に西方浄土へと旅立ちましょう」というような意味です。この辞世の句からは、戦国時代の武家の女性たちも高い和歌の教養を持っていたことがうかがえます。当時の上流階級の女性教育において、和歌は必須の教養とされており、感情や思想を洗練された形で表現する手段でした。
忠元の妻の和歌には、「有明の月」という優美な自然の比喩と「西へこそゆけ」という仏教の西方浄土を示す表現が巧みに組み合わされています。
「有明の月」(夜明け前にまだかすかに空に残る月)は、この世を去ろうとしている自分の命を表現し、同時に美しさと儚さを象徴しています。また、死を前にしても動揺せず、むしろ西方浄土への往生を穏やかに受け入れる心境は、彼女の揺るぎない信仰心を表しています。
このとき、忠元はすでに高齢でした。数多くの合戦で戦ったにもかかわらず、戦国武将のなかでもめずらしく長生きをしました。彼は妻の死から一年後の慶長一五年三月に次の和歌を詠んでいます。
さそな春つれなき老と思ふらん ことしも花の跡にのこれは
「誘いかける春よ、きっと私のことを情のない老人だと思っているだろうね。今年もまた、桜の花が散った後まで私は生き残ってしまったのだから」。前年に亡くなった妻への深い思慕と、自分だけが生き残った悲しみが込められています。
新納忠元の歌は言葉の重層的な意味を巧みに用いた高度な文学作品であることがわかります。戦国武将としての側面だけでなく、繊細な感性と高い教養を持ち合わせていた忠元の人物像がより鮮明になります。
この歌と妻の辞世の句を対照すると、妻が清らかな心で西方浄土へ旅立ったのに対し、忠元は取り残された寂しさのなかで生きていたことが対比的に表現されており、二人の深い絆が一層際立っているといえるでしょう。
歌道の力で城を守りぬいた細川幽斎
ちなみに、新納忠元は九州出兵のあとに人質として上洛した際、細川幽斎に和歌の指導を受けたようです。
幽斎は三条西実枝から歌道の最高秘伝である「古今伝授」を受け継いだ人物です。この「古今伝授」は『古今和歌集』の解釈を中心とした歌学の秘伝で、通常は公家の間でのみ継承されていました。武士の身分でこれを正式に継承したのは幽斎だけという、きわめて異例の存在だったのです。
関ヶ原の戦いの直前、東軍に与した幽斎は、息子の忠興が徳川家康の会津征伐に従軍したため、みずから丹後田辺城を守ることになりました。

田辺城には五〇〇人の兵しかいませんでした。これに対し、西軍は一万五〇〇〇人もの大軍で田辺城を包囲。数の上では圧倒的に不利な状況に陥りました。
しかし、西軍の攻撃は予想外に消極的でした。その理由は、西軍のなかに幽斎の歌道の弟子たちが多数いたからです。武将たちは、自分の歌の師を討つことに躊躇していたのです。包囲が始まった初期に一度だけ城に攻め入ろうとしましたが、そのあとはもっぱら鉄砲の打ち合いに終始していました。
特に興味深いのは、『寛政重修諸家譜』に掲載されている逸話です。幽斎の歌道の弟子の一人であった谷衛友は、密かに幽斎と内応していたといいます。武士としての忠誠よりも、歌の師弟関係を優先した例として語り継がれています。
事態を最も憂慮したのは後陽成天皇でした。天皇は幽斎が討死すれば「古今伝授」の継承が断絶することを恐れました。幽斎はすでに八条宮智仁親王(天皇の弟)への伝授を開始しており、日本の歌道の将来がかかっていたのです。
幽斎は覚悟を決め、籠城の最中「古へも今もかはらぬ世の中に 心の種をのこす言の葉」という素養が滲み出る和歌を添えながら「古今集証明状」を八条宮に贈り、『源氏抄』と『二十一代和歌集』を朝廷に献上しました。これは自分の死後も、歌道の伝統が続くよう配慮した行動でした。
最終的に後陽成天皇は、幽斎の歌の弟子でもある大納言三条西実条らを勅使として派遣し、講和を命じました。天皇の勅命によって、幽斎たちは九月一三日に田辺城を明け渡しました。表面上は西軍の勝利に見えたこの戦いですが、実は東軍にとっての戦略的勝利でした。小野木重次らの丹波・但馬の西軍一万五〇〇〇人がこの攻城戦に釘付けになり、二日後の関ヶ原の本戦に間に合わなかったからです。
田辺城を開城するかなり前に、石田三成は真田昌幸に宛てた書状で次のように書いています。「丹後国へ軍勢を派遣し、その居城(田辺城)を攻め取り、細川幽斎が籠っている城に押し寄せ、二の丸まで攻め落としたところ、命だけは助けてほしいと朝廷へ取り次いで懇願してきましたので、一命だけは許し、丹後国を平定して事態は収まりました」(真田家文書)
当時のほかの史料の内容と比較すると、事実とは異なる不誠実な報告のようにみえます。西軍の諸将が三成のために積極的になれなかったことも頷けます。
* * *
戦国武士の死に対する覚悟と美学について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『戦国武家の死生観』をお読みください。
戦国武家の死生観
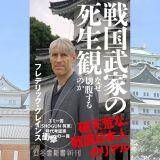
エミー賞「SHOGUN 将軍」
時代考証家・衝撃の一冊
戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。こうした戦国独特の価値観を古文書から読み解き、その知見をドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証に存分に活かした歴史学者が、戦国武士の生きざまを徹底検証。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。