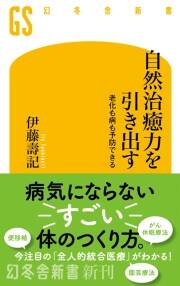がん、認知症、寝たきり…… 年齢を重ねれば仕方がないと思われがちな不調の数々。だが、私たちの体には、病や老化に抗う力が本来備わっている――。
現役外科医が、西洋医学だけでなく東洋医学や民間療法にも目を向け、自然治癒力を引き出す生活習慣を具体的に解説した新書『自然治癒力を引き出す 老化も病も予防できる』。本書から、一部を再編集してご紹介します。
* * *
腸が第2の脳と言われる理由
脳と腸が密接に関連することを「脳腸相関」あるいは「腸脳相関」と言います。以前から知られていたことではありますが、腸管と脳は相互にクロストークをしていて体の調整をしています。腸管には栄養や水分を吸収する上皮細胞、免疫を担う免疫細胞のほかに、ホルモンを分泌する内分泌細胞や情報伝達に関わる神経細胞が存在します。
お腹の調子が悪い人は心にも不調をきたす傾向が見られます。逆の見方をすれば、緊張をするとお腹をこわして下痢になったり、便秘を起こしたりします。整腸剤などの薬剤で便秘や下痢を治そうとしても改善しないということもあります。これは腸内の状態が脳の機能に影響を与えているからです。腸が第2の脳と言われる所以です。
近年の腸内細菌の解析技術の進歩により、この腸と脳の相関関係が明らかになりつつあります。腸内細菌が出す生理活性物質が、私たちの体の受容体と呼ばれる分子と結びついて、様々な細胞の機能を変えることができると考えられます。例えば、クロストリジウム菌より分泌される酪酸は抗うつ作用があることが知られています。
また脳と腸は情報交換しています。腸内細菌は、脳内で気分や感情を調整するのに重要な神経伝達物質の一つであるセロトニン(幸せホルモン)の代謝にも関わっていることが明らかになっています。
パーキンソン病はその代表的な例です。脳内のドーパミン不足によって引き起こされる神経変性疾患で、手足が震えたり、歩行が小刻みになったりする進行性の厳しい疾患ですが、これは、脳の神経細胞内に異常たんぱく質(リン酸化αシヌクレイン)が蓄積することで引き起こされます。
そしてドーパミンは腸管で作られ、迷走神経を介して脳に伝わるのではないかとも言われています。つまり、パーキンソン病は腸から発生する、ということです。事実、パーキンソン病の早期症状の一つに、便秘が起きることがあります。
腸内の環境が神経系の疾患に関与する例はほかにもあります。近年急速に進む腸内細菌研究で、色々なことがわかってきました。神経系(変性)疾患でいえば、パーキンソン病だけでなくアルツハイマー病や多発性硬化症。精神系では、うつ病や不安障害、統合失調症、双極性障害、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)、PTSD、強迫性障害(OCD)、摂食障害もそうです。
私の専門である消化器系でいえば、潰瘍性大腸炎やクローン病、過敏性腸症候群、機能性ディスペプシア、胃食道逆流症の一部なども腸内細菌との関連性が言われています。それから勿論、機能性の下痢や便秘も同様です。
腸内環境の整え方は後述しますが、「腸から健康になる」ということはとても重要です。お腹の調子さえ整えていれば大方、心身ともに健康でいられると言っても過言ではありません。ただストレスにも、化学物質や抗生物質にも過敏に反応する腸だからこそ、腸管の免疫機能や腸管バリア機能の低下は、老年期になればとりわけ起きやすく、加齢とともに腸をケアするということは大事になってくると思います。

腸を鍛えれば、認知症も予防できる
最近は、腸内環境を整える機能性表示食品が多く誕生し、特定のビフィズス菌には記憶力を維持する働きがあるんだ……、という認識が消費者にも受け入れられ、広がっていると感じます。
ヨーグルトは、各企業が異なる種類の乳酸菌で作っているために、味も風味も栄養価も、そしてその健康効果も違います。メーカーのほとんどが違う菌株を使っており、ビフィズス菌入りのものもあれば、そうでないものもあります。
ヨーグルトを食べて腸内環境を整えたいと思っている方は、まずは色々なメーカーのものを食べて体への変化を見て、自分に合ったものを選ぶのが良いと思います。数日食べ続けて体調を見るのです。
「腸から健康になろう」と考えるならば、金額は度外視して、同じものを試しつつ、菌株にだけこだわらずに、体調管理もしつつ、体の様子を見てみます。そのうちにきっとわかりますよ、私はこのメーカーのヨーグルトだと腸の調子が良い、というのが。そして、そういう日々を続けていきながら、認知機能の低下の予防をすることができたら、最高だと思います。それこそ、コスパの良い認知症対策です。
ただ、腸内環境が極度に乱れている時にそういう食品を試しても、なかなか効果は感じ難いと私は思います。悪玉の餌になるような肉類ばかりとって腸の中の菌のバランスが乱れていたら、まず発酵食品など善玉と言われる菌の餌になるようなものを食べるように心がけて、いったんスタートラインに立ってほしいと思います。
申し上げたいのは、せっかく自分に合ったヨーグルトをとっていても、腸内環境を乱すような日常生活をしていたら効果が出ないということです。

一日でも出ないなら下剤を使う
腸の調子を見るために、手っ取り早い方法が、便チェックです。そう、ウンチを見てください。
毎日出ていますか? するっと出ましたか? 形や大きさ、臭いはどうでしたか?
排便はとても大事な日常的な行為です。
排便が少なく、便秘あるいは宿便傾向が続くと、腸内環境が悪くなって、腸内の悪玉菌(いわゆる腸内環境を悪化させる菌。腐敗菌)が増えます。
腸の中に便がずっと滞っていると、良いことは一つもありません。本来は排出すべき便が腸内に滞在していることで有害物質が再吸収されやすくなり、悪玉菌が増えやすくなって腸内環境が悪化します。便秘が重症化すれば、腸閉塞を引き起こしたり、大腸憩室炎という大腸の壁での炎症を起こしたりすることもあります。

私は推奨します、一日1回排便をしましょう。便は速やかに排泄しましょう。
一日でも出ない時は、下剤を使ってもいいので、出してほしいのです。勿論一人ひとりに合った排便ペースもあると思うので、強制はしませんが、日常的に便秘傾向であるという方は、ご自身に合った下剤を見つけて、習慣的に飲んで便を排泄させるということを心がけてください。
まずは発酵の食品などを取り入れ食生活を整えた上で、トライ&エラーで合ったものを見つけることです。はじめは酸化マグネシウム等マイルドな下剤をベースに使用し、その上で必要に応じて別の機序の下剤、例えばセンナなどを上乗せしてコントロールすることをお勧めします。
その組み合わせは人により異なりますので、ベストのものを探し出して下さい。さらにまた、体を冷やさないことや運動習慣を身につけることも相乗効果を生みます。
ウンチはトライ&エラーです。毎日観察していると、だんだん自分に合った「ウンチ量&タイミング」が見えてきます。毎日、このタイミングでこれぐらい、というのがわかってきたら、なるべくそれをキープできるような排泄習慣を心がけるのです。
便の形状を見る「ブリストル便形状スケール」という共通の基準があります。タイプ1の「コロコロ便」から、タイプ7の「水様便」まで7段階あり、タイプ3「ややかたい便」タイプ4の「普通便」タイプ5「やややわらかい便」あたりが理想的なウンチと言われています。バナナのような形の便がするっと出るのが良いと言われています。
量も健康な人で一回100~200g、一日に1~2回程度が正常と一般的には言われていますが、特に回数はこだわらなくてもいいと思います。ただ最低でも一日1回は出すべきだと私は思っています。
よく女性の中には「毎日出ないけれど、困っていないからいいの」と仰る方がいらっしゃるのですが、それは違いますよ、と伝えています。体に悪いものが溜まったその終末が「大腸がん」です。女性に大腸がんが多いのは、そういうことです。男性では健診などで貧血がある場合、大腸がん検診での便潜血が陽性であれば、必ず内視鏡を入れて大腸をチェックしてください。大腸がんが隠れている場合がありますので。
便意を感じたらすぐトイレへ。便意は15分でなくなります。便の排出には、前かがみになるといいです。直腸と肛門(V120度)の角度が鈍角となって、便の排出がしやすくなるからです。足はつま先が膝の下にくるように引いて床につけ、かかとを少し上げます。ひじを膝の上に置き、深く考え込んでいるような「考える人」のポーズです。
先に「出ないならば下剤を」と書きましたが、下痢するほどの下剤は問題です。自分に合った下剤を適切量とりましょう。高齢者が日常的に飲まれる酸化マグネシウム錠は、体内に自然に存在する成分が入っていますから、あまり大きな副作用はないと思います。
ただし、腎機能障害のある方では、高マグネシウム血症のリスクがあるので、漫然と長期間服用することは避けるべきです。
実は悪玉菌も必要。腸内細菌の整え方
ここで改めて、腸内細菌の話をしましょう。
我々の腸内には約100兆個、1000種類以上の細菌が生息していて、細菌叢を形成しています。様々な細菌が1つの種類ごとの塊で存在しているその形態がお花畑(フローラ)のように見えることから“腸内フローラ”という名前がついています。
腸の構造は非常にすぐれていて、健康でいられるのも腸内細菌のおかげと言っても過言ではありません。
腸内にある細菌数も種類も、腸の部位によって異なります。細菌数が最も多いのが大腸で、ビフィズス菌やバクテロイデスなど酸素を嫌う嫌気性菌が大半です。小腸は酸素が比較的多いので、酸素に耐えうる細菌が多くいます。ラクトバチルス、エンテロコッカスなどです。
また、一人ひとりの腸内の細菌のパターン(組み合わせ)も、その数も異なります。食事の内容や生活環境の改善で、腸内環境が良くなるというのはおそらく多くの人が知るところですが、ではその形成はいつどのようにできたのか、ご存じでしょうか。なお、生まれる前の赤ん坊の腸内は無菌状態です。
実は生まれた時に、母体から引き継いでいるのです。産道を通って正常分娩で生まれた子どもは、母親の持つ腸内の細菌をそこで(出産時に)もらいます。ですので、帝王切開で生まれた子どもは、もらい受けません。腸内細菌はこのように母親由来+α、3歳までに確立すると言われています。お母さんのお腹の環境がとても良かったら、ぜひとも正常分娩で出産し、その腸内細菌をお子さんに引き継いでいただきたい。良い環境も悪い環境もそのままお子さんに引き継がれます。しかし後述しますが「便移植」などで、腸内環境は全面的にリセットすることもできます。

腸内環境は常に変化していて、日頃の生活習慣が左右します。まず、老化や薬物(抗生物質、抗がん剤)、食事、疾病(感染性腸炎)、ストレスなどの要因で変化します。食事では、肉に偏った高たんぱく・高脂肪食で悪玉菌が増えます。
ストレスがたまると交感神経優位となって腸管の血流が減少してしまい、消化機能が低下します。その結果、腸内フローラのバランスが崩れ、悪玉菌が優勢となり、便秘や下痢を引き起こしやすくなります。
腸内フローラを形成している菌ですが、いわゆる善玉菌と悪玉菌に加えて、日和見菌があります。日和見菌は普段は何事もなく腸内で共存していますが、免疫力が低下すると、「悪さ」を始める悪玉菌と化してしまいます。これが過剰に増殖すれば、感染症を引き起こすこともあります。
善玉菌は、乳酸菌やビフィズス菌など。悪玉菌は、大腸菌やウェルシュ菌、ブドウ球菌など。日和見菌はバクテロイデスや大腸菌連鎖球菌などです。一般的には腸内フローラの菌の割合は、善玉菌2~3割、悪玉菌1割、日和見菌6~7割ぐらいが理想だとされています。
「いやいや、悪いのは要らぬ。善玉菌だけでいい」と考えがちですが、悪玉菌も一定程度必要です。その理由は、悪玉菌が作る特定の物質が善玉菌の栄養源となるからです。善玉菌が増殖していくためには、ある程度必要なのです。しかも悪玉菌は、免疫システムの働きを強化するという役割もあります。「悪いヤツが適度にいるからこそ、バランスがいい」というのは、意外とありがちな話だと思いませんか? 何事もバランスです。腸は社会の縮図のようですね。
腸は休むことなく働いていて、健康維持に大いに役立っています。
善玉菌がどう働いているのか、ごく簡単に説明すると……。
善玉菌は、(1)乳酸や酢酸や酪酸などの「有機酸(短鎖脂肪酸)」を生成して腸管内を酸性にします。それにより(2)腸の動き(蠕動)が改善されます(整腸作用)。「有機酸」は(3)特定の細菌や病原菌の増殖を抑える効果があり、この有機酸があることで(4)腸内のpHバランスが保たれます。(5)便通もスムーズになり、(6)腸の炎症も抑えられます。
また、善玉菌は腸管内で胆汁酸やコレステロールを吸着して便として排出することで、(7)血中のコレステロールが低下します。(8)さらに、アレルギーを抑制するTh1細胞(細胞性免疫を助ける)を増やして、アレルギー反応を抑えます。どうですか? いいこと尽くしでしょう。
できる限り腸内の善玉菌割合を、理想値に近づけたいものです。
* * *
老いに負けず、最期まで自立して生きる方法について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『自然治癒力を引き出す 老化も病も予防できる』をお読みください。
自然治癒力を引き出す
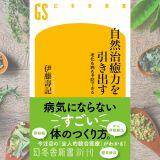
がん、認知症、寝たきりは予防できる――。その鍵は、人間に本来備わる自然治癒力を引き出し、老化や病を遠ざける“統合医療”にある。年のせいと諦めていた不調であっても、改善が期待できる新しい医療のかたちだ。その可能性を追究し続け、東洋医学や民間療法までも実践と検証を重ねてきた外科医が、健康寿命を延ばす日常ケアを具体的に解説。たとえば、頭も体も使う園芸療法、誤嚥を防ぐ咀嚼トレーニング、心を整える瞑想法など、毎日の習慣に取り入れやすいものばかりだ。最期まで自分の足で歩き、自宅で充実した日々を過ごしたい人、必読の一冊。