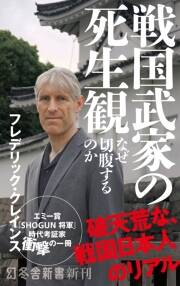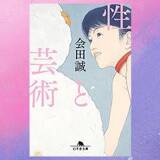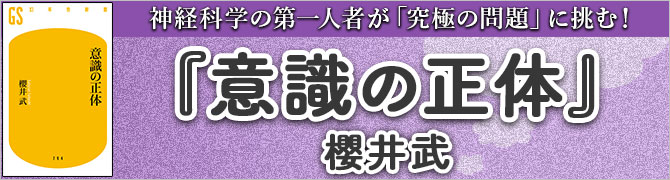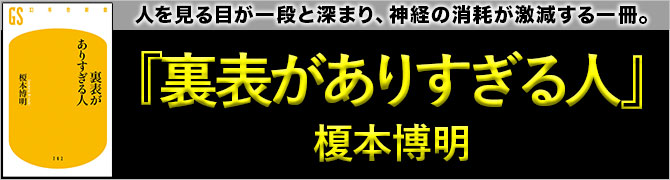ハリウッドにて制作が決定している『SHOGUN 将軍』シーズン2。新キャストとして、Snow Man・目黒蓮さん、水川あさみさん、
シーズン1にひきつづき、
* * *
戦国時代の切腹の多面的な性格
下野(栃木県)の有力な国衆の佐野氏について書かれた軍記物『唐沢城老談記』から、佐野宗綱の家臣の切腹について書かれた一節を紹介しましょう。
大抜越中守は、元旦の出陣に供をしなかったことがある。たしかに越中守は諫言をしたが、主君である宗綱は立腹して彼を用いなくなった。出陣は避けられない状況だったが、越中守の主張にも一理あった。しかし、彼の本心は計りかねるところがあり、本城の留守居も任されなかった。
宗綱は何も意見を述べずに出陣してしまったが、越中守が後に残ったことは本意ではなかった。留守城番はつねに緊急時のために命じられるものだから、通常の家臣たちはそれでよいのだが、越中守のような重臣が残る場合は違う。たとえ本心から残ったとしても、大抜家の者である以上は是非なく、必ず裏切るだろうと考えられた。
そこで、富士源太、竹沢山城、山越才吉、津布久弾正、細野次郎左衛門を始めとする三十余人の侍大将と、数百騎の軍勢が大抜越中守の居城に押し寄せた。越中守は佐野四天王の一人で、一騎当千の武将だったが、しだいに家老たちとの不和が深まり、宗綱の討死の後、間もなく、〔敵軍と〕戦うこともなく切腹したのだった。
この場合の切腹は、直接的な失態というよりも、主君との不和、家老との対立など、複合的な要因が積み重なっての結末です。越中守は戦う力があるにもかかわらず、武士としての最後の意思表示として切腹を選択したのです。
戦わずに自害することを選ぶ背景には、感情が武士の行動に大きな影響を与えていました。越中守の行動は、江戸時代の儒教的な武士像からかけ離れています。それは、戦国時代において、主君と武士は形而上的な倫理観で結ばれていたのではなく、感情的な絆で結ばれていたからです。
この事例は、先の山上藤七郎の事例よりも複雑な切腹の様相を示しています。主君の信頼を損なったことに対する責任からというよりも、複雑な状況に陥った越中守が感情的に切腹にいたった様子が描かれています。感情的な切腹は戦国時代の史料によく見られます。戦国時代における切腹の多面的な性格を理解するうえで、把握しておくべきでしょう。

自己実現のために自害する武士の姿
戦国時代の切腹が名誉回復の方法であったことは前述したとおりですが、さまざまな史料を読むと、むしろ積極的に称賛される行為ととらえられていたことがわかります。
たとえば、「信長公記」巻一四には越中願海寺城主の寺崎盛永と、その息子・喜六郎に関する次のような記述があります。寺崎父子は何かの事件について尋問され、その後、佐和山城で監禁されていました。
七月一七日、佐和山において、痛ましい出来事があった。
越中の寺崎盛永とその子息の喜六郎が、(信長により)生害を命じられた。息子の喜六郎はまだ一七歳という若さで、眉目秀麗、姿形も類まれな美しさをもつ若者だった。
まず、父の寺崎盛永が本来の作法として、腹を切り、若党(従者)が介錯を務めた。その後、喜六郎は父の腹から流れ出る血を手に受け、それを嘗めながら「私もお供いたします」と言って、凜として腹を切った。これは比類なき働きであり、まことに目を覆いたくなるような出来事だった。
江戸時代には刑罰の一種となる切腹が、戦国時代には称賛される行為であったという価値観の逆転現象は、なぜ起こったのでしょうか。主君の命令に従って切腹をしたこの例においてもなお、切腹を刑罰としてではなく、武士の規範としてとらえて、分析し直してみましょう。
「信長公記」の記述からは、切腹の本質的な要素として、次のような特徴を読み取ることができます。
寺崎盛永と喜六郎の切腹は、たしかに命令を受けたことがきっかけではありましたが、その後の対処の仕方に重点が置かれています。武士としてゆるぎない覚悟のうえでの死に様を伝えているのです。
また、「比類なき働き」という評価は、彼らの行為が武士としての称賛すべき生き方を体現したものとして認識されていることを示しています。
さらに、父の血を嘗めるという喜六郎の行為は、親子の絆と武士の誠の表現として描かれています。面白いことに、この描写では、定着してきた江戸時代の重々しい儀式的な切腹のイメージと違って、当事者の感情的な側面に重点が置かれ、かなり荒々しく、また生々しく切腹の場面が表現されています。
切腹は命じられたものであっても、それを実行する態度において、武士としての自己を完成させる機会としてとらえられていました。とくに、若年の喜六郎の凜とした態度は、武士としての称賛すべき生き方の達成として高く評価されているのです。
このように、切腹を武士の規範として見ると、それは武士がみずからの死に様を実現する手段として機能していたことがわかります。命令や刑罰、儒教的な倫理などという外的要因ではなく、武士としての内面的な価値観の表現として切腹が位置づけられていたと解釈できます。
秀吉が書き留めた柴田勝家の最期
戦国時代の女性の自害の例として、お市の方の逸話も紹介しましょう。
織田信長の妹とされるお市の方は、当初、近江の浅井長政に嫁ぎますが、兄の信長によって浅井家が滅ぼされると、織田家に引き取られ、やがて信長の死後に柴田勝家に再嫁します。
しかし、賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れた勝家は、天正一一(一五八三)年四月、居城の越前北ノ庄城で自害に追い込まれます。その際、お市の方も勝家とともに自刃しました。
当時の様子を記した秀吉の書状が残されています。同年五月一五日付、小早川隆景宛ての書状から、まずは夫である勝家の最期を現代語訳で見てみましょう。
城内に石の蔵を高く築き、天守を九重にまでつくり上げたところへ、柴田の軍勢二〇〇人ほどが籠城していた。城内に閉じこもっているので、こちらの総勢をもって城に攻め入れば、互いに応戦し、負傷者や死者が出ることは避けられない。そこで、総勢のなかから精鋭を選び出し、天守をめざして攻撃した。
天守ゆえ、矢や鉄砲を使って攻め入ったが、北ノ庄城の柴田勝家は、日ごろから武芸を積んだ武士だったので、七度も切り返して出てきた。しかし、とうとう防ぎきれず、天守の九重の最上階に上がった。
そこで、勝家が総勢に呼びかけて、「自分が腹を切る様子を見て、後学のためにしなさい」と言った。その言葉を聞いた心ある侍たちは、涙をこらえ、鎧の袖で顔を覆った。すると、その場にいた者たちは皆、東西の隅々まで、しんと静まり返った。
その後、勝家は妻子や一族をみずから刺し殺し、身寄りのいない者八〇名は切腹し、申の刻(午後四時ごろ)に果てたとのことである。
死は、名誉ある人生を完結させる「晴れ舞台」
この書状に記されている柴田勝家の最期の場面には、戦国武家が高く評価していた死の形が表れています。勝家は「自分が腹を切る様子を見て、後学のためにしなさい」と家臣たちに呼びかけます。これは単なる自害ではなく、後世に語り継がれるべき「模範的な死」として演出されています。武将たちにとって、最期のときはみずからの生き様を集大成として示す「晴れ舞台」だったのです。
さらに、勝家だけでなく、妻子や親類、家臣たち八〇余名がともに死を選んでいます。これは主君との絆を最後まで貫く武士の生き方を示すとともに、一族の名誉を守るための選択でもありました。
こうした死生観の根底には、名誉と評判を何より重んじる武家社会の価値観があります。「どう死ぬか」は「どう生きたか」と同等か、それ以上に重要視され、その最期の有様は伝説として後世に伝えられ、家名の誉れとなったのです。秀吉がこの書状で勝家の最期を詳細に記録したことも、敵将とはいえ、その死に様を価値あるものとして認めていたことを示しています。
勝家が後世に名を残すことを望んでいたとすれば、その願いはみごとに成功を収めました。その名声は現代にまで伝わるだけでなく、当時においてはイエズス会士までもがその壮絶な最期を詳細に記録し、遠く西洋の地においても名を知られるほどの人物となりました。

* * *
戦国武士の死に対する覚悟と美学について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『戦国武家の死生観』をお読みください。
戦国武家の死生観
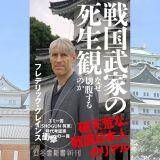
エミー賞「SHOGUN 将軍」
時代考証家・衝撃の一冊
戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。こうした戦国独特の価値観を古文書から読み解き、その知見をドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証に存分に活かした歴史学者が、戦国武士の生きざまを徹底検証。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。