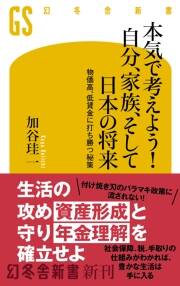手取りは増えない、年金ほか社会保障は不安、物価だけが上がっていく――付け焼刃で連発される政策に騙されず、この苦境を乗り切るにはどうすればいいのか。経済評論家・加谷珪一さんの最新刊『本気で考えよう! 自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』から「はじめに」をお届けします。

「今さえよければいい」という危ない感覚
とどまるところを知らない物価上昇、自民党の少数与党転落と国政の混乱、兵庫県知事選をめぐるドタバタ劇、メディア報道に対する強烈な不信感など、このところ、従来の常識では説明できない出来事が次々と起こっています。
これらは別々の事象かもしれませんが、日本社会を形作ってきた秩序や規範が崩壊し、社会の底が抜けてしまったような印象を持っている人も少なくないと思います。将来に対する不安感が増大し、多くの人が得体の知れないイライラを感じながら、日々の生活をこなしているのではないでしょうか。
私は、いよいよ日本社会にも本格的なポピュリズムの流れが到来したと考えています。
しかしここで言うポピュリズムというのは、巷で(ちまた)イメージされているようなものではありません。それは私たちの心の中に生まれつつあるポピュリズム、つまり内なるポピュリズムと言ってよいものだと思います。
政治や経済、ビジネスの現場では、これまでと同じような毎日が繰り広げられているように見えます。しかしながら、私たちの心の中をポピュリズムが徐々に侵食しており、ちょっとした判断においても「後で考えればいい」「今さえよければいい」「面倒くさいことは嫌だ」といった感覚が強まり、徐々に合理的な考え方ができなくなっています。
こうして面倒な判断を少しずつ回避していった結果、私たちの暮らしは坂道を転げ落ちるように悪くなっています。この状況からどのようにして脱却し、個人として充実した人生を送ることができるのか、ひいては国全体を適切に運営できるのかというのが本書における最大のテーマです。
生活に滲み出る貧しさの正体
日本経済は長くデフレ(物価の下落)が続いてきましたが、とうとう物価が継続的に上昇するインフレのフェーズに入りました。ひとたび始まったインフレを抑えるのは容易なことではなく、インフレ経済下では、継続的な成長と賃金上昇を実現できない限り、国民生活は果てしなく窮乏していきます。すでにその兆候はあちこちに表れているといえるでしょう。
2024年秋に行われた総選挙では自民党が少数与党に転落し、キャスティング・ボートを握った国民民主党は大規模な減税を政府に要請しました。減税を喜ばない国民はいませんが、その分だけ歳出を減らさない限り、減税の実施には財源が必要となります。財源を確保せずに国債に頼れば、経済学の理屈上、インフレがさらに激しくなり、手取りが増えた分はすべて吹き飛んでしまいます。
この話はほとんどの人が理解しているはずですが、それでも目先の手取りを増やして欲しいと国民が強く要求しているのは、今の生活があまりにも厳しいという、ある意味で魂の叫びと言ってよいでしょう。
政治がこうした声に真摯に向き合う必要があるのは当然のことですが、一方で、無い袖は振れないというのも事実です。財源を国債に頼れば、今後、インフレ税という、これまで経験したことのない大増税に見舞われることになります。つまり国債の追加発行は何の問題解決にもならないばかりか、近い将来、状態をさらに悪化させる可能性が高いのです。
今、発生しているインフレや財政問題は、半分は避けられなかった面がありますが、半分は私たち国民が選択した結果としてもたらされている現象です。多くの人は、日銀の大規模緩和策を過度に続ければマネーの量が増えすぎ、物価がさらに上がって生活が苦しくなることについて、ある程度は認識していたと思います。しかしながら、大規模緩和策から撤退して金融を正常化するには金利を上げなければならず、それに伴う弊害は大きなものとならざるを得ません。ズルズルと決断ができない状況を続けてきたのは、まさに「分かっているけれどやめられない」という話の典型といえるでしょう。
なぜ「手取りを増やす」議論に魅了されてしまうのか
2024年末に社会を大きく賑わせた「年収の壁」問題にも同じメカニズムが作用していると思います。私は国民民主党が提案していた基礎控除の引き上げそのものには賛成の立場でしたし、この問題についてはテレビ番組などを通じて何度も政策の中身やメリットおよびデメリットについて解説してきました。
こうした中、私が感じた最大の問題点は、国民民主党が提案したプランというのは、学生の働き控えを解消するという話と、大規模な減税策を実施するという話がセットになったものだという点です。政策というのは、必ずしもひとつの目的のみを達成するためのものである必要はなく、複数の目的を持っていること自体は何の問題もありません。しかしながら、複数の目的が混在している政策を実施する場合には、それぞれの目的について、他の案との比較検討を十分に行う必要があります。
私は、問題の切り分けと、それぞれにどのようなプランがあり得るかを比較検討した上で議論を進めた方がよいという話を繰り返し主張してきました。減税を行うのであれば、ガソリン税を大幅に引き下げる、減税と給付を組み合わせる給付付き税額控除を導入するなどの政策を実施した方が圧倒的に効果が高く、国民も減税を実感しやすいはずです。しかしながら、金額をいくらに設定するのかという議論にばかり焦点が当たり、政策の中身についてきちんとした比較検討はできませんでした。
加えて言うと、金額についてもエイヤ! で決めてしまってよいものではありません。
その理由は、財源が足りないという問題もあるのですが、最大の理由は基礎控除を一気に引き上げてしまうと、物価上昇率など経済情勢との整合性、あるいは生活保護、最低賃金、年金、各種控除など、他の政策との整合性が取れなくなり、後で必ずやっかいな問題を引き起こすからです。
こうした説明をすると、多くの人から、「そんな面倒くさいことをなぜネチネチと議論するのだ」「とにかく手取りを増やせというのが国民の声なんだ!」と激しく批判されます。また年収の壁がいくつも存在し、制度が複雑であることから、「なぜ次から次へと政府は複雑な制度を作るのか?」という怒りの声もよく聞きます。
しかしながら、現代社会というのは価値観やライフスタイルが多様化しており、多くの国民にとって公平な制度を構築するには、どうしても制度が複雑になってしまいます。イライラする気持ちはよく分かるのですが、ここで短気を起こしてしまい、「面倒な議論などやめてしまえ」と言ってしまったら、別のやっかいな問題が次々と発生し、結局は私たちの首を絞める結果となるのです。
繰り返される年金破綻論と現実との離乖(かいり)
様々なテーマについて冷静な議論ができなくなっている背景には、年金や医療など、社会保障制度に対する国民の不信感があると考えられます。若い世代の中には、将来、どうせ年金はもらえないのだから、保険料など払っても意味がないと主張する人もいます。
しかしながら、「公的年金は破綻するので、払っても意味がない」という議論は今に始まったことではありません。私が社会人になったのは今から約30年前のことですが、当時から公的年金は破綻すると噂されており、多くの若者が「年金に入っても意味がない」と声高に主張していました。当時、年金など要らないと叫んでいた若者の多くは今、高齢者となっていますが、公的年金は彼らの命綱として現在も機能しています。
現時点でも支払った保険料に対して2・5倍の年金がもらえる仕組みになっており、民間に存在するどの商品よりも圧倒的に安全で有利です。しかも、今後の試算においても、制度が破綻する可能性はゼロに近く、今、20代の人であれば、人口構成の変化によって、むしろもらえる年金額が増える可能性すらあります。
昔も今も公的年金は人生における最後の砦であり、老後の生活を支える大黒柱であることに変わりはありません。下手に制度を貶めることは、結果的に私たちの生活水準を下げてしまうでしょう。
医療についても同じことがいえます。
日本の公的医療制度は、保険料の滞納さえなければ、貧富の差を問わず、誰でも最先端の医療を自由に受けることができます。近年の日本は経済や社会の衰退が激しく、諸外国に胸を張って自慢できるものが少なくなっています。こうした中、公的医療制度だけは、唯一、多くの外国人がうらやむ制度ではないでしょうか。
健康な人にはイメージしにくいかもしれませんが、病気になった時、自由に病院にかかれるというのは、本当に大事なことです。年金と同様、医療制度に多くの問題があるのは事実であり、改善の余地もたくさんありますが、誰もが病院にかかれるこの制度だけは絶対になくしてはならないと思っています。制度の枠組みはしっかりと残しつつ、私たちの保険料負担をいかに軽減できるのか、真剣に議論していく必要があるでしょう。
資産形成はいつ始めても遅くない
公的年金が破綻する可能性はほぼゼロとはいえ、高齢化がさらに進むのは確実であり、 40代、50代の人たちが将来受け取る年金額は減少が予想されます。こうした経済的・社会的環境においては、公的年金だけを老後の収入源として頼ることにはリスクが伴います。体が元気なうちは可能な限り働いて収入を得ると同時に、積極的に資産形成を行い、それを老後の生活の足しにしていく工夫が必要となるでしょう。
老後を迎えた当初は、現役時代と同様、勤労収入を中心とした生活を行い、体力の低下に合わせて勤労収入の割合を減らし、投資収益や年金を収入源にしていくという流れについて、今のうちから考えておく必要があります。
その意味で、資産形成がうまくいくかどうかは、老後の生活に極めて大きな影響を与えることになります。本書では個人の資産形成についても言及しますが、長期の資産形成を成功させるには、毎年、一定額の投資を長年にわたって継続することが大事です。筆者は約30年間、その作業を続け、自分でも驚くほどの資産を構築することができました。しかしながら、ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。
詳しくは第8章で解説しますが、投資を行うには、たとえ小さな額であっても軍資金が必要であり、貯金をせずに(つまり原資なしに)投資をすることは不可能です。厳しい現実ですが、この現実を受け入れ、涙ぐましい努力を重ねて何とか資金を捻出したのです。私の中で内なるポピュリズムが勝って、「いざとなったら一気に挽回できる方法がある」と考えてしまっていたら、私の資産形成は大失敗していたことでしょう。
こうした地道な考え方に至ることができたのは、多くの成功者と接し、その思考回路をじかに学ぶことができたからだと思っています。
私はサラリーマン時代、金融機関に勤務していたことがあり、数多くの成功者・富裕層と接してきました。彼らの行動パターンや言動をつぶさに観察すると、ある共通項が存在することが分かりました。私は凡人なので彼らの10分の1以下かもしれませんが、少しでも真似できれば、経済的なメリットを享受できるのではないかと考えたわけですが、実際にやってみたところ、効果は想像以上に絶大でした。
成功者に共通する思考パターン・行動パターンというのは、まさに今説明してきた内なるポピュリズムの克服であり、「いいとこ取りはない」という現実をしっかり受け止めた結果として得られるものです。繰り返しになりますが、私たち自身は凡人ですから、彼ら成功者のようには振る舞えません。しかし、彼らの10分の1でも身につけることができれば、庶民としては十分すぎるほどの成果を得られるのです。
不安の時代を生き抜く術(すべ)とは
本書では、なぜインフレが止まらないのか、なぜ賃金が上がらず私たちの生活が苦しいのか、といった基本的な経済の仕組みを解き明かしつつ、多くの人が不安視している年金制度について、できるだけ分かりやすく解説し、実は過度な不安や不満は持つ必要がないという現実を明らかにしていきます。加えて、大規模減税に頼らなくても、手取りを増やす方法や、税収を増やす方法は存在するという事実を丁寧に説明していきます。そして、肝心の賃金についても、まだ賃上げする余地があることを知って欲しいと思います。
一方で、日本の人口は今後、減少が確実視されており、かつてのような成長を実現できないのも事実です。こうした中、個人としてお金をどう増やしていけばよいのか解説していきます。
日本は民主国家ですから、独裁的な支配者がいて、民は一方的に支配されるという仕組みではありません。日本という国の主権者は我々国民であり、この国の運営をどうするのか、今後、どうしていくのかは、私たちが責任を持って決めなければなりません。
国家ではなく国民生活を基軸とする新しい時代において、年金や医療は、私たちの生活を支える基本インフラですから、絶対に政争の具にしてはならないと思います。国民も社会保障制度についてもっと理解を深め、この仕組みを維持できるよう、主体的に議論していく必要があるでしょう。
もっとも、私が本書で解説するやり方は、粘り強く、腰を据えて取り組まなければ実現できないものばかりであり、決して簡単な道のりではありません。本当に面倒で辛いことですが、日本人にはこうした壁を乗り越える底力があるはずです。地道な努力を積み重ねて制度をよりよいものに変え、個人としても生きる力を身につけることができれば、人口が減って技術開発が停滞する日本においても、豊かな生活を維持することができるでしょう。
日本の経済・社会システムが限界に近づきつつあるのは事実であり、これからの10年は、最悪の事態を回避する最後のチャンスだと私は考えます。今、決断し、動かなければ、私たちの未来は暗いものとならざるを得ません。その意味で、本書は日本社会に対する希望であると同時に最後の警鐘でもあります。
本気で考えよう!自分、家族、そして日本の将来の記事をもっと読む
本気で考えよう!自分、家族、そして日本の将来
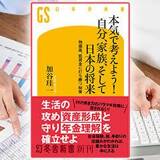
賃金停滞と米などの物価高騰の二重苦に晒される私たちの生活。財源なき減税論が政争の具とされ、国民も「今さえよければ」という一種の思考停止状態に陥っている。日本経済はなぜツケを後回しにし続ける袋小路から抜け出せないのか? 年金や税、賃金の制度を変えることは簡単ではない。しかし、その仕組みを正しく理解することで、減税に頼らず手取りを増やす糸口は見出せる。その時は今しかない。データに基づいた分析に加え、著者自身の経験則から導いた資産形成方法も明らかにした、国が、個人が生き残るための緊急提言。
- バックナンバー