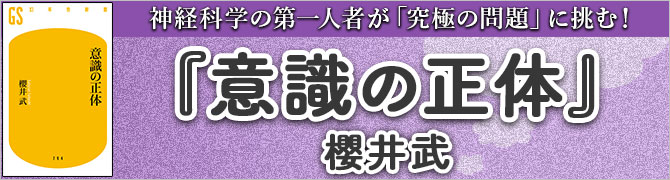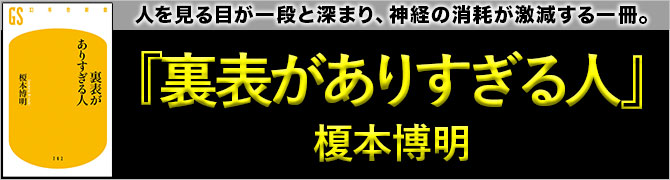前回の記事では、田才さんが国連を退職し、株式会社坂ノ途中のコーヒー事業部「海ノ向こうコーヒー」で働くことになった経緯をご紹介しました。
NGO職員や国際公務員としてのキャリアを積んできた田才さんにとって、民間企業への転職は大きな方向転換だったそうです。
今回は、「そもそもなぜコーヒーの仕事を選んだのか?」というテーマで綴っていただきます。
* * *
大学入学のために地元・新潟を離れ、横浜に住むことになった。初めての一人暮らし。生活費も稼がないといけないので、アルバイトを探していたところ、横浜駅西口にカフェを見つけた。
ガラス張りの扉を開けると、コーヒーの香ばしい匂いが鼻をかすめ、大きな機械が堂々と鎮座する姿が目に飛び込んできた。エスプレッソマシンというやつだろうか。静謐で、でも冷たすぎない灰色のコンクリートの床と、ウッド調のカウンターの木のぬくもりが、絶妙な塩梅でマッチしている。静かな空間に時おり控えめに響く、「シューッ」「キュル、キュルキュルッ」という音を聴きながら、アルバイトの面接をしてくれる店長が現れるのを待っていた。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
幻のコーヒー豆を探して海ノ向こうへ
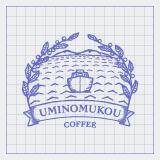
──元・国連職員、コーヒーハンターになる。
国連でキャリアを築いてきた田才諒哉さんが選んだ、まさかの“転職先”は……コーヒーの世界!?
人生のドリップをぐいっと切り替え、発展途上国の生産者たちとともに、“幻のコーヒー豆”を求めて世界を巡ります。
知ってるようで知らない、コーヒーの裏側。
そして、その奥にある人と土地の物語。国際協力の現実。
新連載『幻のコーヒー豆を探して海ノ向こうへ』、いざ出発です。