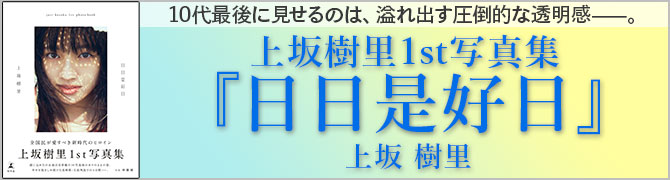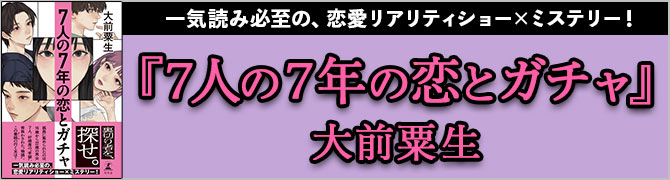「ロボットは『負の感情』を極めよ」
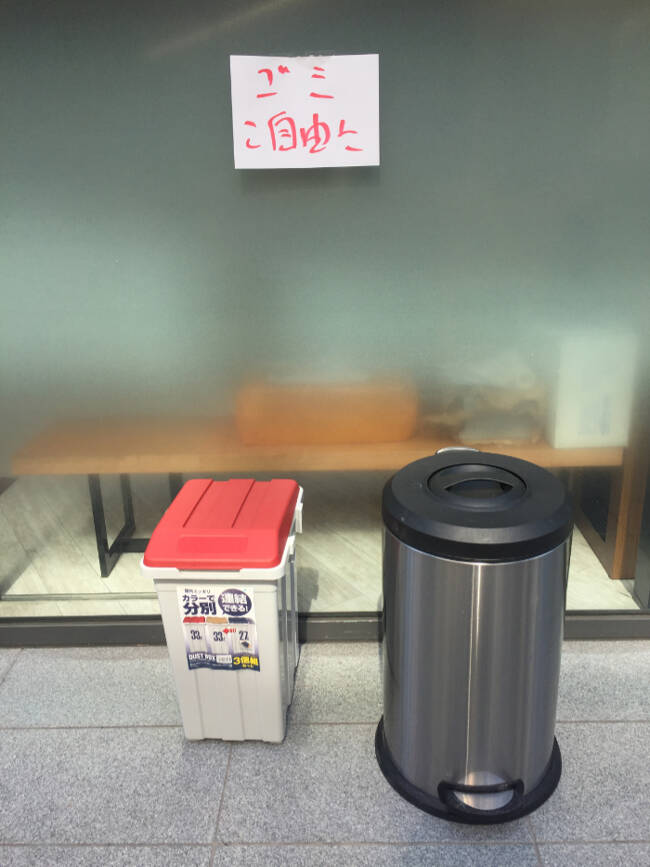
今年4月、北京で世界初の人型ロボットによるハーフマラソンが行われたらしい。1位でゴールしたロボットは2時間40分42秒で、これは初心者が走った場合の平均タイムとほぼ同じだという。
1月には、横浜市に住む96歳の奥山新太郎さんが、国内史上最高齢でフルマラソンを完走したが、こうした感動話もいずれロボットに取って代わられてしまうのだろうか。奥山さんのタイムは8時間43分46秒で、今後さらにタイムを短くしたいと抱負を語っていたが、「おじいちゃん、あとはロボットがやるから大丈夫よ」と言われてしまうのかもしれない。
こうした事態に、私は強い危機感を覚えた。
アメリカや中国では昨今、人工知能を搭載したロボットが飛躍的な進化を遂げているという。人間には、どうも人に似せた存在をつくりたくてたまらないという欲求があるようだ。それは、本能と言ってもいい。しかし、なぜよりによって、小説を書く、絵を描く、映像・音楽を作る、など楽しいところばっかり奪っていこうとするのか。
世間では、長らく「AIに奪われる仕事ランキング」が話題を呼んでいるが、このままいくと、仕事どころか趣味や気晴らし、生き甲斐までが奪われてしまいそうだ。
開発者たちは、何か大きく方向性を間違ってはいないか、今一度考えてもらいたいものである。
そもそも、人間の最大の魅力は欠点のはずだ。一生懸命なのに不器用だったり、ちょっと抜けていたり、長所と同じくらい短所があるから愛される。逆に完璧な人間ほど、人をイラつかせるものはない。何でもできる万能な存在など、誰も求めていないのだ。
「俺は、ロボットみたいな人間にはならねえ」という言葉が示すように、ロボットのような人間は嫌われるのである。
開発者たちは、人間界で嫌われる存在をせっせとつくってどうするつもりなのか。
1942年、SF作家のアイザック・アシモフは、ロボットと人が安全に暮らすための行動規範として、「ロボット工学三原則」を提唱した。
1、ロボットは人間に危害を加えてはならない。
2、人間の命令には従わなければならない。ただし、1に反しない限り。
3、ロボットは自分自身を守らなければならない。ただし、1と2に反しない限り。
この三原則のもと、人間の安全を最優先に設計された、品行方正なロボット像が描かれるようになった。特に「怒り」のような衝動は、ロボットから排除されたのである。
だが、21世紀も四半世紀が経った。そろそろ、このタブーをブチ破ってもいいのではないか。
人間そっくりな存在をつくるなら、やはり主たるテーマは「負の感情」だろう。ドロドロした醜い感情を持つからこそ、人は夢を抱き、成長しようともがく。負の感情こそ、人間を人間たらしめるものなのだ。
たとえば、劣等感。
今年3月、千葉県東金市で19歳の女が強盗目的でコンビニに押し入り、店員に包丁を突きつけ「金だすか、通報してくれませんか」と脅して逮捕された。彼女は学歴が低く、人と関わることが苦手だったようで、「劣等感がやばくてやっちゃいました」と供述しているという。
これぞ人間。人に包丁を突きつけるのはよくないが、愛嬌たっぷりの犯行動機ではないか。「〇〇ちゃんは、そういうとこ可愛いよね」と、誰か言ってあげなかったのだろうか。
この劣等感をロボットに搭載できたら、それこそ人間に近づく一歩だろう。
負の感情は、人と比較することで生まれる。もしも無人島にたった一人なら、劣等感すら生まれないはずだ。
以前、私の著書がノンフィクションの賞にノミネートされたとき、ある人物からこう忠告された。
「インベさん、これから妬み嫉み僻みがすごいことになるよ」
それを聞いて、私は胸がいっぱいになった。
私の半生は、まさにその逆。ずっとずっと、「妬み嫉み僻み」を他人に向ける側だったからだ。荒れ狂う感情を、何度ノートに殴り書きしたことか。あっち側の気持ちなら、私の中にも深く染みついている。その「妬み嫉み僻み」が、ついに自分に向けられるのだ。これほど本質を突いた賞賛はない。
さあ、来い! 来い! 来い! と待ち構えていたが、いざ蓋を開けると、ノミネートごときでは誰も私のことを羨ましいとは思わなかったらしい。とんだ、取らぬ狸の皮算用だ。
せめて、ロボットでもいいから「妬み嫉み僻み」をぶつけてくれないものか。
誰かと比べては自分を否定し、悶々と悩み続けるのも人間の特徴だ。悩みのかたちは千差万別。ときに人は「え? そんなことで?」と思うような、理解不能なことで悩んでいたりする。
ここで一つ、私がこれまで出会ったなかで、もっともインパクトのあった「悩み」を紹介しよう。
それは、ある年、私の写真展にフラリと現れた若い男性の悩みである。
彼は、私が出したエッセイ集『私の顔は誰も知らない』を読み、己の半生を振り返ったらしい。ギャラリーの椅子に座ると、彼はこう語った。
「インベさんは、本の中で『女性は実体験をもとに自分の考えを語るからおもしろい。男性は社会的なくくりで自分を語ろうとするからつまらない』みたいなことを書いていたじゃないですか。自分がまさにそのタイプなんです」
まるで懺悔するように言い、「男はかっこつけてしまう。それがよくない」と、続けた。
どうやら彼は、偉人の名言、注目したニュース、興味を惹かれた論文などをスマホ内で収集し、なにか話題が出るたびに、それらの情報を取り出して解説することが癖になっているらしい。
私が聞かれるがままに、撮影した女性のエピソードなどを話すと、彼はそのたびにスマホを取り出し、「その話に繋げると、こういうことを言ってる人がいます」と、引用を始めるのだった。そして、途中でハッとし、「またやってしまった。これがダメなんだ」と頭を抱えるというのが、2回3回と繰り返された。
つまり、彼は病的なデータ主義者。エビデンス依存症なのである。それをカッコイイと思っている自分に悩んでいるのである。
「どうして女性は、そうならないんですか?」
おもむろに顔をあげ、そう聞いてくる。
私は、答えた。
「うーん、たとえば女性って、なにか酷い目にあって泣いてるときでも自撮りしてたりするじゃないですか。かっこつけるのとは逆に、無様な自分を晒したいって欲求があるんじゃないですかね」
すると彼は、動揺した様子で「そんな姿を見られてもいい……、見られても平気……!?」とうわごとのように言い、「やっぱり女性にはかなわない。自分には絶対にできない。今から野球選手になりたいっていうのと同じくらいできない」と、また頭を抱えるのだった。
彼は、1時間ほどその件についてギャラリーで喋ると、「『リンゴは赤い』って概念を捨てたほうが広がりがあるんですね」とつぶやいて、静かに帰っていった。
このような高度な悩みは、AIがどれだけ発達してもロボットには再現できないだろう。しかし、だからこそ真の意味で人間に似せたいというのなら、「負の感情」を搭載すべきではないのか。
電車が遅れて駅員に怒鳴り散らすロボットや、混雑した場所でわざとぶつかってくるロボットができれば、「人のふり見て我がふり直せ」にも繋がる。ロボットを見て幻滅し、「あんな風になりたくない」と思った人類が、より品行方正に向かう可能性だってある。
ロボットには、楽しいことではなく苦悩こそ背負わせる。それこそ、人間の進化に役立つ気がしてならない。
それが、人間

写真家・ノンフィクション作家のインベカヲリ★さんの新連載『それが、人間』がスタートします。大小様々なニュースや身近な出来事、現象から、「なぜ」を考察。