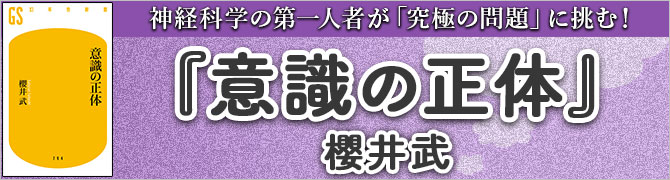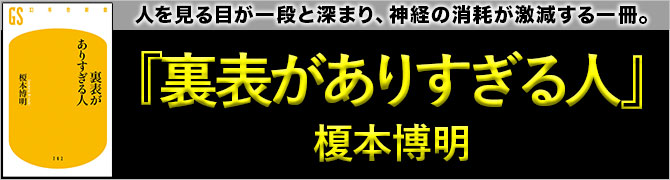迫りくる戦闘機、燃え上がる家々、耳をつんざく叫び声――あの日の記憶は消えない。
東京大空襲を体験した元NHKアナウンサー・鈴木健二が、太平洋戦争の混乱と喪失を赤裸々に語る。書籍『昭和からの遺言』より、一部を抜粋してお届けします。
軍隊は「むやみに殴られる恐しい所」
小学生の頃、自転車の部品製造の町工場がわが家の稼業でしたが、働いていた一人の職工さんが、徴兵されて軍隊へ行きました。
しばらくして、休暇でわが家を訪ねて来たのですが、その顔を見て、小学2年生だった私は思わず母の背中に隠れました。
左の眼が腫れ上がって、紫色になっていたのでした。四谷怪談のお岩さんのようでした。
どうしたのその眼。痛いでしょと母が聞くと、
「うーん、痛い。軍隊てとこは、理由もなしに、むやみに殴るんだよ」
「悪いことしたの」
「いや、朝早く起こされて整列した時、同じ班の一人が、手が滑ったらしくて、持っていた鉄砲が地面に倒れたんだ。そうしたら班全員がたるんどる、恐れ多くも天皇陛下から賜った銃を、地面に倒すとは何事かって、新兵ばかりだった俺達の班5人全員が殴り倒されたんだ。連帯責任とかで」
「レンタイ、ナニ?」
「一緒に働いている人全部が悪いってことだよ」
母が言葉を補いましたが、以来気が小さかった私は軍隊はわけもなしに、むやみに殴られる恐しい所だという印象を強く持ってしまいました。余計に軍関係の学校を志願する人の気が知れなかったのです。
「非国民」と呼ばれた日
中学校以上の学校には、敗戦の日まで、配属将校という名の軍人が1人いて、週に2時間ぐらい、教練といって、軍人になるための教育をして、敬礼の仕方から鉄砲の撃ち方までを教える授業がありました。ある日、その配属将校と1年生の私は廊下でばったり出会いましたので、教わっていた通りに、廊下の隅に寄って、型通りの敬礼をしました。するとなぜか私の名前を知っていて、突然質問してきました。
「お前はどこの学校を志望するのだ」
「は、あの、僕は生まれつき体力がないのと、小学校時代からメガネを掛けているので、たぶん軍関係の学校の試験を受けても、落第すると思うので、どこかの高等学校の文科へ行こうと考えています」
と答えると、大喝一声して怒鳴りました。
「この非国民めっ。しっかりしろっ」
非国民というのは、昭和になってからの最低の軽蔑の言葉でした。
国家から強要されていた「軍国の母」の涙
大本営発表は常に日本大勝利なのに、20歳になると文科系の学生さんは学問を捨てさせられて兵隊になることが決まりました。
私のたった1人の兄清太郎(清順・映画監督)も、昭和18年10月の第1回学徒出陣となり、神宮競技場で雨の中を行進し、東条英機首相の発声に合わせて、万歳を三唱させられ、それからすぐ小学校時代の同級生3人と一緒に、町内中の人の歓呼と日の丸の小旗に送られて出征しました。
その日の真夜中、私は小さな音に目をさましました。そーっと起き出してみると、音は台所の方から聞こえてきました。忍び足で近づいてそっとのぞき、目をこらして見ると、母が板の間の上で、崩れ落ちるような姿勢でうずくまり、悲しそうな声を出してすすり泣いていました。
私は生まれてから母が亡くなるまで、気丈な明治生まれの母の泣き声を耳にしたのは、この時だけでした。昼間は笑顔で皆さんにお見送りありがとうございますと言っていたのにです。当時の女性の多くは、軍国の母と呼ばれていましたが、その姿は国家から強要されていたのです。
本当の母親は深夜にひとりすすり泣いて、わが子との訣別を嘆き悲しんでいたのです。
* * *
この続きは書籍『昭和からの遺言』をお求めください。