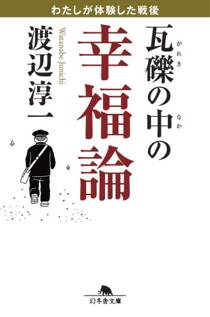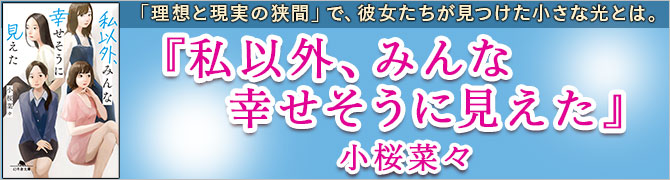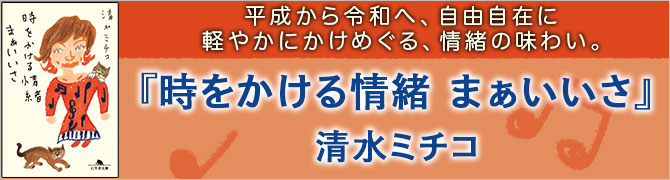太平洋戦争のただ中を生き抜いた作家・渡辺淳一が、自らの記憶をたぐり寄せ、人生の根底を形作った「戦後」を語る。生きる重さと希望を問い直す珠玉の回想録『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』より、一部を抜粋してお届けします。
* * *
わたしが小学校三年生のとき、父が札幌の旧制中学に勤めることになり、わたしたち一家は札幌に移ることになった。
ここではもはや、炭鉱町のような荒々しい事件を見ることはなかったが、虐待されていた朝鮮人のことは、なお頭に深く残っていた。
川原の飯場
わたしの一家は歌志内から車で一時間半ほどの、やはり炭鉱町の上砂川に住んでいたが、父も渡辺家の娘であった母の婿養子となったことから、当時、母が勤めていた上砂川小学校に、ともに勤めていた。このことからもわかるように、わたしの家は母系家族であった。
この上砂川町には、祖母の弟もいて、市街地で仙田という新聞店をやっていた。わたしはここにもよく遊びに行き、二人の又従兄弟と親しんだが、仙田家は市街地の南にあり、広い庭の下は崖になっていて、そこにあまり大きくない川が流れていた。
その川原にやや横長の宿舎のようなものがあり、崖の上からときどき眺めていたが、大叔父に一言だけ注意されたことがある。
「下におりて、あの宿舎に近づいてはいけないぞ」
それは何故なのか。注意されると、かえって行ってみたくなる。そこで又従兄の徹ちゃんにきくと、「あそこは朝鮮人の飯場で、朝鮮人がいるからだ」と。
当時の朝鮮は日本の植民地で、いわゆる朝鮮人がかなり大量に日本に連行され、炭鉱労働などに従事させられていたようである。
朝鮮人を見るくらいならいいのではないか。そう思いながら見詰めていると、さらに徹ちゃんが教えてくれた。
「あいつらはな、飯のときも立ったまま食うんだ。そしてときどき、日本人の監督に殴られた奴が、アイゴー、アイゴーといって泣いている」
そんなことが、川原の飯場でおこなわれているのか。わたしは怖いような不気味な気持ちにとらわれて、さらに覗いてみたくなってきた。
棒にぶら下げられて
徹ちゃんの話を聞いて、改めて思い出したのが、冬になると屋根の雪下ろしに来る人夫のことだった。
わたしの家は三井炭鉱の職員たちが住む、朝陽台というところにあったが、人夫が来るおかげで、雪下ろしをする必要がなかった。
それまで、わたしは人夫と話すことなどなかったが、改めて考えてみると、彼らは朝鮮人のようである。
母はこの人たちに、よくお握りなど渡していたので、かわりにわたしが持っていってやると、両手を合わせるようにして受け取る。そして余程、お腹が減っているのか、その場で即座に食べてしまう。
そうか、彼らは凄く厳しい条件の下で働いているのか。わたしは今まで、知らなかった世界を垣間見たような驚きを覚えた。
だが、驚きはそれだけではなかった。それから半年くらい経った頃、やはり市街地に行ったとき、「どけどけ……」というような声とともに行列が近づいてきた。
「なんだろう」と思って振り向くと、大きな丸太に半裸の男が両手両足を縛られたまま吊るされている。
男は間違いなく朝鮮人で、それを担いでいる二人の男も朝鮮人である。
しかし真っ先に胸を張って歩いているのは日本人で、うしろから従いていくのも日本人である。
「どうして、あんな目に……」
わたしは信じられず、仙田の大叔父さんにきくと、「仕事中に、怠けたからだろう」という。
それにしてもあれではあまりに酷いではないか、まさに虫けら以下である。
「あの一番前にいるのが、日本人の人夫頭で棒頭というんだ」
「あの人、殺されるの?」
「わからない」
なにをしたとしても、朝鮮人をあんな目にあわせていいのだろうか。わたしは身近の日本人が急に怖くなってきた。
植民地の実態
札幌のわたしの家の近くに住んでいた、佐藤のおじさんは以前、仕事の関係で一度、朝鮮に行ったことがあるらしい。
そこで改めてきいてみると、今の朝鮮人のほとんどは日本語が話せるという。
すでに二十世紀初めに、日本は武力で韓国を併合し、植民地化していた。このため、朝鮮人は強制的に日本人として組み込まれ、日本語を覚えるよう強要され、さらに、彼らが本来もっていた姓や名前も、日本式の名前に改められたとか。
そんなことが、朝鮮で現実におこなわれていたのか。わたしが不安になってきくと、おじさんは、「もちろんだよ」とあっさりうなずいた。
「日本人に、してやったんだから」
おじさんは当然のようにいったが、彼らにとっては、喜ぶべきことではないのではないか。
実際、このあと朝鮮人の一部は日本軍に組み込まれて戦地に送られ、朝鮮の女性の一部は従軍慰安婦として、戦場にも駆り出されたらしい。
さらに日本各地に労働力として送り込まれた朝鮮人の総数は、二百万とも三百万ともいわれている。
この頃、わたしは夏休みになると、決まって歌志内の祖母の家に遊びに行っていた。
たまたま夏休みのときだったろうか。祖母は雑貨店の裏に何軒かの貸家を持っていたが、そこに玉木さんというおじさんがいた。
まだ三十代くらいだったか。大柄だがわたしに空中ブランコなどしてくれて、優しい人だったが、あるとき、彼の隣りに住んでいたおばさんが、「あの人、棒頭だよ」といったのを聞いて、わたしは息をのんだ。
棒頭といったら、あの丸太の棒に吊るされた朝鮮人の男を殴りつけていた男ではないか。そんなことを、この優しいおじさんがするのだろうか。わたしは一瞬、信じられず、しばらくして、そっと当人にきいてみた。
「おじさん、棒頭なの?」
瞬間、おじさんは目を細めて、「そうだ、こう見えても、俺は強いんだぞ」と胸を張ってみせた。
正直いって、わたしはなにがなんだかわからなくなってきた。
あんなに、優しくしてくれるおじさんのなかに、裸の朝鮮人を丸太に吊るす、もう一人のおじさんが潜んでいるのだろうか。
人間の二面性、などという、難しい言葉など、わかるはずもない。しかし人間のなかには、すごく優しい面と信じられないほど残酷な面と、二つが巣くっているのかもしれない。
この思いは、その後深く、わたしの心に残った。
* * *
この続きは書籍『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』をお求めください。
瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後
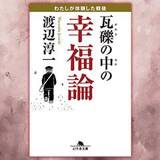
太平洋戦争のただ中を生き抜いた作家・渡辺淳一が、自らの記憶をたぐり寄せ、人生の根底を形作った「戦後」を語る。生きる重さと希望を問い直す珠玉の回想録『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』より、一部を抜粋してお届けします。