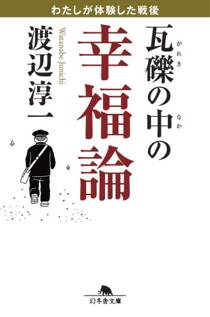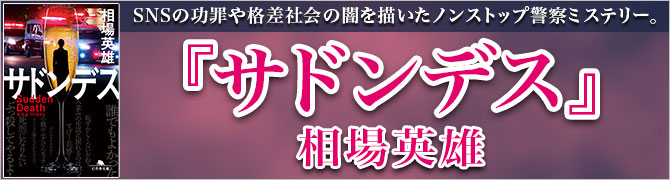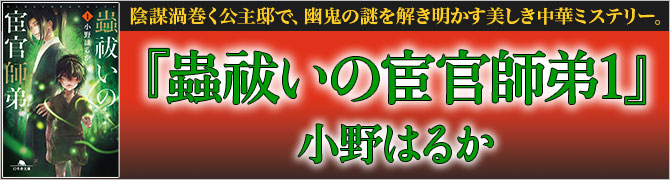太平洋戦争のただ中を生き抜いた作家・渡辺淳一が、自らの記憶をたぐり寄せ、人生の根底を形作った「戦後」を語る。生きる重さと希望を問い直す珠玉の回想録『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』より、一部を抜粋してお届けします。
* * *
この頃、市内でよく見かけたのが、白衣の兵士である。
突然、こう書かれても、意味がわからない人が多いかもしれないが、これは文字通り、白衣を着た元兵士のことである。
街角の風景
当時、やや賑やかな街角には、白衣を着たままの元兵士が立っていて、ハーモニカを吹いたり、稀にギターを弾いている人もいた。
元兵士とわかったのは、みな戦闘帽をかぶっていて、片脚か片腕を失っている。その意味では、元傷病兵といえばいいのかもしれないが、松葉杖をついていたり、箱を積み重ねた上に座っている人もいた。
しかし、いずれの兵士の前にも小箱が置かれていて、そこにわずかの小銭が入っている。傷病兵に同情した人たちが投入した募金である。
元兵士たちは敗戦とともに、一般の家庭に戻されたのか、あるいはそれ以前から家庭で療養していたのか、いずれにせよ、そのままでは生活ができなくて、街頭に出るようになったのかもしれない。
当時、これらの人たちにどれくらいの恩給や年金が支払われていたのか、わたしにはわからなかったが、払われたとしても、敗戦直後だけに微々たるものだったに違いない。
これら、白衣の兵士を見ると、みな、先の悲惨な戦争のことを思い出すのか、無言で目を伏せ、なかには軽く頭を下げて、いくらかのお金を置いていく人もいた。
彼らが演奏する曲は、古い日本の歌謡曲のようだが、その前に立ち止まって聴いている人はほとんどいない。
わたしも何度か立ち止まりかけたが、それほど上手ではないし、それ以前に、彼らの前に立っているのが、なにか辛いような、切ない気分になったからである。
結局「ご苦労さま」と、目で一礼して通り過ぎるだけで、お金を投じることはなかった。
なにか子供の分際で、そんなことをするのは、やりすぎのように思えたし、それらおじさんたちの現実に、あまり近づきたくない、という気持ちがあったこともたしかである。
日米の兵士が
個人的な感情はともかく、これら街角の白衣の兵士の姿はときに奇妙な思いを誘うこともあった。
たとえば、彼らが立ってハーモニカを吹いている。その数十メートル先の靴磨きの少年の前では、アメリカ兵が足を突き出して、日本の少年に靴を磨かせている。
何気ない、穏やかな午後の街角の風景だが、見方を変えたら、さまざまなことを思いおこさせる。
もしかしたら、その白衣の兵士と靴を磨かせているアメリカ兵は、つい少し前には前線で銃を向け、戦い合った相手かもしれない。
その二人が、一方は街行く人にお金を求め、一方は元敵国の少年に自分の靴を磨かせている。
まさしく、戦争に負けるとは、こういうことなのかもしれない。そんなふうに思ったこともあるが。
それにしても、あの白衣の兵士や靴磨きの少年のところに、ヤーさんは現れないのか。カレンダーを売っていたわたしたちに、ショバ代を払え、といったように、お金をたかることはないのだろうか。
興味がわいて見ていたが、彼らが近づく気配はなさそうだった。
さすがにそこまで、たかる気になれなかったのか。それとも白衣の兵士には、多少の敬意を抱いていたのか。ともかくほとんどの人が、見て見ぬふりをしているようだった。
偽りの兵士
街角の、白衣の兵士の姿に馴染んだ頃、ある奇妙な噂を耳にした。
それは、クラスの仲間が教えてくれたのだが、街角の兵士のなかには、偽りの兵士も加わっている、というのである。
偽りの兵士とは、戦争に行って本当に傷ついた元兵士ではなく、白衣だけ着て、傷ついたように見せかけているのだという。
でもどうして誤魔化すのか。不思議に思ったが、なんでもないのに片手を包帯で吊ってみたり、片脚を折り曲げたりして、誤魔化しているのだ、という。
「ずるい奴だよ」
友達は怒ったようにいったが、わたしはそんなふうに怒る気になれなかった。
たしかに傷病兵でもないのに、外見だけ真似て金を無心するなど、ずるいといえばずるいが、あんな恰好をして、街頭に立つのも、結構大変かもしれない。
だいたい、あんなところで白衣を着る気になれないし、寒い日など、あれを着ただけで街頭に立っているのはなかなか大変である。
「いいんじゃないか」
わたしがあっさりいうと、友達は不満そうに押し黙っていたけれど。
それにしても、靴磨きの少年は磨き方をどこで覚えてきたのだろうか。
まず、ほとんどが小学校の低学年のようだが、靴磨きのブラシや靴墨は、どこから買ってきたのか。そして靴台や自分の座る椅子は、どれを見ても、ほとんど同じような台を揃えている。
さらに磨き方は誰に習うのか。いろいろ勝手にやっているうちに、客のアメリカ兵が教えてくれたのか。それとも他の仲間がやっているのを、見よう見真似で覚えたのか。
それにしても、彼らはみな手つきがいい。
しかも終わったあと、アメリカ兵に「マネー」と英語ではっきりいって、ときにはチップももらっているようである。
あれなら金儲けになるし、英語の勉強にもなるので、一挙両得である。
わたしは半ば感心しながら、ときどき見とれていた。
* * *
この続きは書籍『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』をお求めください。
瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後
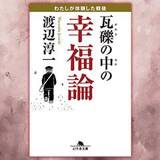
太平洋戦争のただ中を生き抜いた作家・渡辺淳一が、自らの記憶をたぐり寄せ、人生の根底を形作った「戦後」を語る。生きる重さと希望を問い直す珠玉の回想録『瓦礫の中の幸福論 わたしが体験した戦後』より、一部を抜粋してお届けします。