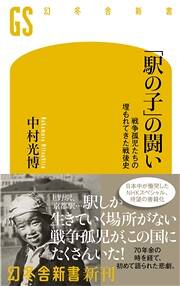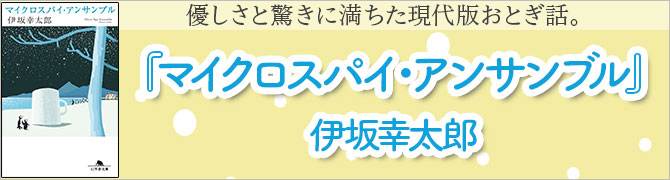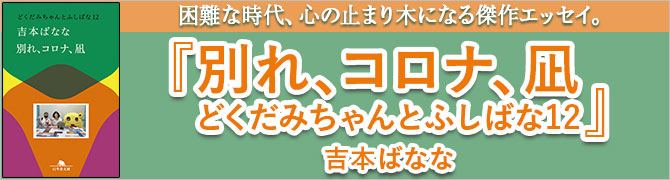敗戦は終わりではなく、戦争孤児たちにとって“地獄の始まり”だった――。
「クローズアップ現代+」や「NHKスペシャル」などでディレクターを務めてきた中村光博さんが、戦争で親を失った子どもたちへの綿密な取材を元に戦後の真実を浮き彫りにした幻冬舎新書『「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』より、一部を抜粋してお届けします。
野良犬から教わった残飯の食べ方
復興が進み始めてもなお、路上生活を続け社会から嫌われていった「駅の子」たち。当時子どもたちは何を思っていたのか。
そのあたりを、詳しく教えてくれたのが埼玉県秩父郡小鹿野町で暮らす戦争孤児、山田清一郎さん(83歳、昭和10年生まれ)だった。
山田さんは、子どもの頃、家族で神戸で暮らしていた。10歳だった昭和20年3月、空襲で父を、6月には同じく空襲で母を亡くし、戦争孤児となった。
家も焼け、行き場をなくした山田さんは、自然と仲間になった同世代の子どもたちと一緒に、「駅の子」として生活をするようになった。しばらくの間、地元神戸で過ごした後、新天地を求めて、東京・上野に移動した。神戸でも上野でも、残飯をあさって、飢えをしのぐ生活だったという。
「人間の一番の欲は、食欲ですよ。本当の空腹となると、もう人間でなくなるというか、犬猫と同じで、食えるものならなんでも、どんなものでも手に入れて食う、これは生きるための本能じゃないですか。
闇市には食べるものがあってももらえるわけではないので、盗って食うしかないわけ。盗って食うか、拾って食うか、これしかないわけですね。だから捨てられているものを拾って、古くなったものばかり食べるんですね。始終、お腹を壊して、下痢をしていました。
そんなあるとき、空腹に耐えているときに、野良犬を見たんですね。すると野良犬は、残飯を桶かバケツから食べるとき、食べ物の上の方を上手に食べるんですよ、こうやって桶につかまって。私たちは腹が減っているから、思わず手を突っ込んで下の方から持ってきて口に入れるもんなんだけど、実は、下にあるものの方が傷みが激しいわけですよね。
だから、腹を壊さないためには、食べ物は表面のものを食べる。これは野良犬が飯食ってるのを見て教わったってことだね」
洗えない、着替えられない、路上の現実
傷んだものを口にし、激しい腹痛に苦しんだ末に、命を落とした仲間もいたという。
しかし、つらいのは飢えだけではなかった。身なりもひどい状況だったという。長期にわたる路上生活で、着ている洋服は、これ以上ないくらい汚れてぼろぼろとなり、においなども自分では分からなくなるほどの悪臭を放ったという。
「同じものを何カ月も着てますね。進駐軍がくれるんですよ。それを着て、ずうっと。風呂は入らない、顔も洗わない、着替えをするものもない、だから着たら着たまま。それをね、何日じゃなく、何カ月も着てる子どもが多かったということですね。
においなんて消えちゃいますね、ある一定の臭さがくると。昔はシラミなんていう虫にみんなやられていたんだけど、それさえも寄りつかなくなってしまう。
シャツがシャツでなくなる、硬くなっちゃう。全然洗ってない、同じものをずうっと着ていると、こちこちになって段ボール着てるみたいになる。でもだんだん、そういうものが気にならなくなってくる。同じものを何日着ていても、全然それが気にならないからね……怖いよね」
戦争孤児から「治安の敵」へ
孤児たちは、生きていくのに必死だった。しかし、汚れた服を身にまとい、食べ物を求めて町を徘徊し、ときには盗みまでする山田さんたちに、社会は冷たかった。大人たちは「駅の子」たちを野良犬のように扱ったという。
「駅の待合室に私たちが入っていると出ていけと追っ払われる。蹴飛ばされる。それから店に行ってなんか拾ってこようとすると水をかけられたり、野良犬だってわけでね、お客さんからもらった棒を持って、店の人にこの野郎なんて追いかけられる。そういうことが多かったですよ。
人間が人間にやることじゃないですよね、相手が浮浪児であったとしてもね、まさに野良犬に対する扱いと全く同じだよね。いま考えると、よくあんなことができたな。なんで浮浪児になったのか、知ってるはずなんだよね」
当初は、戦争の犠牲者として同情の目もあっただろう。しかし、戦争の爪痕が消え始めると、「駅の子」たちは、ただ社会の治安を乱す存在として認識されていった。そうした認識が、「駅の子」たちの心を傷つけ、ますます孤立させていったのだ。
* * *
この続きは幻冬舎新書『「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』をお求めください。
「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史
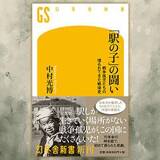
敗戦は終わりではなく、戦争孤児たちにとって“地獄の始まり”だった――。
「クローズアップ現代+」や「NHKスペシャル」などでディレクターを務めてきた中村光博さんが、戦争で親を失った子どもたちへの綿密な取材を元に戦後の真実を浮き彫りにした幻冬舎新書『「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』より、一部を抜粋してお届けします。