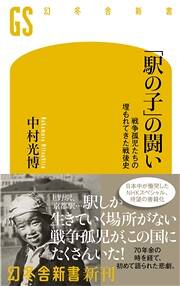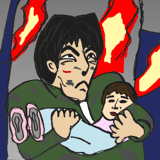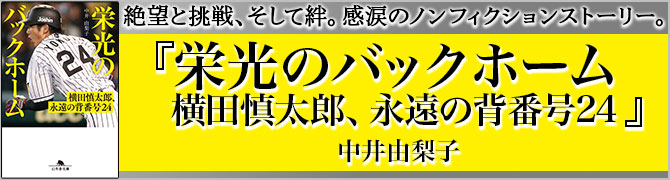敗戦は終わりではなく、戦争孤児たちにとって“地獄の始まり”だった――。
「クローズアップ現代+」や「NHKスペシャル」などでディレクターを務めてきた中村光博さんが、戦争で親を失った子どもたちへの綿密な取材を元に戦後の真実を浮き彫りにした幻冬舎新書『「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』より、一部を抜粋してお届けします。
神戸を襲った容赦ない空襲
神戸市で生まれた内藤さんは、母子家庭で育った。父の記憶はないが、映画界の実力者だったと聞かされたことがある。そのためか、母は神戸市の春日野道にある小さな映画館の実質的な運営を任されていたようだ。
学校が終わると、母が切り盛りする映画館の2階にある座敷の部屋に直行し、倉庫代わりになっていた押し入れに山積みになっている上映済みのフィルムを眺めるのが大好きだった。普通は目にすることができない映画のフィルム。その珍しさから「見せてほしい」と、学校の友達が毎日のように自宅についてきたことは、内藤さんの自慢だった。
母は女手一つで子どもたちを養うために、休みなく働いていたが、子どもたちには、いつでも優しかった。時々、休日に妹と一緒に、神戸の繁華街にあった食堂に連れていってもらい、腹いっぱいになるまで食べさせてもらったことが、家族で過ごした平和な日々の思い出として刻まれている。
しかし、昭和20年6月5日、神戸を狙ったアメリカ軍による空襲で、幸せだった日々がすべて奪われた。
三菱造船所や神戸製鋼所などが大きな工場を構える日本の軍事産業の一大拠点であり、世界とつながる貿易港としても重要な役割を果たしていた神戸。昭和20年になると3月、5月と、大規模な空襲の標的になり、神戸の市民たちはアメリカ軍の容赦ない空襲の恐ろしさを身をもって体験していた。
そして、3回目の大規模な空襲となった6月5日。朝6時過ぎから、神戸の町に警報が響き渡り、7時半を過ぎた頃、350機を超えるB29が一気に神戸上空を襲った。
焼夷弾の雨からなんとか逃げ延びて
内藤さんは、当時、小学6年生の12歳。空襲が始まると、すぐに家を飛び出し、恐怖の中、何も考えずに必死になって逃げた。
「焼夷弾っていうのはね、落ちてくると夕立のときのようなザーッていう音がするんですよ。そのザーッという音が聞こえ出すと、逃げている人はみな反射的に道路にばばばっと体を伏せてね。攻撃が落ち着いた隙を見て、またみな一斉に逃げ出すわけなんですけど、私が逃げるために立ち上がったら、伏せていた人のもう3分の2は立ち上がらないまま。焼夷弾の直撃を受けて、みな死んでました。
そんな状況で、タイミングを見てまた逃げ始めるのだけど、猛烈な熱さに襲われて息ができないんですよ。私はとっさに防火用水がためてあったところに、服のままザブンとつかってね、それでまた火の海の中を逃げていきました。それでも、どうも足の方が熱いぞと思って見てみると、靴が地面の熱さで溶けて、靴底が全部なくなってしまっているんですよ。足の裏は全部やけどしていました」
当時、学童集団疎開によって、同級生たちは神戸を離れ、田舎で生活していた。内藤さんは、体が弱く、どうしても母親から離れたくないと言って、地元神戸に例外的に残っていたのだ。本来なら、疎開先に避難していて神戸を離れていたはずの12歳の少年が体験した、神戸空襲の貴重な証言だ。
3回目となる6月5日の空襲は、神戸に壊滅的な被害を与えた。町は焼き尽くされ、3000人以上が命を奪われた。
命こそ助かったものの、一緒に逃げていた母と途中ではぐれてしまい、気づいたら一人になっていた。焼けてしまった自宅の跡地や通っていた小学校など、母が避難していそうな場所を必死で探し回ることおよそ1週間、別の地域の小学校を訪ねてみると、避難している人たちのために調理をしている女性たちの中に、母の姿があった。母もすぐに、内藤さんに気がつき、駆け寄ってきた。
「よう生きとったね。必ずどこかで生きていると信じていた」
母はそう言って強く抱きしめた。内藤さんも張り詰めていた緊張が解け、声を上げて泣いた。しかし、家を失い、財産もすべてなくした母は、激しく落ち込み、途方に暮れた様子だった。
目の前で母を亡くし「駅の子」に
母に連れられて向かったのが三宮駅。国鉄だけでなく阪急、阪神などの私鉄も通る交通の要であり、当時から昼夜問わず賑わっている神戸の中心地だ(国鉄の表記は「三ノ宮」)。人が多く集まる場所に行けば食料なども手に入りやすく、生きていけるのではないかと考えやってきたものの、現実は甘くはなかった。食べる物はほとんどなく、飢えに苦しむ日々が始まった。
寝床にしたのは、三宮駅の待合室。母は、内藤さんがお腹をすかせないようにと、日中、神戸の中心地を歩き回り、毎日どこからか、その日に食べる一人分の食料を入手して、待合室で待つ内藤さんに持ってきてくれた。内藤さんは、母が手に入れてきた食べ物を夢中で食べ、腹を満たした。
しかし、母は、先の見えない路上生活による心労に加えて、食事もほとんどすべてを内藤さんに与え、相当な無理をしていたのだろう。体調を崩して、日を追うごとに衰弱していった。
「母親はゴミ箱をあさって食べ物があったらそれを持ってきて、私に食べさせてくれる。私はそれを食べてなんとか過ごしていたんですけれども、母親は自分が全く食べないから栄養失調にかかってどんどん細くなってしまったんです。そんな中、絞り出すような声で『妹が疎開しているから、必ず迎えにいってやってくださいよ』と言われてね。それが私の母親との最後の会話になってしまったわけなんです。
つないでいた手もだんだん冷たくなっていくのが分かるんで。一生懸命、『お母ちゃん、お母ちゃん』と呼んだけども、もう、それが最後で亡くなった。畳の上で死なせてやりたかったなという気持ちを、いつも持ってるんです」
生き抜くために背負った兄の役割
三宮の駅舎で、母を目の前で亡くしても、内藤さんに、悲しみにひたっている余裕などなかった。一人になり、「駅の子」として自分の力だけで生きていかなければならなかったからだ。
生きるために必死な毎日を過ごすうちに、いつの間にか戦争は終わっていた。秋になると、母との最後の約束を守るために、疎開から帰ってきた妹を地元の小学校に迎えにいった。どのように母の死のことを伝えればいいのか、ただただ気が重かった。久しぶりに元気そうな妹の顔を見て安心はしたものの、母の死のことだけはどうしても言い出せなかった。
空襲で自宅は全焼してしまい、仕方なく三宮駅の待合室で寝泊まりをしていることを伝えると、妹もすべてを察したようで、それ以上は聞いてこなかった。母がどのように亡くなったのか、今日まで妹に直接話したことはないという。
「駅の子」としての生活に妹も加わった。これまで自分の世話をしてくれた母親の代わりを果たさなければならなくなった内藤さん。妹を食べさせていくためには、手段を選んでいる場合ではなく、物乞いだけでなく、ときには、盗みをすることもあったという。
当時の様子を聞くために、私は内藤さんとともに三宮へと向かった。三宮駅の南側、買い物客でいつも賑わっているメインストリート、三宮センター街に来ると、内藤さんの記憶が蘇ってきた。当時、ここには巨大な闇市ができていて、内藤さんの食料の調達場所となっていたという。
「えーと、終戦直後からすでに、ここから全部が闇市だったんですね。地面に机を置くとか、そういうような感じで店をつくって、ずーっと向こうの方まで並んでいました。私はそこに並べられた商品を黙って盗って、急いで逃げるとかしていました。もう悪に関しては絶対やらないと食べられへんしね。悪いとは分かっているんだけども、妹と二人で生きていくためには、そうしないといかんと思ってね」
スリをしてでも、生きていくために
闇市は大勢の人で賑わっていたが、終戦直後の混乱期で、警察すら手をこまぬく無法地帯の様相を呈していた。やくざや外国人の集団が互いを牽制し合うことで、かろうじて秩序が保たれていたと内藤さんは言う。
そんな闇市で出会った浮浪者の男性が、内藤さんきょうだいの境遇を案じてか、とてもかわいがってくれた。そして「生きていくためにスリというものを教えたる」と言って、その手口を教えてくれた。
特に丁寧に教えてくれたのは、当時「チャリンコ」と言われていた手法。カミソリの刃の部分を指と指の間にはさみ、通行人のハンドバッグやナップサックの底の部分をすれ違いざまに切り裂き、路上に落ちた財布などの貴重品を拾って逃げる、というものだった。小銭が落ちる「チャリン」という音からそう呼ばれていたのだろうか。
内藤さんも必要なときには、「チャリンコ」に手を出したという。
終戦後の混乱の中で、自分が生きていくために、そして妹の命を守りぬくために、12歳の少年が、文字通り、悪いことでも何でもしなければならないほど追い込まれていた。内藤さんの穏やかで優しい口調と、その証言の過激な内容とのギャップが強く印象に残った。
* * *
この続きは幻冬舎新書『「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』をお求めください。
「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史の記事をもっと読む
「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史
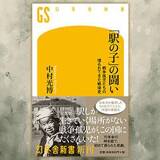
敗戦は終わりではなく、戦争孤児たちにとって“地獄の始まり”だった――。
「クローズアップ現代+」や「NHKスペシャル」などでディレクターを務めてきた中村光博さんが、戦争で親を失った子どもたちへの綿密な取材を元に戦後の真実を浮き彫りにした幻冬舎新書『「駅の子」の闘い 戦争孤児たちの埋もれてきた戦後史』より、一部を抜粋してお届けします。
- バックナンバー