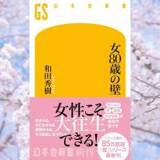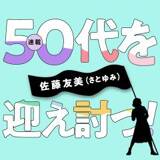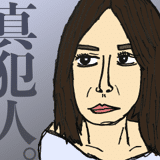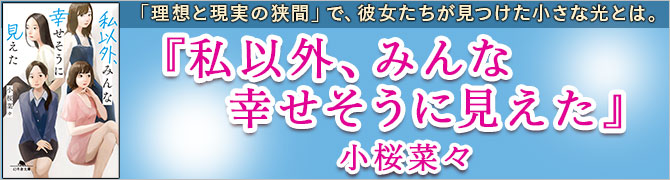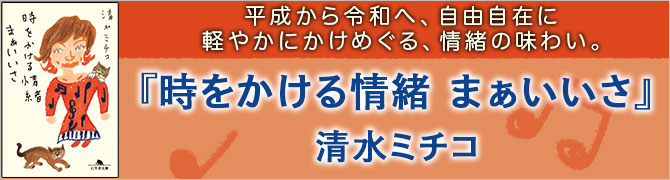体力も気力も70代とは全然違う「80歳」の壁。その壁をラクして超えて、寿命をのばす――その秘訣がつまった『80歳の壁』は、2022年の年間ベストセラーにもなりました。そんな「壁シリーズ」の最新刊『女80歳の壁』が出版されました。
「夫の世話・介護からくるストレスや負荷」「骨粗しょう症による骨折で歩けなくなる」など、ぶ厚い障害を乗り超え、高齢期を楽しみ尽くすための生活習慣を詳細に解説した一冊。本書から、一部をご紹介します。
* * *
懐の 深い人ほど いい・加減
私が幸齢の方によく言うのは、「いい加減に生きてみたら」ということです。
人生経験の豊富な幸齢者は、いい加減に生きるには、最適なのです。
「いい加減」と言われると、悪口のように聞こえるかもしれません。でも、これはほめ言葉だと、著者は思っています。
いい加減=良い・加減。
「バランスがいい」とか「ちょうどよい」という意味です。
人生の酸いも辛いも甘いも経験している幸齢者だからこそ、最高の“いい加減人間”でいられるのだと、むしろ胸を張ったらいいのです。

日本はいま、閉塞感で覆われています。ちょっと悪い面が見つかると、寄ってたかって袋叩きにする。そして、人格のすべてを否定する。
健全な社会とは言えませんよ。なぜなら、欠点がひとつもない、悪い心がひとつもない人なんて、世の中にはいないのですから。
テレビのコメンテーターに同調して「あいつはけしからん」と社会全体が流されてしまう現在の風潮は、とても恐ろしいと、私は思っています。こんなときに「まあ、人間ってそういう愚かな面もあるよね」と、堂々と意見できるのが、幸齢者の強みだと思うのです。
さまざまな経験をしているからこそ、人の痛みや苦しみがわかります。弱さに寄り添うこともできます。それが幸齢者の人間的な深み、器の大きさだと思うのです。
人に好かれようとして世間に迎合するよりも、人生の経験を活かして“いい加減(良い・加減)”に生きる。そのほうが、晩年は楽しいと思うし、結果的に、人に好かれるようになると思うのです。
意見され ボケたふりして 聞き流す
いい加減とは、人に流され、ふらふらと生きることではありません。
自分の軸をしっかりと持つからこそ、いい加減に生きられるのです。
自分の軸は、どうやってつくるのか?
それは、物事をよく考えることでしょう。
例えば、ロシアとウクライナの戦争を見て、「どちらが正しいか」ではなく
「なぜ戦争になったのか」と考えてみる。攻め入ったロシアが一方的に悪で、ウクライナが正義なのか。戦争によって誰がいちばん得をしているのか、を考えてみる。
こうやって、考える習慣があると、自分の中にしっかりとした物差しができてきます。すると、人に流されず、自分の意見を持てるようになるのです。
「老いては子に従え」なんて諺がありますよね。年をとったら出しゃばらず、子の意見や方針に従うべきだという教えです。でも、よく考えたら、この諺は権力者が自分の都合のいいように社会を動かすための方便だとわかります。
物事がよくわかっている幸齢者に反対されると困る。そこで「老いては子に従え」という体のいい言葉で、黙らせたに過ぎないのです。
老いた、というより人生経験を積んだからこそ、権力者の狡猾さもわかるのです。若者の未熟さも浅はかさもわかる。世間的に偉いと言われる人や、テレビのコメンテーターが「じつは大したことない」ということもわかるのです。
なので「年寄りだから」と口をつぐむことはありません。「年寄りだから」と、堂々と意見すればいいのです。長らく低迷する日本が活力を取り戻すカギは、幸齢者の経験と深い知恵にあると、私は思っています。
純真に 好きを追いかけ 日々生きる
『GOETHE』という雑誌で、対談の連載をさせていただいています。「長生きの真意は医者ではなく大先輩に聞け」という主旨の企画で、最前線で活躍中の80歳オーバーの方々が対談の相手です。
みなさんご存じの養老孟司先生(87歳(2025年1月刊行時点、以下年齢同じ))を始め、百寿者研究で有名な柴田博医師(87歳)、毎日数千万円の株取引をする現役デイトレーダーの藤本茂さん(88歳)、アプリ開発を行う世界最高齢のプログラマー若宮正子さん(89歳)など、ユニークな生き方をされている方ばかりです。
対談して改めてわかったのは、どの人も例外なく「好きなことをやっている」ということです。
例えば、養老先生は昆虫採集とたばこ。国内の秘境だけでなく、海外にまでお目当ての虫を追っていく。重い道具を持って森林に分け入っていくんですよ。医師から止められても「うるさい」と意に介さず、たばこをスパスパ吸います。
柴田医師は、長生きしている人の実態調査をして、コレステロール値が低い人は早死にすることを突き止めた方です。現代医学の常識を根底から覆す説なので妨害もある。でも、むしろ逆境を楽しむかのように、実証研究を続けています。
藤本さんは、朝の4時から株の銘柄研究をして、市場が開く9時~15 時までパソコンの前で株の取引です。その後は今日の取引の復習をするという株漬けの生活です。脳は一日中フル回転です。血圧は220㎜Hgもありますが、医師から注意されても「血圧下げたら頭が働かん」と笑い飛ばし、意に介しません。
若宮さんは、大手の財閥系銀行を定年退職した後にパソコンを始め、81歳のときにiPhone のアプリ「hinadan」を開発しました。表計算ソフト「Excel」を使って図柄をデザインするアーティストでもあります。アップル社のCEOティム・クック氏や台湾のIT担当大臣オードリー・タン氏など、IT世界のリーダーたちが一目置く存在ですが、本人は「好きなことをやっているだけ」と涼しい顔です。
諸先輩方に対し、若輩者の私が言うのも失礼なのですが、みなさんに共通しているのは「少年、少女のように生きている」という点です。好きなこと、やりたいことに夢中になるんですね。「純真」とか「生命力が旺盛」という表現もピッタリきます。老化と闘うのではなく、寄せつけないのです。

現に若宮さんは、「年齢なんて考えたこともないわね。毎日おもしろく生きてるだけだから。でもなぜか、みなさん私に優しくしてくださるのね。危なっかしくて放っておけないんじゃないかしら」と笑います。
まさに、みなさんの生き方こそが、モテる理由なのだと思います。
好き勝手 生きてる母ぞ 愛おしき
身内のことを語るのは気が引けるのですが、母の話をします。
母は現在94歳。ひと言で言うと「好き勝手に生きている人」です。
とはいえ、私は、母の好き勝手に育てられたわけではありません。私や弟を育てるために、母はそれなりに自分を抑えていたのだと思います。
母はお肉が嫌いで、がりがりに痩せています。運動もしない。長生きしているのが不思議なくらいです。私が「お肉を食べたほうがいいよ」とか「少しは運動したら」と言っても完全に無視です(笑)。
自分が好きなものを食べ、好きなことを言い、好きなように生きています。
その意味では、私が本で書く「自分勝手に生きましょう」を、実践してくれているのかもしれませんね。
好き勝手は、年をとってから強まっているように感じます。
70歳のときには、「夫と同じお墓には入りたくない」という理由で、あっさりと離婚してしまいました。当時、私は40歳、娘たちは小学生でしたが、驚きはあ
りませんでした。娘たちは「おばあちゃんらしいよね」と笑っていたほどです。
30年ほど前に、大阪で暮らしていた母を東京に呼び寄せました。当時私は、医師をする傍らで通信教育の事業もやっていて、母に社長をお願いしました。
まあ、そこでも好き勝手でしたね。言いたいことを言うので、社員も定着しません。給料はあるだけ使ってしまう。外交的な人ではないので、おしゃれして出かけるわけではないのに、百貨店で服を買うんです。店員さんにちやほやされるのが、うれしかったのかもしれませんね。
「母が長生きする理由」が、もしあるとするなら、「好き放題に生きている」ということしか考えられません。
人と仲良くしようともしません。だから友だちも多くない。なのに、寂しそうでもない(笑)。
友だちが少ない分、孤独で苦しむこともないわけです。そもそも自分のわがままで友だちをつくらないわけだから、寂しくないのです。「友だちがいないと寂しい」というのは、世間の勝手な思い込みであり、本人は違う価値観で生きているわけですから。
だから、母を見ていて思います。そういう生き方もあるよね、と。母の人生ですからね。私がとやかく言うことではない。それでいいと思っています。
横並び そんな人生 つまらない
精神医学的には、母の生き方はストレスが少ないと思います。
やはり低ストレスが「元気で長生き」につながっていることは、間違いありません。我慢すると免疫力も落ちるし、意欲もわきませんからね。アクティブさが失われたら、体力も落ち、老化が進むのは当たり前なのです。
その点では、母はアクティブですね。活発ではないのですが、心がアクティブなのです。コロナ禍の真っ最中に2回も骨折しましたが、復活しています。
80代で骨折すると、そのまま寝たきりになってしまう人がいますが、母は90代で歩けるようになりました。「介護付きホーム」に移るのが嫌で、リハビリを頑張ったのです。自分のペースで生きたい人ですからね。
母のことを「好き勝手に生きている」と言いましたが、要は「自分のペースで生きる」ということです。そして、これは私にも受け継がれています。
私は子ども時代、今で言う発達障害の傾向がありました。不適応児童だったのです。だから、いつも仲間外れにされます。普通の親なら、子供が仲間外れにされているのを見たら動じるし、「みんなと仲良くしなきゃダメよ」とでも言うでしょう。でも、母はまったく平気なのです。そして、私にこう言います。
「お前は変わっているのだから、何か資格でも取らないと生きていけないよ」と。
人に合わせてまで生きていく必要はない、ということを、私にメッセージとして伝えてくれていたのです。
父は会社員でしたが、出世とは縁遠い人でした。出身大学なども関係していたのかもしれません。母には「父さんみたいにならんためにも、勉強せなあかんで」と言われました。私が東大に入ったのも、母の言葉の影響が大きいと思います。
世間的に見れば、悪い親ですよね(笑)。ですが、結果的に、そのおかげでいまの私があるわけです。大学病院での出世にはまったく興味がなく、精神医学を専攻し、幸齢者に幸せな晩年を過ごしてもらうことを本願にしている。「ダメなものはダメ」と、現代医療への批判も辞さない。だから医学界からは嫌われます。
でも、私としては母譲りのマイペースを嫌ってはいないし、それが自分らしいと思うし、そうやって生きるのが好きなのです。
私はこれまで1000冊近い本を書いてきましたが、母はおそらく一冊も読んでいないと思います。マイペースですからね。「私の息子は○○で」と人に語ることもない。「勝手に生きてくれたらそれでいい」と思っていると思います。
自分らしく生きてくれる母でよかった。そして「人に合わせなくていい」と言ってくれる母でよかった。たぶんこの本も読まないけれど、この場を借りて言います。感謝しています。ありがとう。
出し殻に なってからでは もう遅い
日本人の平均寿命は、男性が81・05歳、女性は87・09歳です(2022年、厚生労働省調べ)。男女差は約6歳です。いまの80代の方は、男社会で生きてきましたし、結婚できる年齢は男性が18歳、女性が16歳(現在は18歳以上)なので、夫婦は「男性のほうが年上」というのが一般的です。
そう考えると、それまでに別れたとしても夫の死後、8~10年くらいは、女性である妻がひとりで生きることになります。
どんなに真面目に夫に尽くしてきても、最後の8~10年はひとりの時期があるわけです。そのときに燃え尽きて、いわゆる“出し殻”になっているのか、それとも、まだまだ輝いている女性でいたいのか?
現実問題として、これはみなさんの身に降りかかってくる選択なのです。
ところが、選択の際には、大きな問題があります。それは“時間”です。
「まだまだ輝きたい」と思っても、すでに輝けない状態になっているかもしれないのです。輝くには70代、あるいは60代から準備を始める必要があるのです。

「出し殻は嫌だ」と思うなら、60代、70代から出し殻にならないように工夫、努力する必要があるのです。