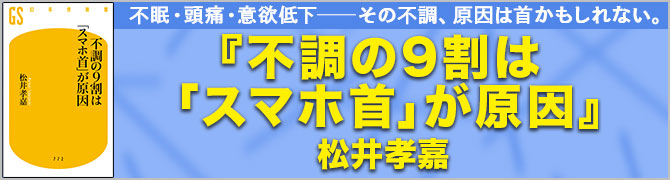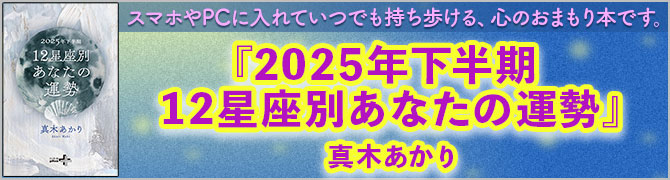みなさん、こんにちは。積水ハウス住生活研究をはじめとする住まいの専門家 河﨑由美子です。今年の夏は、日中の外出をためらうほどの異常な暑さが続きましたね。近年の気候変動により、異常気象や自然災害が増加しているように感じています。「備えあれば憂いなし」というように、もしもの時に身を守る準備や日常の意識をもっと高めたいところ。
さて、9月は防災月間です。今年は関東大震災から100年という節目でもあります。この防災月間をきっかけに、自然災害への防災意識や対策を見直してみませんか。今回は、災害時に自宅の倒壊や浸水などの危険性がない場合にそのまま自宅で生活を送る「在宅避難」についても掘り下げていきます。もしもの時もなるべく普段に近い暮らしを過ごすために、必要なことをご紹介していきます。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
数字から考える幸せわが家の記事をもっと読む
数字から考える幸せわが家

幸せのかたちは、家族やライフスタイルの多様な変化に合わせて変わっていくもの。ほんの少しの知恵や工夫で、わが家がもっと好きになる。積水ハウスの住生活研究から“住めば住むほど幸せ住まい”研究に基づく、暮らしのヒントやエッセンスをご紹介していきます。研究データや意識調査、リアルな実例をもとに「ちょっとやってみようかな」と思ってもらえるコラムを更新しています。
- バックナンバー
-
- 掃除に積極的な男性が18%増加。10年ご...
- 約5割がペットと一緒に眠っている。ペット...
- インテリアにこだわる派は4割。直近で購入...
- すでに始まっている花粉の飛散 外出時のマ...
- 【防災対策】6割が悩む食料ストック 無理...
- 義実家の帰省は4割が「気を遣う」 年末年...
- 45.8%が結婚後の最も大きい変化を食生...
- 「いつもの暮らし」が「もしもの備え」6割...
- 5割が帰宅後にバッグを置きっぱなし? 玄...
- 8割が“家での食事”を楽しみたい。暑い夏...
- 今夏も猛暑予想。節電にもつながる、ひんや...
- あなたはどのタイプ? 4タイプ別インドア...
- 5割以上が悩む梅雨の洗濯物。住まいの風通...
- 「留守にできない」63.6%がペットと暮...
- 睡眠7時間以上の人は五月病になりにくい ...
- “熱中したい”が2023年の個人的欲求1...
- 2人に1人が花粉症の症状あり! 花粉ピー...
- 約7割が感じている心身の不調は「冬バテ」...
- 直近5年で“家事楽”を目的に50.4%が...
- アラサー&アラフォー男性の約4割が関心あ...
- もっと見る