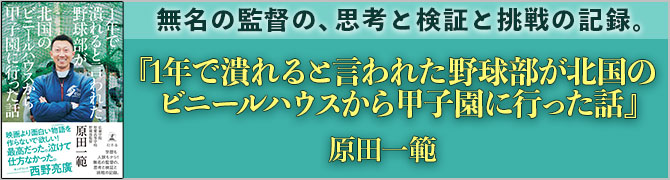2月1日に亡くなられた石原慎太郎氏。哀悼の意を表するとともに、氏が弟で俳優の石原裕次郎氏の生と死を描いた小説『弟』より「時代の恩寵」を抜粋し、3回にわけてお届けします。2回目は、はじめての小説を『文學界』で評価されたあとのこと。

最初の原稿料で買ったのは母親への電気洗濯機
試験も終わりなんとか最終学年に進めるめどがついてから例の雑誌を読み返してみると、悪い気はしなかった。
浅見氏の評を読んで、この俺が注目すべき新人というなら、ひょっとすると俺は小説を書いて生活の出来るような人間になれるのかも知れない、と漠と感じもした。
同じその号に、文学の世界では初めての試みだった新人賞の設置の告知と、すでにその規定にのっとって応募し第一次の予選を通過した、当時は年四本の候補作品の第一回作への評が載っていた。選考者の中にあの伊藤整氏もいて、氏が条件をつけながらもその作品をかなり褒めてい、他の評者も相当に評価している様子なので私は興味にかられて読んでみた。
印象は、なんともつまらぬこんな作品をなんでこんな顔ぶれの人たちがこうも褒めるのだろうかということだった。
そして、こんなものと比べるなら俺の方がまだ面白いものが書けるに違いないと、不遜といえば不遜な、結果については思いを馳せもしなかったが、少なくともこれには勝てるなというやや絶対的な、しかし決して高ぶったものでもない自信が兆してきた。
ならば何を書くかという段になって、ごくスムーズに最初の作品の中に織り込んだ挿話の一つで、弟からある仲間の噂として聞かされた時、いわばそのえげつなさに感心した話があったので、それを基に据えて若い二人の男と女の逆説的な愛の話を書いてみようと思った。
私はその頃フランスの思想、特に文芸思想に関するゼミナールで背伸びしてジュネとかサドを持ち出したりしていたので、インモラルという人間にとってはいわば永遠の主題を、現代のアンファン・テリブルにかぶせて書いたら大人たちは少しはどきりとするだろうと思った。
書き出してみると前作よりはずっと簡単で二晩で書き終え、左ぎっちょゆえ自ら認じる悪筆なので、校正を兼ねてゆっくり念入りに三日もかかって清書した。
加えて小手先の作戦として、どうせ沢山集まる投稿原稿を、手分けしたとしても編集者たちがそう真面目に読む訳はなかろうから、出だしの外連(けれん)で相手の目を引きつけるためにボーヴォワールのサドの評論の中から都合のよさそうな文句を抜き出してエピグラフとして付けておいた。
郵便局まで自転車に乗っていって分厚い原稿を投函する時、さてこれでどうなることやらという気分だけでなんの高ぶりもなかった。私が応募したのは第二回目の候補作品としてで、結果は二月ほど先の雑誌に載るはずだった。
運動部の合宿やその他この他で春休みもあっという間に過ぎてまた新学期が始まり、その段になるともうその年限りの大学生活にし残したことばかりが目について気が落ち着かず、自分はもう来年からは社会へ出て暮らすのだという、自覚どころか意識もほとんどないということに不本意というか心もとないというか、そのくせまあどうにかなるだろうというただ気休めばかりをしていた。
そんな頃突然家に電報があり、発信元は文藝春秋の『文學界』編集部だが、文面はなにやら相談したいことがあるので至急来社願いたいということだった。
私は、以前に出したあの原稿のことだな、あれが当選したらしいなとは思ったが、それならそういってくれればいいのに、相談とはどういうことなのだろうかと思った。私が決して世の文学青年でなかった証拠に私はそれをそのまま自分の都合で解釈し、あの世界の彼等は多分こういう表現で人を呼びつけて当選採用を告げるのだろうと思って疑わなかった。
別に演出を考えた訳でもないが学生服よりはその方が良かろうと思い、その日は紺のブレイザーコートを着て、学校の帰りに当時は銀座のみゆき通りにあった文藝春秋の本社に出向いていった。
後に聞けばあの作品の作者がくるというので、編集部のスタッフは私が幾つくらいの年配かいろいろ推測していたそうだ。大方の者はごく若い人物だろうといっていたらしいが、ある人は使っている漢字が古めかしいからかなりの年配者かもといい、ある人は、こちらはわざわざ時間かけて清書したのに、原稿の字の醜さからしてとんでもなく若い人間だろうといってもいたそうだ。
当時の編集長の尾関氏と会ったが、相手の相談とは、冒頭につけてあるあのエピグラフはあまり内容に関係ないので外したらどうかという意見がある、特に武田泰淳氏がそういっているがということだった。私は心中密かに作戦の効果はあったようだなと思ったが、顔には出さず、一応首を傾げ、
「そうですかねえ、関係ないことはありませんが、でも、是非といわれるならとっても結構です。あれがあると当選にはならないのですか」
真顔のつもりで聞いてみたら尾関氏が笑って、
「いや、そういうことはありませんが、私も外した方がいいのじゃないかと思うなあ」
といったので、確かめるべきものは確かめたと思い、
「いいですよ。ならば外して下さい。でも当選は当選なんでしょう」
尋ねたら相手も頷いてくれた。
間もなく出版された雑誌の私の作品に添えられたキャプションは『ついに現れた戦後の青春像』という大仰なものだったが、私は私なりに心中、「なるほどここまでは思った通りにきたな」という感じでいた。
なによりの満足は一枚あたり四百円の原稿料が払われたことで、これは当時の私にとっては労に比べてかなり効率のいい収入だった。
大学時代、高校の時の担任教師の紹介で英語の家庭教師を二軒引き受けていたが、それはやや学生としての良心の証しのようなところがあって、片方では誰かから知恵を仕入れて、ダンスパーティが盛んになりかけていた当時、新橋のダンスホール『フロリダ』を昼間借りて弟と組んで有名無実の学生クラブを作り、頭が堅く融通の利かぬ東大生を雇って受付をさせ、税務署の方はそんな興行にいちいち目を配る暇もなかったろうが、そうした集まりを狙って必ずやってくるM大系の菊水会など学生やくざの対策に当てて、結果としては実費を差し引いてその度に三、四万の収入にはなっていた。
それを弟と山分けしたのだが、それに比べれば一人だけの労ですむ原稿料というのは、なにしろ大学出の初任給が一万三、四千円の頃だから結構な実入りではあった。
いんちき学生クラブ主催のダンスパーティでのアルバイトといえばもう一つ思い出すことがある。
弟と組んで数度やった最初の折に、実質主催者の片割れの弟がいつになっても会場にやってこない。私もただ客の顔をして会場にきてはいるがなんとも心もとない。
弟は終り近くになってやっと現れ、聞けば前夜悪友と新宿二丁目の遊廓に登楼したら、連れが約束した相手の女がやってこずに女将に文句をつけての狼藉となり、それに手を貸した弟も一緒に警察に泊められての遅参だった。
事件は尾を引いて、弟は母親まで呼び出されて職員会議にかけられなんとか譴責(けんせき)ですんだが、相棒の方は会議の席で咎められたら、先生たちだって同じ所に出入りしているじゃないですかと居直ってしまい、同じ町でいつか見かけた教師たちの名前を口にしてそのまま退学になった。
もっともその男は父親には在学し通したと嘘をついて、卒業の年には同じ印刷屋で卒業証書を偽造して父に渡し、親をいたく感動させてそのまま父親の会社を継いでしまい、今では会社をますます繁盛させてもいる。いかにもあの時代ならではの挿話だった。
最初の原稿料を手にしてまずしたのは、弟に気兼ねせずに着られる私専用の背広を仕立てたことと、気障に聞こえるが母親へのせめてもの親孝行として、なによりも先に電気洗濯機を買ったことだった。
日頃私たち二人だけではなく、夏だけではなし春にも秋にも、二人とも勝手に友達を連れてきては家に泊め、その汚れものをもう女中のいなくなった家で母親に洗わせていた。その量は並大抵のものではなく、当時普通の家での洗濯といえば、大きな盥(たらい)に洗濯板を置き手の荒れる洗濯石鹸で洗う、大層手のかかる作業だった。
それを承知していながら私も弟も、自分一人の時には殊勝に自分で洗ったりすることもあったが、仲間がくるとそれと一緒に自分の分も山と積んで出して、陰で申し訳なさに手を合わせてもいた。風呂場にしゃがんで、つい以前は女中のしていた洗濯を自らしている母親の後ろ姿だけには気が咎め気持ちもめいった。
家の近くの電器屋に注文した電気洗濯機が到来したら母が久し振りに心から笑って私に感謝してくれ、私は生まれて初めて親孝行の実感を味合えた。
後になって母に、テレビより車よりなによりもあの電気洗濯機が家にきた時、父の生前にはまだなかった機械ゆえにも、
「ああ、この子は死んだ主人よりも大層なことをしてくれると思ったわ」
などといわれて、私としては父が死んだ後あの頃までの我が家の財政の超低空飛行を思い起こし、自分の幸運に改めてぞっとしない訳にいかなかった。
それもあの浅見氏の評の載った一冊の雑誌からということなら、あれに載っていた募集広告に応募して書いた小説のお蔭というなら、さらにそれに活用した弟の放蕩経験の所産ともいえる悪い仲間たちの挿話のお蔭というならば、結果としては、弟の放埒には見事な再生産性があったということにはなる。といっても、後になっても私や母が改めて弟のあの頃の放埒に感謝したなどということは決してない。
第二作の載った雑誌を見せた時、弟がなんといったか覚えていない。その頃の時点ではまだ反響は少ないものだったし、評価も定まらぬ兄貴の書いた小説の内容なんぞ自分からの聞き語りの域を出ぬ印象でしかなかったろう。
しかし、弟がその雑誌を手にしてひどく興味深げに、読み出す前にも何度も全体の頁をめくり直しながらしげしげと眺めいっていたのを覚えている。それを見て私は自分の悪戯を打ち明けてしまったような面映ゆさでその場を離れてしまったものだ。
作品の評として彼から何を聞かされたということもなかった。それでも弟は悪い仲間たちとの遊びの間に、俺たちがやってることを兄貴が小説にしたてて、それが懸賞の候補になっているというようなことをいっていたようだ。
もっともそれ以来ずうっと、弟は私の新刊が出るのを周りには大層自慢にしていたようだ。だから新しい著書の弟への献本が遅れていると、必ず電話がかかり、買うのは易いが必ず至急に届けさせろといってきた。
いずれにせよ『文學界』の懸賞に応募し当選した小説のお蔭で、私たちの運命が開けたことには間違いない。今になって思えば思うほど、あれは天のもたらした幸運というよりない。もしあれがなかったなら、私たちは弟の放埒の巻き添えで間もなく破産していたろう。
後になってあの頃を振り返り私が背筋を寒くすると、母がもっともらしく、
「ちゃんとお父さんがついていて下さったんだよ」
とはいったが、私としてはもっとそれ以上の何かが我々を看取っていてくれただろうことを疑わない。