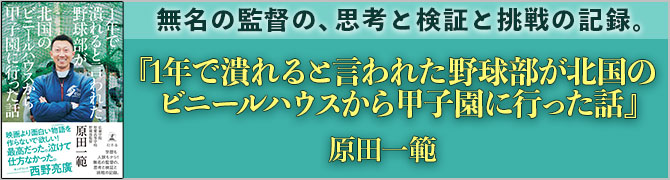4度の自殺未遂、その後は精神科病院に入院したり、デイケアに通ったり、生活保護を受けたりと、紆余曲折の人生を送ってきた小林エリコさん。
強い希死念慮に苛まれながらも、ここまで生き延びてこられたのはなぜか。出会ってきた人たちとのやりとりを振り返り、「生きること」の意味を考え直したエッセイ『私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに』が11月10日に発売になります。
本書の一部をお届けいたします。

初恋は人を狂わせる
私が小学六年生の時、峰田君というクラスメイトがいた。峰田君は勉強が飛び抜けてできて、運動神経も抜群で、顔つきも精悍で、こんな茨城の田舎の学校にいるのがおかしいような子だった。
峰田君は当たり前のように、学級委員長に推薦されて、名札の上には委員長のバッジをピカピカと光らせていた。峰田君が少しふざければ、クラス中どっと笑いの渦に巻き込まれ、授業中なのに先生ですら笑っていた。いつもクラスの中心にいて、峰田君の周りには人が集まり、そこだけ光が当たっているかのようだった。
その頃の私は、クラスでいじめに遭っていた。当時、兄と一緒にお風呂に入っていたのだが、勝手に体を触られたり、兄の性器を押し付けられたのがきっかけで、お風呂には一ヶ月に一度くらいしか入らなくなっていた。そのため、肩の上には常にフケが積もり、クラスメイトの嘲笑のネタになっていた。休み時間は誰とも話すことなく、机に向かって黙々と絵を描いていた。
大きな眼鏡をかけて、俯いていつも一人で過ごしている私は、人気者の峰田君のことが気になっていた。そして、それは私だけじゃなくて、多分、クラスの女子のほとんどが、同じだった。時々、クラスの女子が校庭でドッジボールをしている峰田君を見ながらキャアキャア騒いでいたし、色っぽい噂話にも登場した。私はその中に入ることすらできない、ドブのような人間だった。
授業中、峰田君が肘を机について、肩のあたりに手をやっていた。それを見た先生が、手を挙げていると勘違いし「峰田君」と指した。峰田君は、ふふっと笑って「違いますよ、先生。ちょっと肘をついていただけで、手を挙げたんじゃないです」と堂々と答えた。すると、クラス中が笑いに包まれて、先生は恥ずかしそうに頭を掻いた。「紛らわしいことするなよ。まったく」そう言った先生の顔は少しも怒っていなかった。

それから、しばらくの間、峰田君の真似をするのが流行った。授業中に肘を机に置いて、手を挙げているフリをする子が何名か現れた。先生はそれを見て「峰田君の真似、しないように」と軽く注意をした。私もそれとなく、肘を机につけて、先生が注意してくれるのを待っていたけれど、注意されることはなかった。
ある日、漫画のコピーを下敷きに入れている私に向かって、クラスの男子がこう言ってきた。
「それって、違法なんじゃねえの? 漫画を勝手にコピーするのって、ダメだろ」
それが違法かどうか、子供の私にはわからなくて、黙り込んだ。彼は私のことが嫌いだから、そういうことを言ってくるのだろう。多分、同じことを峰田君がやっていたら、何も言わない。もちろん、峰田君が私のようなオタク趣味丸出しのことをやるはずもないが。
その男子は、私のやっていることが相当気に入らなかったらしく、わざわざ先生に告げ口した。先生は「それは別に違法じゃない」とはっきり言った。すごすごと帰ってくる男子の姿を見て、私は本当に嫌われているのだとわかった。
生まれて初めての「好き」という気持ち
図工室で、絵を描いている時、峰田君と近くの席になった。私はドキドキしながら絵を描いた。峰田君は優等生なので、勉強も運動もできる上に、絵も上手だった。峰田君の肌は日に焼けていて浅黒く、目は大きくパッチリとしていて、眉毛は太く凜々しい。どうして、こんな完璧な生き物がこの空間にいるのだろう。私は近くにいる峰田君をチラチラ見ながら2Bの鉛筆をせわしなく動かした。
峰田君を前にすると、私は心臓がドキドキして、落ち着かなくなる。私はきっと、峰田君のことが好きなのだろう。そして、それは絶対に誰にも知られてはいけない秘密だった。私のような最下層の人間が、クラスの頂点に立つ峰田君を好きだなんてことがバレたら、学校に行くことができなくなるのは目に見えていた。
私は下描きを終え、絵の具を出して、着色に入った。肌色を作るのに、茶色の絵の具と、白の絵の具、それに赤い絵の具を少し出した。黄色の絵の具も出そうとしたのだが、蓋の周りの絵の具が乾いて固まっていて、開けようとしてもどうしても開かない。パレットには指を入れる穴の他に絵の具の蓋が開かなくなった時のための穴が空いている。その穴に蓋の部分を差し込んで本体をくるっと回すと軽い力で開けられるようになっているのだ。

しかし、私のパレットでそれを試しても、なぜかうまく開かない。困った私は散々悩んで、隣にいる男子に「パレットの穴の部分、貸してもらえる? 私の絵の具、開かなくて……」とお願いした。隣の子は一言「ヤダ」と言ってプイッとそっぽを向いた。私が肩を落としていると、峰田君が口を開いた。
「それくらい貸してやれよ」
その瞬間、時が止まったような気がした。私みたいないじめられっ子をかばうのが信じられなかった。しかし、きっとそれが、彼が人気者である理由なのだ。その子は峰田君に言われても、私にパレットを貸してくれなかった。そうしたら峰田君は「僕のを使いなよ」と言って自分のパレットを差し出した。私は恐る恐る彼のパレットの穴に自分の絵の具の蓋をねじ込んだ。蓋はすんなり開いた。私はお礼を言って、そのまま絵を描いた。
絵の具事件があってから、私は峰田君に嫌われていないということがわかって、頭の中がずいぶん沸き立っていた。もしかしたら峰田君は私のことを好きかもしれないと考えたが、直後にそんなわけはないと否定した。同じ道を行ったり来たりするように、峰田君のことを毎日考えていた。
ある日、少女漫画雑誌についていたおまじないの本を読み直している時、好きな人の名前をシャーペンの芯一本分、書くことができたら両思いになるというものを見つけた。幼い私は、新しい芯を一本取り出して、慎重にシャーペンに入れると、ノートを開いて峰田君の名前を書き始めた。
峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登、峰田登……
私は右手の痛みをこらえながら、峰田君の名前をノートに書いた。峰田君が好きだということは、誰にも言っていなかった。しかし、ある日、兄と二人きりで話している時に聞かれた。
「エリコ、お前好きなやつ、いねえの?」
私はいないと答えたが、兄はしつこく聞いてくる。兄は中学生になっていて、モテる部類の人間だった。デートに行った時の写真を見せて自慢してくるので、悔しくなって、つい、言ってしまった。
「峰田登って人が好き」
兄はそれを聞いて、顔を歪ませて、ゲラゲラ笑った。私のような人間に好きな人がいるのが面白いのだろう。
「小林エリコの好きな人は峰田登! 小林エリコの好きな人は峰田登!」
ベランダの窓を開けて、大声で外に向かって兄は叫んだ。夜の団地に私の名前と峰田君の名前がこだまする。私は兄を制して急いで窓を閉めた。
「今のは嘘! 適当に言ったの!」
私は顔を真っ赤にして怒った。兄はひしゃげた笑い顔をしたまま、バカにしたような目で私を見た。私は自分の部屋に戻って、布団を被った。恥ずかしくて死んでしまいたかった。
積もりに積もった思い
年末になり、私は郵便局に年賀はがきを買いに行った。一年の終わりの大仕事は年賀状を書くことだった。絵を描くのが好きな私にとって、年賀状を書くのはとても嬉しいことだ。得意のイラストを堂々と描いて、人に送ることができるのはこの時くらいしかない。しかし、私は年賀状を出す相手がとても少ない。父方の祖母と叔母。母方の祖父母。それと数人の友達だけで、全部合わせても十枚いかない。それでも、干支のイラストを何回も練習して、年賀状に下描きをした。

駅前の画材屋さんで購入した漫画家が使うGペンを握りしめて、ペン先をインク壺に落とし、ゆっくりとペンを入れる。インクが乾いたら丁寧に下描きを消しゴムで消して、色鉛筆で色を塗って仕上げた。残った余白に書くメッセージを何にしようか、頬杖をつきながら考える。「お餅の食べすぎに注意!」というのは、使いすぎてしまったので、それ以外の言葉を考えて、書き込んだ。宛名を書き終えると、トントンとはがきを揃えて机の上に置いた。そして、悩んでいる問題を考え始めた。
実は、峰田君に年賀状を出そうかと考えていたのだ。ひとしきり悩んだのち、私はとりあえず、書くだけ書こうと思い、他の年賀状と同じレイアウトとイラストで書き始めた。
出来上がったあと、右端の隅っこに小さな文字で「好きです」と鉛筆で書いた。流石にそれはダメだと思いとどまり、消しゴムで消した。しかし、しばらく経って、また「好きです」と鉛筆で書いた。そして、また消した。何回も「好きです」と書いては消してを繰り返し、私は頭を抱えた。私はどうしようもなく峰田君が好きなのだ。
しかし、それは私だけが抱いている感情ではない。あのクラスでなくても、学年中の女子が峰田君を知っていて、みんな好感を持っている。峰田君に告白をされて断る女子はいないと思われるくらい、みんなの憧れの的だった。みんなが峰田君を好きなら、私だって好きになってもおかしくない。それくらい素敵な存在なのだ。
私の脳裏には、図工室で、私の隣の男子に「それくらい貸してやれよ」と男らしく発言した峰田君の顔が焼き付いていた。そして、嫌がることもなくパレットを差し出した姿が思い出された。私は年賀状の「好きです」の文字を消した後、学校の連絡網を取り出して、峰田君の住所を表面に書いた。「好きです」の文字は消したけれど、何回も書き直したので、跡がくっきりと残っていた。大きさにしたら一センチにも満たない小さな「好きです」の文字の跡を残したまま、私はありったけの勇気を出して峰田君宛の年賀状をポストに投函した。
そして事件は起こった
年が明けて、ポストに向かう。相変わらず、私宛の年賀状は少ない。峰田君は私の年賀状を受け取っただろうか。ふと、とんでもないことをしてしまったのではないかと思い、激しく後悔した。やっぱり出さなければよかった。親しくもない私から年賀状をもらって、嬉しいわけがない。しかも、隅っこには「好きです」の文字がうっすら刻まれているのだ。でも、峰田君なら、私からの年賀状をなかったことにしてくれるかもしれない。いじめられっ子の私にも優しいのだから、私がしたバカなことを放っておいてくれるだろう。彼はそれほどの人格者だと信じていた。
冬休みが明けて、新学期になり、いつものように教室に入った。その瞬間、ざわついていた教室が水を打ったように静かになった。みんなが私を見ていた。そして、峰田君が気まずそうな顔をして、仲の良いクラスメイトに耳打ちをしていた。
私はその瞬間、全てを悟った。峰田君は私から年賀状が来たことを、クラスメイトに話したのだ。私は恥ずかしくて生きた心地がしなかった。いつもは「バイキン」などと言って囃はやし立ててくるクラスメイトも、何故かやってこない。私は冷たい視線を一身に受けながら、できるだけ平静を装って、席につき、意味もなく教科書をめくった。早く家に帰りたくて仕方がなかった。
峰田君のことが好きだとクラスメイトにバレたら、学校に来られなくなると思ったけど、そんなことはなかった。私は嫌だったけど、学校に行った。逆に学校に行かなくなる方が年賀状を峰田君に出したことを印象付ける気がしたからだ。
私は何もなかったかのように学校へ行き、普通に授業を受け、終わったらまっすぐに家に帰った。心を石のようにして、何も感じないように、考えないように、沈黙を保った。
冬が終わり、春の足音が近づいてきた頃、クラスメイトの興味は卒業式に向かっていき、その準備で忙しくなると、彼らの冷ややかな視線は消えていった。
卒業式を迎え、クラス全員に卒業アルバムが配られた。集合写真の峰田君はまっすぐ前を向いていて、クラスの男子の中で一番かっこよかった。でも、私の中には、好きだという甘酸っぱい気持ちは、もうなくなっていた。
クラスの女子が峰田君の噂をしていた。彼はみんなが行く公立の中学でなく、入るのがとても難しい遠くの私立中学へ進学するという。うちの小学校からは峰田君しかそこへ行かない。飛び抜けて頭が良かったから当然だろう。私はもう二度と顔を合わせることがないと思うと、心底ホッとした。
大人になってから一度、峰田君の名前を検索したことがある。会社社長か、偉い官僚にでもなっているかと思ったのだが、どこにも名前は出てこなかった。峰田君はあの学校では一番だったけれど、広いこの社会では、一番ではなかった。それでも、やっぱりあの時あの場所で峰田君は一番かっこよくて輝いていた。
私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに

「孤独だったんですね」
その言葉を耳にして、私は喉の奥に何かが詰まり、次の言葉をつなげなくなった。自分が孤独だということは薄々感じていたけれど、それを認めたくなかったのだ――
いじめに遭っていた子供の頃、ペットのインコが友達だった。初めてできた恋人には、酷い扱いを受けた。たくさんの傷を負い、何度も死のうとしたけれど、死ねなかった。そんな私をここまで生かし続けたものは何だったのか。この世界には、まだ光り輝く何かが眠っているのかもしれない。そう思えた時、一歩ずつ歩き出すことができた。
どん底を味わった著者が、人生で出会った人たちとの交流を見つめなおし、再生していく過程を描いた渾身のエッセイ。
「人生はクソだ。それでも生きてさえいれば、いつか必ず美しいものに巡り合う。そういうふうに、できている」――はるな檸檬氏 絶賛!