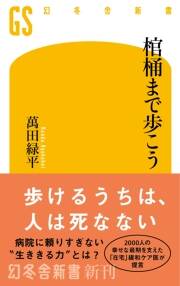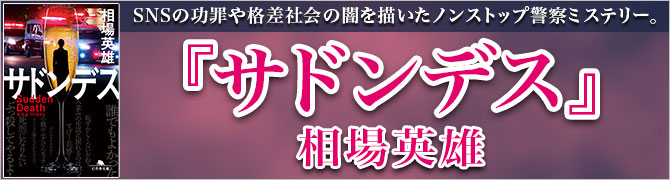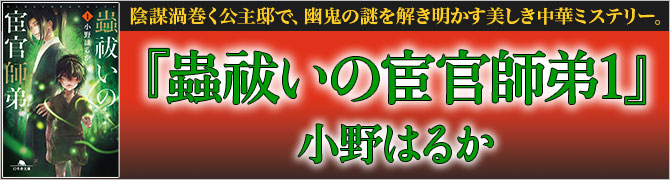不健康寿命が延び、ムダな延命治療によってつらく苦しい最期を迎えることへの恐怖が広がる今、「長生きしたくない」と口にする人が増えています。先行き不透明な超高齢化社会において、大きな支えとなるのが、元外科医で2000人以上を看取ってきた緩和ケア医・萬田緑平先生の最新刊『棺桶まで歩こう』です。
家で、自分らしく最期を迎えるために、何を選び、何を手放すべきか。本書から、一部をご紹介します。
* * *
入院していると「好きに生きられない」から、つらいのです
入院している患者は、どうしてそんなにつらいのでしょうか。
まずは、本人が好きに生きられないからつらいのです。もちろん治療したい人は、いくら苦しくても死ぬまで治療すればいい。でも「もう家に帰りたい」という患者さんは、確実にいるわけです。
がんと診断される前から在宅を望む人もいれば、診断されてから希望する人もいます。しばらくがんの治療をしてからという人もいるし、何回も入院してあとは死ぬのを待つだけだとなってから「家に帰りたい」という人もいます。
いずれにしても、途中で治療をやめて家に帰りたいと望んでも、家族が「いいよ」と理解してくれるケースはほんのわずかです。これまでの僕の経験では「帰りたい」と望んだ患者さんの1割以下だと思います。
ほとんどの患者の家族は、こう言うのです。
「あきらめるんじゃない。がんばれ」
「可能性があるなら治療しよう。あきらめるなんておかしい」
「家に帰りたいなんて、そんなわがまま言ってはダメ」
患者には、家に帰る自由もありません。要するに、好きなように生きられないのがつらいのです。
当然ながら、萬田診療所には、家族が「いいよ」と言ってくれた人しか来ません。この時点ですでに「つらくないコース」なのです。僕が患者を「つらくなくする」のではなく、家族が了解してうちに来た時点で、もう「つらくないコース」。
がんの治療医は、がんを小さくするのが専門ですから、がんの大きさと腫瘍マーカーばかり見ています。だからがんを小さくするための抗がん剤治療をしますが、患者にとっては副作用が苦しくつらいのです。
一般的ながんの治療医は、がんの大きさで余命を決めますし、がんが大きくなったら死んで、大きくならなければ死なずに済むと思っています。
僕の診療所にも、「抗がん剤をやめたら死んじゃう。あとは死ぬのを待つだけ」というイメージで来る方が多い。そんなことはありません。
そう思い込んでいる患者には、「死ぬのを待つなんてダメだよ。まだまだやることあるんだよ!」という話をします。

もっと生きたいよね? じゃあ歩きましょう
人はがんが大きくなって死ぬのではなく、老いて、弱って死ぬのです。と、僕は考えています。
人は必ず老化していきます。言ってみれば、下り坂です。どんなにいいものを食べても、いくら健康にいいことをしても、上がっていくことはありません。若返ることなど絶対にないのです。仮にタイムマシンがあったとしても、若返りはできません。
人は弱っていって死ぬのです。がんになるから死ぬ、病気になるから死ぬのではなく、弱っていって死ぬ。
がんが大きくなっても、生きていられる人もたくさんいます。僕の患者さんにも外からもわかるくらいがんが大きくなって、体重が25キロになっても歩いている方がいます。
いずれはつらくなってきたり、むくんできたり、しんどくなってきて、歩けなくなる、がんばれなくなるときが必ずくるでしょう。
進行すれば、抗がん剤をどの時点かでやめるのですが、医師によっては「あきらめた」ととられるのがいやだから、患者が死ぬまでやめない人もいます。結果死ぬまで、患者さん本人がしんどい思いをするわけです。
では抗がん剤を使い続けるのと、やめた場合とではどちらが長く生きられるのか。僕は、やめた方が長く生きられると考えています。ただ、抗がん剤をやめたとして「あきらめて死ぬのを待つだけ」では、患者さんにとっては楽しくない。恐怖の時間です。
ならばその時間を楽しい時間にするのが、僕のやり方、萬田道場だと思っています。
「そんなんじゃ死んじゃうよ。いいの? 好きにすればいいんですよ。死にたくないならやり方教えます。でも、やるかどうかはあなたしだいですよ」
1がんばりたい人には1、教えます。10がんばりたい人には10、教えます。1しかがんばれない人に、10教えてもかわいそうだからです。
そして家族にはこう伝えます。「心は上げられるんだよ。俺には上げられないけど、家族には上げられる」
病院では多くの人が、「がんばれがんばれ、そんなんじゃダメだ」と言われ続けて死んでいきます。心の状態が下がっていき、死んでいきます。
そうではなく、「ほめてあげよう」と。「ありがとう、あの時は楽しかった」と声をかけてあげよう。そうすると、ほとんどの人は「いい人生だった」と口にします。
そして、「いい人生だった」と思えれば、次に「もう少し生きたい」という言葉が出てきます。
そこからが僕の出番。患者さんにこう言います。
「もっと生きたい? じゃあ、立ち上がろう、棺桶に入るまで歩こうよ」

人の寿命は歩幅と背筋でわかります
もう一度言います。人は歩けているうちは、死にません。歩けるというのは、がんばれるということ。がんばれるうちは人は死にません。なぜなら、がんばれるというのは脳の若さだからです。ですから歩く速さや歩幅を見れば、ほぼその人の寿命がわかります。
スタスタと歩ける方は、おおむね10年以上生きられるでしょう。イスから腕の力を使わずに立ち上がれる人なら、余命1年以上。立ち上がれない人は余命半年以内。ちょこちょことしか歩けない方は余命数カ月、歩けない人は余命1カ月以内、というお話はすでにしました。
では、歩けるためには何が大事なのか。一言で言えば、「体幹の持久力」だと僕は考えています。
僕はよく、「心がではなく、医学的に、科学的に『疲れた』ってどういうことでしょう?」と問いかけます。
髪の毛が抜けた、口が乾く、指が痺れた……、それはいわゆる「疲れた」とは違います。
人間は「ああ疲れた」となると、バッタンキュー。そう、寝転びたい。立っていられないはずなのです。
「疲れた」とは自分の体をささえていられない状況。すなわち体幹の持久力が限界にきた状態です。
背筋を伸ばして、背もたれに寄りかからず座ってみてください。これは、体幹の持久力があるからできる姿勢です。持久力ですから、マラソンの選手と一緒で細い筋肉があればいいのです。太いむきむきの筋肉は要りません。
体幹の持久力があれば、どんなに痩せても歩くことができます。僕たちは、ふだん何かに寄りかかりながら歩く、ということはありえません。「はじめに」で紹介した体重25キロでも歩ける人も、背筋はピシッとしているのです。
茶道、華道、書道など、さまざまな「道」の先生は背筋を伸ばして長時間座っている姿勢があたりまえになっています。体幹の持久力がある人はなかなか疲れませんから、「道」の先生たちはよほどでないと疲れたとは言いません。
30分間、背筋を伸ばして座っていられる人は、30分歩けます。3分しか背筋を伸ばして座っていられない人は、3分しか歩けません。
「食べられないから歩けない」と嘆く人が多いけれど、点滴で栄養を入れているから永久に歩けるわけではない。筋肉だけで歩いているわけでもない。
* * *
最期まで自分らしく生きたい方、また“親のこれから”を考えたい方は、幻冬舎新書『棺桶まで歩こう』をお読みください。
棺桶まで歩こうの記事をもっと読む
棺桶まで歩こう
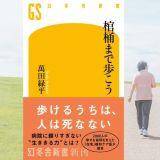
体力も気力も衰えを感じる高齢期。「長生きしたくない」と口にする人が増えています。
不健康寿命が延び、ムダな延命治療によって、つらく苦しい最期を迎えることへの恐怖が広がっているからです。そんな“老いの不安”に真正面から応えるのが、元外科医で2000人以上を看取ってきた緩和ケア医・萬田緑平先生の最新刊『棺桶まで歩こう』です。
家で、自分らしく最期を迎えるために――いま何を選び、何を手放すべきか。
本書から、一部をご紹介します。