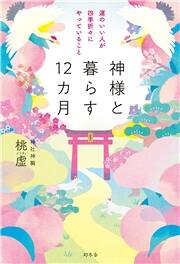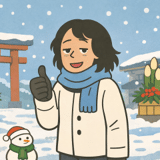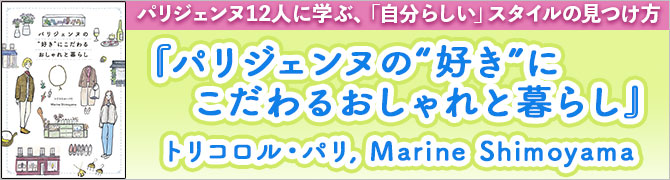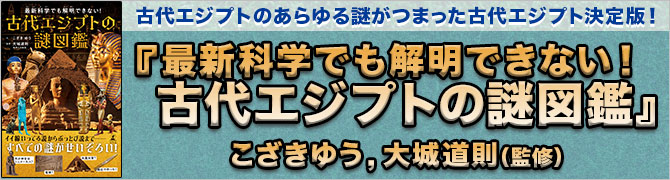五感を研ぎ澄ませば、もっと充たされる。そんな事象が多いのが10月です。残暑でぐだぐだしていた五感が、秋に向かって、ぱあっと開くのを感じましょう!
神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。
* * *
虫の音を楽しむ日本の風習は、世界的にも珍しい!
私の住んでいる大阪は、秋になっても気温が高く、夏の延長戦、といった感じが否めません。そんな折、東北地方の山あいに住んでいる友人と、夜に電話で話しておりましたら、鈴虫の声が聞こえてきて、その瞬間、「秋がきた」と思いました。
残暑でぐだぐだしていた五感が、秋に向かって、ぱあっと開いた心地がしたのです。
鈴虫の声の周波数3500~4500ヘルツは、通信規格3Gの回線を使っていたころには切り捨てられていたので、携帯電話やスマホでは聞こえなかったそうです。ところが今は、通信速度も、一度に送ることのできるデータ容量も、再生するアプリケーションの性能も格段に上がったので、50~1万4400ヘルツの周波数をやりとりできるようになっています。

それにしても、電話の向こうの鈴虫の声だけで、秋の訪れを感じ、懐かしいひんやりとした空気の感触まで思い出す……というのは、いったいどういうことなのでしょう? ふと、私の子どもたち(ふたご)が1歳のころに、保育園の若い先生から言われたことを思い出しました。
「お子さんと一緒に外に出て、お花が咲いていたら、きれいだね、と声をかけてあげてくださいね。そうすることで、お花がきれいだな、という感情が育ちますからね」
ひょっとしたら、保育の世界では常識なのかもしれませんが、そのときの私は、この言葉にたいへん胸を打たれました。たしかに、「きれい」という感情は、見ている対象と「きれい」という言葉がつながったときに、はじめて認識されるのではないか? と思ったからです。
以来私は、お散歩のたびに、花や木や草、昆虫やカナヘビ、夕焼けやいわし雲にいたるまで、見つけたら子どもに「きれいだね」「可愛いね」「おもしろいね」と言い続けてきました。何らかの感情が生まれたとき、それを言葉でなぞることによって、その感情と対象物がきちんとつながって強化される気がしたのです。
自然界の「音」に対しても同じことが言えるのではないでしょうか?
日本語は、オノマトペ(擬音語、擬態語、擬声語)がとても多い言語と言われますよね。秋の虫で言うなら、
アオマツムシが、りー、りー、りー/マツムシが、ちんちろりん/クサヒバリが、ふぃりりり/カンタンが、るるるるる/キリギリスは、ちょん、ぎーす/コオロギは、ころころりーりー/スズムシは、りりーん、りりーん。などなど。
虫が翅(はね)をこすって出す「音」をオノマトペで言語に組み込んで、「秋だね」「いいねぇ」「風情があるねえ」「わびてるね」「さびてるね」と祝言(ことほ)ぎ続けた結果、虫の声を聞く「虫聞き」という文化が日本に定着したのではないかと思います。
虫の声を聞いて「秋だね」と言って楽しむ大人に囲まれて育った私は、電話口のむこうにいる鈴虫の声を聞くだけで、「秋」という季節を自分に引き寄せることができたのでしょうね。
虫の声を処理するのは右脳?左脳?――日本語を話す人は「言語を処理する=左脳」、欧米の言語を話す人は「音楽を処理する=右脳」で
ところで、虫の声を楽しむ「虫聞き」の趣味は、日本では古くからありますが、世界的にはめずらしいそうです。そして、それは日本人の脳の使いかたに関係しているという説があります。
医学博士の角田忠信さんの研究によると、
・日本語を母国語として話す人の脳は、「虫の鳴き声」を、「日本語の音声範疇」と同じ領域(脳の左半球)で受け止めていて、
・欧米人は、言語以外の音を受け止める領域(脳の右半球)で処理している
と言います。
おおざっぱに言うと、
・日本語を話す人は、虫の声を、「言語を処理するのと同じ左脳」で処理していて、
・欧米の言語を話す人は、「音楽を処理するのと同じ右脳」で処理している、
ということです。
虫だけでなく、鳥など他の動物の鳴き声、波、風、雨の音、小川のせせらぎ、邦楽器の音も日本人は左脳で処理していて、「音楽」については西洋人と同様に右脳で処理しているそうです。
うーん。「虫が翅をこすり合わせて出す音を、言語として聞く」というのは、どういうことなのでしょうか。べつに音楽として右脳で処理したっていいじゃないか。謎です。
実際、虫の出す音は、「メスへの求愛」「なわばりの確認」「オス同士のあらそい」などのコミュニケーション手段である、と考えられているので、それを「言語」と呼ぶこともできます。
でもそれは、虫同士の言語。人間が聞く場合は、欧米人のように「ふつうに音として聞く(または聞かない)」のでよかろう、と思います。
日本人が「虫の声」を言語として聞いている、ということは、「自分にとって何かしらの意味がある」「自分が話しかけられている」と感じて聞いている、ということではないでしょうか? 音には意味がないですが、言葉には意味がありますから。
でも、虫の声の意味って……???
(つづく)
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること
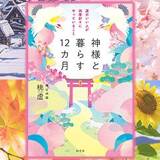
古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!
* * *
神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。
- バックナンバー
-
- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...
- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...
- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...
- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...
- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...
- 神々がしていることを真似すると、運が開く...
- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...
- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...
- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...
- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...
- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...
- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...
- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...
- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...
- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...
- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...
- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...
- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...
- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...
- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...
- もっと見る