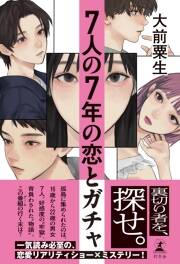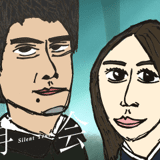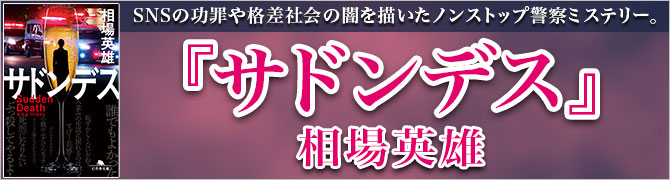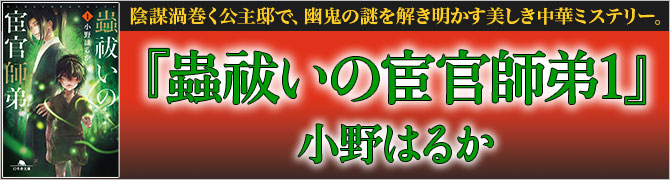大前粟生さんの最新作『7人の7年の恋とガチャ』の刊行を記念して、『死んだ山田と教室』で鮮烈なデビューを果たし、その後も話題作を刊行し続けている作家の金子玲介さんとの対談を行いました。
2016年、大前さんが「彼女をバスタブにいれて燃やす」で「GRANTA JAPAN with 早稲田文学」の公募プロジェクトで最優秀作に選出されたときからお付き合いがあるという二人。前編ではお互いの作品への深いリスペクトを感じた対談でしたが、後編ではさらに今後の作品へのリクエストも飛び出し……。
* * *

恋愛はよくわからないからこそ、脱線できる
金子玲介(以下、金子):大前さんは『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』(以下、『ぬいしゃべ』)で恋愛の加害性、男性の生きづらさを文学の俎上に載せた。男性でフェミニズム文学をやる作家はこれまであまりいなかった印象なんですけど、一切の照れなく、そこを真っ向から書き切った。
『ぬいしゃべ』で扱った「恋愛の加害性」は、たとえば『きみだからさびしい』や『かもめジムの恋愛』など、その後の大前さんの作品群に通底しているなと思うんです。
大前粟生(以下、大前):そうですね。そのなかで、読む人に与えるストレスの度合いを作品ごとにコントロールできたら、という思いがあります。
――今作はストレスの度合いはどれくらいにしようと思いましたか?
大前:100のうち10くらい? 恋愛リアリティショーはそもそも若い人がよく観るものだと思うので、「初めて小説を読みます」みたいな人にでも単純に楽しめるようにしました。
書いてある内容はちょっと怖いかもしれないけど、読書体験としてはさっぱりしたものになっていると思います。
金子:今作が今まででいちばん読みやすいかも。
興味を惹かれる謎が冒頭に差し出され、読者を牽引するエンタメの技法がふんだんに盛り込まれている。新規の読者が入りやすい小説になっていると思います。
――こちらは恋愛小説と呼んでも?
金子:言っていいですよね、恋愛小説だと。
大前:僕は、恋が成就するとか、しないとかだけが恋愛だとは思っていなくて。
誰かが誰かを好きになったときって、内面がすごく膨れ上がっていると思うんです。ああでもない、こうでもないと悩んだり葛藤したり。そこの自意識が膨らんでしまうことが、僕はすごく豊かなことだと思っているんですね。そして自分と相手について考えるすごくいい機会だろうなと。
誰かが誰かを、恋愛感情をもとに想う、ということがあれば、それはもう恋愛なのかなとか思います。
金子:『ぬいしゃべ』に、「ぬいサーのBOXでは恋愛や男女の話があまりされない。そういう話、楽しいけど、疲れてしまうから。消費したり消費されたりしているって、自覚してしまうときがあるから。」という文章があって。大前さんご自身も、多分、そういうタイプかなと思っていたんです。私も近い感覚で、『流星と吐き気』にも書いたんですけど、恋愛は加害性と結びつきがちですし。
でも大前さんの作品は、恋愛の小説が多いじゃないですか。恋愛が自分の中でちょっと怖いというか、人を傷つけうるものとしての認識があるのに、恋愛をオブセッション的に書き続けているのって、人が人を想うことへの肯定的な気持ちがあるからなんですか?
大前:内面が膨らみすぎて暴走してしまうと怖いけど、人が人を想うこと自体は良いことだと僕は思っていて。みんな、どんどん恋愛をしなくなりそうじゃないですか。自分一人だけで完結しちゃいそうで。それがあまり良いことだとは思ってなくて。
コミュニケーションしていかなきゃね、と言いたいというのがまずあって、それを言う方法として、なるべく優しい感じの恋愛を書き続けているような意識があります。
金子:コミュニケーションするのは、友情でもいいと思うんですけど、あえて恋愛を書き続けるというのは?
大前:恋愛自体、よくわからないものだと思っていて。よくわからないものだからこそ、書く上で脱線しまくれるというか、いろんなノイズを入れることができる。
さらに恋愛は物語上でも何らかの展開を担保してくれる。誰かが誰かを好きになりました、その思いはどうなる? みたいな予感とか、この気持ちがこうなっていくのかもしれないという展開を、恋愛というだけで、読む人のなかに植え付けることができるから。
金子さんが大前さんにリクエスト!?
金子:最近、初期のような奇想文学は書いてないですか?
大前:そうですね。このところ、そういうものを書きたいと自分から言うことはないですね。
編集者の人と打ち合わせするときは大体、社会がこうなっているから、みんながこういうこと言っちゃうんじゃないか? みたいな話を延々としていて、その中から出てくるアイデアを書いてる感じが多いです。こういう言葉が今流行ってるのには、こういう背景があるんだろうなみたいな。
やっぱり人間ベースというか、社会の空気感が基になっていますね。
金子:今回、大前さんのキャリアを改めて見つめ直して思ったんですけど、奇想短篇で世に出たあと、『ぬいしゃべ』をきっかけに、男性視点でのフェミニズム文学を書く作家として、リアリズムで勝負していくことになったじゃないですか。一方で、日本のフェミニズム文学の潮流には、松浦理英子さん、村田沙耶香さん、藤野可織さん、古谷田奈月さんなど、奇想を膨らませてフェミニズムを書く作家も多い。
SF的な、何か超自然的なことが起こり、それが社会構造に対するレジスタンスに繋がっていくという作品を、多くの女性作家が書いている。それを大前さんがやったら面白いんじゃないかと思うんです。
大前:なるほど。それはちょっと覚えておきます。
金子:ぜひ書いてほしいです! ミニマムな奇想文学から出発した大前さんが、地に足のついたフェミニズム文学に取り組んだ経験を糧に、社会構造をダイナミックに批評する壮大な奇想を展開させる長篇を、ぜひ読みたいです。
大前:時機を見てやってみたいですね。世の中の流れというか、そういうものが求められているときに。
流行ってるものって、段々みんな疲れてくるじゃないですか。疲れているときに別のものが来て、それに乗ってまた疲れ、また流行って……の繰り返しじゃないですか。そんななか、時機を見極められたらいいですね。
読むことでストレス発散にもなったら
金子:世の中の流れで言うと、「ポリコレ」に対する反発も最近はよく見ますよね。大前さんの小説の視点人物はリベラルな価値観を持った人が多い印象ですが、今回は珍しくマッチョイズムを感じる男性も出てきて、こんな人物も書くんだ! と少しびっくりしました。
大前:実際の恋愛リアリティショーを観ていると、男はこうするべき、女はこうするべきという既存のジェンダー感が濃くて。そしてそういう感覚を持っている人ほど番組に採用されているなという感があったんです。
海外の恋愛リアリティショーでは、どれだけいろんなタイプの人を入れられるか、多様性を確保できるかのフェーズに入っていますが、日本はまだそうではない。クラシックな恋愛観を保存しておこう、みたいな気持ちがテレビ番組としての恋愛リアリティショーにあるのかなと。そこを反映する意識もありました。
金子:マッチョイズムを抱えた田中は、「オレ、女の子を守ってあげたいんだけど」と言って、自立した女性に冷めてしまいますよね。さらに虎太郎は、「むかつくんだよな、あいつ」と言いながら、その“あいつ”をどんどん好きになっていく。そんな昔ながらの少女漫画っぽい、人を好きになる過程も描かれていて、それもクラシックで面白い。ちゃんとベタを踏んでいるなと。
大前:ベタなものを好む傾向が若い人ほどあるような気がしていて。クラシックというところでは、前半の舞台が今から8年前の2017年、というところもありますね。
金子:後半のパート、7年後にまたみんなが集まるところでは、社会的な価値観の変化も浮かび上がってくる。でも人って、当時の仲間と会うと、やっぱり同じようなことを繰り返してしまうんだな、というところも面白かったですね。
――金子さんは登場人物のなかで誰がいちばん気になりましたか?
金子:冨樫まつりという女の子です。その日の食事のグレードや寝る場所を毎日ガチャで決めるんですが、ガチャに当たり続け、運が良すぎて辛くなる、という。大前作品で繰り返し描かれてきた、やさしさにがんじがらめになるキャラクターです。
「私が当たりを引くことで良いご飯が食べられない人が出てくる」と、彼女は思い悩むんですけど、ハズレを引いてしまうターンが続くと、それはそれで辛くなってくる、そして……という謎めいた部分が、キャラクターとして魅力的でした。
でも7人それぞれ、ちゃんと愛せるキャラクターになっていて。大前さんがこれまで書いてきた重層的で複雑なキャラクターも好きですけど、今回の7人はチャーミングですごくよかったです。
大前:ビデオゲームをプレイするような感じで書いたので、シンプルに楽しんでいただければというか、読む方のストレス発散になってもらえたら嬉しいです。
金子:大前粟生史上、いちばん間口の広い小説になっていると思います。
取材・構成/河村道子、撮影/米玉利朋子(G.P.FLAG)
小説幻冬8月号より転載
7人の7年の恋とガチャ

『7人の7年の恋とガチャ』に関するインタビューなどを公開します。