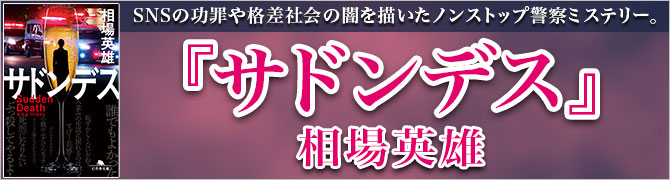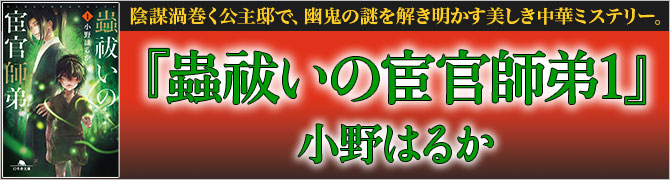大竹まことさんが等身大の「老い」をテーマにつづったエッセイは、今回が12回目。早くも約1年が経ちました。今回は、2023年3月に亡くなられた坂本龍一さんのドキュメンタリー映画についてです。ささやかな日常の中における生老病死について、思いをはせます。
* * *
映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を観た。坂本龍一の最後の3年半のドキュメンタリーである。音楽家・坂本龍一が癌に侵されてから亡くなるまでが、本人の言葉や友人の証言などで綴られていく。語りは田中泯さんである。
冒頭は、坂本龍一さんのニューヨークのアパートの庭にピアノが運び込まれるところから始まる。なぜかピアノは庭に置かれ、風雨にさらされる。時が流れる。
坂本龍一さんが雨の中そのピアノを弾き始める。雨が激しくなる。
別の日には、丸い皿に絵か文字かわからないものを描き始める。描き終わるとなぜか、地べたに叩きつけて割ってしまう。なにか理由があるはずだが、観ている私にはわからない。
ドキュメンタリーの中盤では、雪に埋もれたピアノがまた現れる。途中で「あぁこのピアノは3年半の時間経過を表しているのか」と気がつくが、多分それは半分の意味で、残りはわからないままである。
理解できない事象は楽しい。楽しいまま放っておくのがよい。
彼の日記が出てくる。
「音楽を残すこと
┌残す音楽
└残さない音楽
霧散する音楽」
映画の中、彼が渾身の力を込めて「戦場のメリークリスマス」を弾くシーンが出てくる。
別のシーンでは、イタリアの女性が歌っているのだろうか(私が知らない曲だった)。どこかで聴いた歌なのだが、思い出すにはいたらなかった。いい曲だ。癌に侵されて余命のあまりないことを知った彼が聴いている。泣いている。手や指がなにかを祈っていた。
彼の部屋には、本があふれていた。友人の証言では、孤独な彼は、本が友人だったのではないかと語られていた。彼の日記には、『純粋理性批判』を読むと記されていた。
昔、つかこうへいの舞台を観に行ったとき、たしか『蒲田行進曲』だったと思うが、
「純粋理性批判とは、純粋に理性を批判することだ」というギャグがあったが、大元がわからない私はうまく笑えなかった。みんなは笑っているのに。
『純粋理性批判』を読んでみようと思う。私にも残された時間は無限だが、そう長くあるとは思えない。
映像には力を失っていく彼が、自然な音に近づいていくシーンが何か所か出てくる。
雨や風、それに雲。自然の音は、音楽以上に彼に安らぎを与えたようだ。
窓の外に雲が流れる。四角に囲われた窓枠の向こうに、雲が少しずつ動いていく。
彼は考える。「雲の流れを音に、音楽にできないものだろうか」と。
それが完成したか、私は知らない。
白い月が現れる。雲の隙間を割るように、白い月が現れる。
幻想かと思えるほどの白い月である。
雨がシトシトと地面に落ちる。地べたの土を打つ。水たまりもそこかしこにできている。外燈に映し出された冷たい雨。
映像に音があったのかは定かではない。それでも、私にはその雨音が聴こえた。
坂本龍一さんにも聴こえていたはずである。
太古の昔から雨は降り、風が吹いて季節の雲が大きく流れる。自然が私ども人間たち、そして熊とか鹿、セミやミミズ——余命宣告を受け、苦しい治療を続ければ、1年そうでなければあと半年と告げられた彼は、なにを思ったのか。
最後に、流れる雲を音楽にしたいと思った彼はそれを実現できたのだろうか。雪に埋もれたピアノはおそらく朽ちてゆく。風に叩かれ、雨に打たれ、徐々に少しずつ土に還ってゆくのであろう。
このドキュメンタリーの語り部は、先に記したように田中泯さんである。田中泯さんは坂本龍一さんより年上であり、遅咲きの人でもある。
彼の語りは静かで、寄り添いもせず、ただ静かに伝わってくる。
さてと問題は、私である。76歳。坂本さんの没歳より5歳も年上である。
昨日スーパーで梨を1個買った。もう家に子どももいないし、大きい梨なので1個で十分。妻と、半分をまた半分に割って食べた。
「梨はおいしいネェ」
「おいしいわね」
「柿も売ってたョ」
「柿もいいネェ」
世界は、ウクライナも、パレスチナも壊れていく。この日本とて、底なし沼に引きずり込まれそうになっている。
小さな日常は続くのだろうか。
壊れきったこの世界を雲だけが流れ、風だけが吹いて、雨だけが降る。
もうそこには、なにもないのに。
ジジイの細道

「大竹まこと ゴールデンラジオ!」が長寿番組になるなど、今なおテレビ、ラジオで活躍を続ける大竹まことさん。75歳となった今、何を感じながら、どう日々を生きているのか——等身大の“老い”をつづった、完全書き下ろしの連載エッセイをお楽しみあれ。