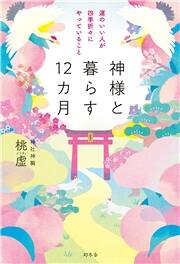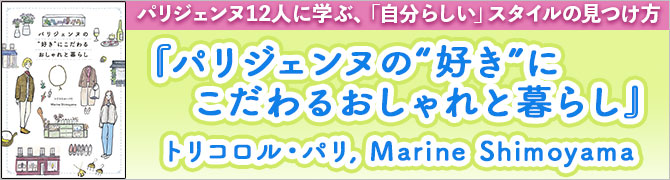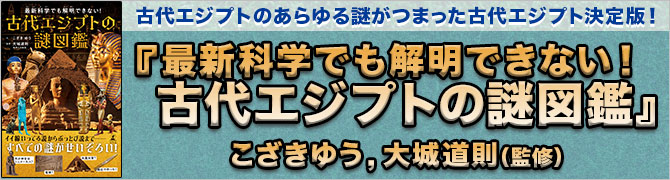かき氷の話題で、少し涼んでみませんか? 実は、平安時代からかき氷ってあったようで…。
神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。
* * *
かき氷について掘ってみたら開運につながったお話
ところで、開運行動の8番目に挙げた、かき氷について。
ばくぜんと、「冷蔵庫が発明されてからできた食べ物」と思っていませんか?
じつは、平安時代、清少納言が「枕草子」で、「貴(あて)なるもの」のひとつとして、
削り氷(ひ)に甘葛(あまづら)入れて、
新しき金椀(かなまり)に入れたる
と書いているのです。かなまり、とは金属のおわんで、そこに削った氷を入れ、甘葛というシロップをかけたもの、すなわち「かき氷」のことです。
しかし、冷蔵庫も冷凍庫もない時代、希少な氷を、どうやって夏に手に入れていたのでしょうか。
実は、天然の冷蔵庫である「氷室(ひむろ)」を活用していたのです。山間部の気温が低いところに穴を掘って作られた氷室。冬の一番寒いときに、凍った池から分厚い氷を削り出し、藁(わら)やおがくずで覆って夏まで氷室に貯蔵しておく、ということが、奈良時代から行われていました。

元明天皇の御世、710年に藤原京から平城京へ遷都のさい、三笠山の山麓や春日野に氷室が置かれ、氷が宮中に献上される「献氷(けんぴょう)」が行われるようになったと言われています。
奈良市春日野町には、それら氷室の守護神として祀られた「氷室神社」がありますが、地域の氏神さんであるとともに、冷凍・冷蔵・製氷の技術の神様、それらの販売業の神様としても、崇敬されています。
平安時代の中期、醍醐天皇の命によりまとめられた「延喜(えんぎ)式」という50巻の法典の中に、氷室は、「山城・大和・河内・近江・丹波の5つの国の10カ所」が記載されています。貯蔵と運搬には、「氷戸(ひこ)」と呼ばれる144戸の専門の家が置かれていて、システマチックに宮中へ氷が供給されていたそうです。
清少納言は、平安時代、宮中に仕える貴族だったから、かき氷を食べることができたのです。そんな彼女が書いている、かき氷にかけたという「甘葛(あまづら)」の味が気になりますね。甘い葛(くず)ですから、葛湯のような、すこしとろっとした風味を連想しますが、植物から取った汁、もしくは樹木からとった樹液を煮詰めた琥珀(こはく)色の液体らしい、ということしかわかっていません。再現して和シロップとして売り出したら人気が出そうだな……とつい夢想してしまいます。
現代では、色とりどりのかき氷シロップが、スーパーに売られています。
「市販のかき氷シロップは、イチゴもメロンもレモンも味は一緒で、色と香料だけが違う」という話を聞いたことがあるでしょう。私もためしに目隠ししてイチゴシロップとレモンシロップを食べて、どちらが何か、当ててみようとしたことがあります。
結果は、見事に不正解でした。同じ実験をした娘はどちらもイチゴだと答え、息子はどちらもレモンだと答え、結局全員わからなかったのです。そのときみんな鼻はつまっていなかったので、もはや香料も関係ないのかもしれません。色を見て食べると、ちゃんとイチゴはイチゴの味が、レモンはレモンの味がしました。

私たちはあのあざやかな色を見てそれっぽい匂いをかぐだけで、イチゴ、レモン、メロンのそれぞれのシロップの味を感じることができるし、ブルーハワイの青色を見るだけでラムネやトロピカル風味(これも漠然としていますが)を感じることができるのです。だとすると、五感とはひとつひとつ完全に独立しているものではなく、相互に補完しあう関係にあると言えますね。
あるいは、本来の全体としての感覚を、論理的に理解する方法のひとつとして、あえて視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の5つに分けてみただけにすぎないのかもしれません。
(つづく)
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む
神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること
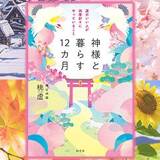
古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!
* * *
神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。
- バックナンバー
-
- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...
- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...
- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...
- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...
- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...
- 神々がしていることを真似すると、運が開く...
- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...
- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...
- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...
- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...
- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...
- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...
- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...
- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...
- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...
- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...
- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...
- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...
- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...
- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...
- もっと見る