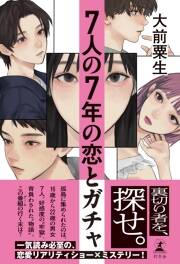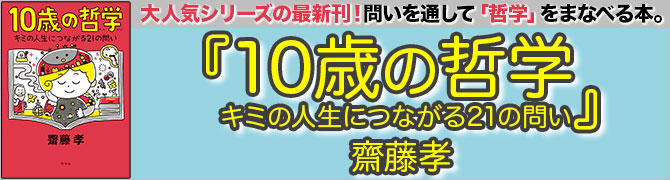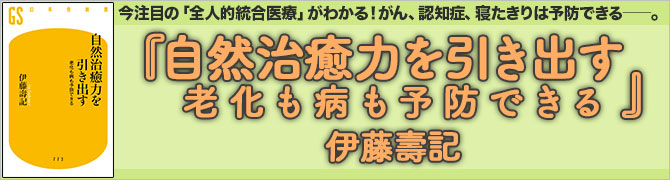大前粟生さんの最新作『7人の7年の恋とガチャ』の刊行を記念して、『死んだ山田と教室』で鮮烈なデビューを果たし、その後も話題作を刊行し続けている作家の金子玲介さんとの対談を行いました。
実は、二人の出会いは2016年。大前さんが「彼女をバスタブにいれて燃やす」で「GRANTA JAPAN with 早稲田文学」の公募プロジェクトで最優秀作に選出されたときに、金子さんがTwitter(現X)で大前さんをフォローしたことから交流が始まったそう。純文学から執筆をスタートしつつ、金子さんはメフィスト賞を受賞しデビュー、大前さんは純文学とエンタメを行ったり来たり。大前さんの新作を軸に、現在地に至るまでを語り合っていただきました。
* * *

恋愛を消費し続けることへの疑問
金子玲介(以下、金子):『7人の7年の恋とガチャ』(以下、『恋ガチャ』)、めちゃめちゃ面白かったです! ミステリーとしての体裁もしっかりしていて、『チワワ・シンドローム』を読んだときも「大前さんがミステリーを真っ向からやっている」と驚きましたが、今回はさらに伏線を仕込み、回収していくことをフェアにやられていて。7人も視点人物がいるのに、エンタメとして人物の書き分けがカッチリしていて、すごく読みやすかったです。
大前粟生(以下、大前):ありがとうございます。
――恋愛リアリティ番組「恋ガチャ」に参加するため、無人島に集められた男女7人。1カ月の共同生活に挑むなか、20日目に脱落者が出て……。そして7年後、その7人が再び、同じ島に集められます。「誰が、一体、何のために?」というミステリーを孕む物語は、2つの時間軸によって構成されています。
金子:7年後にいろいろ効いてくるんだろうなと思いながら前半パートを読み進め、7年後の後半パートでは、ちりばめられた謎が気持ちよく回収されていく。テーマ的なところで言うと、『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』(以下、『ぬいしゃべ』)から大前さんは恋愛の難しさを小説のなかで繰り返し扱っていますが、今回、恋愛リアリティショーというものを通し、恋愛自体に消費を結びつけて考えられたのかなと思いました。
大前:恋愛リアリティショーって、誰かが誰かの恋愛を観て消費するものですよね。でも実はそんな番組を観ている人たちも、たとえば「クリスマスにはデートしなければ」という恋愛のパッケージみたいなものに囚われていたりするし、「私たちはこういう関係です」ということを周りにアピールし続けなきゃ、というような、自分を消費しているところがあると思うんです。それってかなり変だなというか、単純に息苦しいなと。そんなモヤモヤが創作意欲と繋がってきてしまうんです。
金子:今作では、恋愛リアリティショーというフォーマットを用いることで、その問題意識が非常に見やすくなっていると思いました。
大前:冒頭で「書き分けがカッチリしている」と言っていただけたのがすごく嬉しくて。今回、連載させてもらうにあたり、キャラクターの書き分けだけで何か書こうかなと思ったんです。「小説幻冬」はエンタメ雑誌だという意識が僕の中にはあり、せっかくそこで連載させてもらうのだから、ここでだからこそ書けるものを書いてみたいなと。エンタメというか、ノベルゲームを書くようなノリで。
純文学系の雑誌で僕が書くものって、どこか重くなってきてしまっていて、その重さに自分自身やられていく感じがあるので、いろんな軸を確保したいという思いもありました。
金子:私のなかで、大前さんは純文学からスタートし、キャリアを重ねていくなかでエンタメも書くようになった作家、というイメージがあったんです。でも昨日、久々にデビュー作品集『回転草』を読み返したら、「最初からどっちもやってるじゃん」と気付いたんです。
「彼女をバスタブにいれて燃やす」のように尖った言語実験もあれば、「文鳥」のように読者に寄り添った温かい物語もある。
大前:僕は海外文学、なかでもアメリカ文学を日本の小説よりもよく読んでいたんです。海外の小説って、純文学、エンタメというジャンルの括りがないので、そのせいかも。括りの意識というものが自分のなかにはなかった。
金子:じゃあ、作家になってから、括りの意識が芽生えてきたんですか?
大前:僕は文芸誌で書くとき、「この雑誌ってこういう雰囲気だよね」という自分のなかのイメージに寄せるところがあって。あと、編集者の指摘やフィードバックが明確に違います。
エンタメ系の編集者は語順とか、誰が誰だかわかるようにということを言うけれど、純文学系の編集者は細かいところを指摘してくる。たとえて言うなら、エンタメ系の編集者は森全体を見ている感じで、純文学系の編集者は「森のなかにある、ここの木、ちょっとおかしくないですか?」という感じなんですよね。
僕は自分一人で書くというより、いろんな意見を取り入れたい。なんなら編集者に影響されてるくらいでもいいかなと思っているんです。
金子:いろんな出版社さんとお仕事されているなか、編集者さんとのタッグで、いろんな大前さんができあがるというのは面白いですね。
――お二人ともご執筆は純文学からスタートされているけれど、金子さんはエンタメの舞台からデビューし、大前さんは純文学とエンタメを行ったり来たりされていますね。
大前:行ったり来たりが自分の創作スタイルと合ってるのかなと。どっちかだけだと、どちらかの空気しか吸っていないことで、ちょっと息苦しくなっていたかも。
金子:「彼女をバスタブにいれて燃やす」の9年後に『恋ガチャ』のような作品を書いているの、素朴に驚きました。
大前:我ながらほんまに(笑)。語りのリズムさえ合えば何でも書けるな、みたいな感じになってきました。
作品ごとに何か新しい発明をしたい
大前:『死んだ山田と教室』から始まる、金子くんの「死んだ」3部作、そして連作短篇集『流星と吐き気』を読ませてもらい、語りのリズムが本当に良くて、めっちゃいいバンドの演奏をずっと聴いている感じになりました。
改行の感覚も、レイアウトが際立ち、文字を音として鳴らしているようで、金子くんって“声の作家”だなと。
金子:わぁ、ありがとうございます!
大前:音のリズムで小説の時間を進めている感もあり、金子くんの書く登場人物が会話している時間にずっと浸っていたい。喫茶店で、面白すぎる隣の会話をずっと聞いてしまうみたいな、そういう喜びがあるんですよね。
また、ミステリーを書くことによって、小説自体を何か批評したい、そういう意識があるのかなとも思いました。トリックと小説の構造への批評意識が全部マッチしている、一作一作に発明があるなと。
金子:嬉しすぎる! 新しい発明を持ってくる、ということは毎作、意識しているんです。
特に『流星と吐き気』は5篇すべて、新しい文体を作らなければ、と考えていました。
大前:そうした発明への意識って、メフィスト賞でデビューして、ミステリーを書いていることからの影響はある?
金子:純文学投稿時代から常に、一作のなかに発明を一個作る、というのは挑戦していたんです。
でもメフィスト賞でデビューしてからそれがやりやすくなりました。発明をトリック的なところで盛り込みやすくなったんです。純文学だと、ただ実験しているだけになるリスクがあるけど、ミステリーだと実験が小説の目的と直接繋がってくるから。
『恋ガチャ』は大前さんの中で、今までにやってこなかったところ、挑戦的な部分はどこでしたか?
大前:キャラクターっぽいキャラクターを書こうと思ったのは初めてかもしれない。今までどちらかというと、キャラクターっぽくないものをどれだけ書けるかというのをやってきたのですが、今回、リアリティショーというパッケージ、カメラ越しに映る人物たちということもあって、キャラクターとしてデフォルメというか、戯画化して書いたんです。
普段の僕たちもキャラクターとして振る舞おうとしちゃったりすることあるじゃないですか。役割に徹しようとするとか、大きく言うと、そういうノリみたいなものがありますよね。これは「そうしたノリをどれだけ殴れるか」という小説なんです。
物語は本当に人を救っているのか?
――本作で大前さんは「人が背負う物語」を書きたかったと。金子さんの『流星と吐き気』からも「人が背負ってしまった物語」を感じました。
金子:この人が好きだった、ずっとこの人を忘れられないという物語が、自分の中に固着してしまって、そこから逃れられない人たちの話でもあるので、そういう意味では確かに大前さんの今回のテーマと親和性があるかもしれないですね。『恋ガチャ』の後半でもみんなが物語に酔ってる感じ、かなりありますよね。物語に救われているパターンもあれば、物語に苦しめられているパターンもあり、面白いです。
大前:現実の世の中が複雑すぎるから、その世界を単純化し、人を生きやすくするために、遠い昔、物語は生まれてきたと思うんです。けれどいつの間にか、物語の力が強くなりすぎてしまって、何者かにならなければとか、リアルな生活を圧迫するようになってきてしまった。物語って本当に人を楽にしている? って思っちゃいますよね。
金子:物語に縛られて、“自分はこう生きなきゃ”みたいなところって、大前さんがさっき言った、ノリという言葉に近いなと。
『ぬいしゃべ』も恋愛のノリ=物語から逃げようとした人たちがぬいぐるみサークルに溜まる話だし、『物語じゃないただの傷』も、ホモソーシャルのノリやリベラルのノリ=物語から逃げようとする話。
大前さんの作品は初期の頃からわかりやすい物語には乗らないですよね。
大前:そうですね。そもそも物語というものが人に強いる圧力を牽制したいのだと思う。
金子:わかりやすい起承転結から外れていこうとする短篇が初期は多かったですよね。その頃の小説とここ数年の小説って全然違うように見えるけど、物語から抜け出していく動きをどの角度からやるか? という点ではずっと変わらないように思います。
大前:たしかに。そうかもしれない。
金子:小説のフォーマットごと「物語」から抜け出そうとしていたのが初期の奇想短篇で、ここ数年の作品は、人間がリアルに暮らしていく中で、日々の「物語」からどうやって抜け出すか、という小説になっているのかなって気がするんです。
大前:そうですね。
僕は『ぬいしゃべ』以降、読者をなんとなく想定しているんです。こういう感じの生きづらさを抱えている人たちになんとなく届いたらいいなって。
今はリアリズム寄りでの生きづらさとか、ノリに乗ってしまうことを、どうすればいいのか? というところで書いていて。自分のなかでは「人間に付き合っている人」というものを書いている感があります。
* * *
お互いの作品への深いリスペクトを感じる対談、後編は8月8日に公開いたします!
取材・構成/河村道子、撮影/米玉利朋子(G.P.FLAG)
小説幻冬8月号より転載