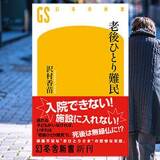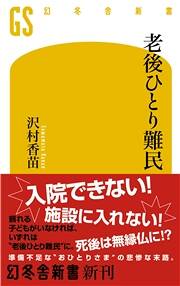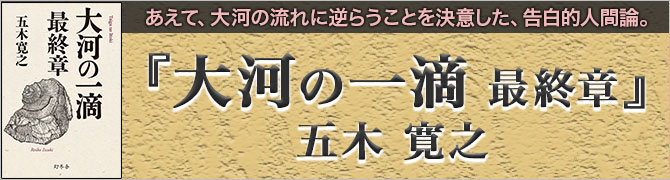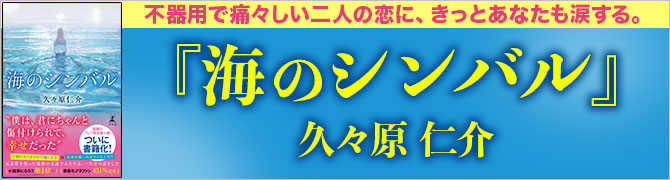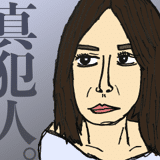
食べ物をはじめとする物価の高騰が日に日に加速しています。「生きていくのに精一杯で、結婚まで考えられない!」という人も少なくないでしょう。とはいえ、結婚していようがいまいが、誰にでも老後は訪れるし、老後の不安がゼロという人もいないでしょう。
そこで今回、『老後ひとり難民』(幻冬舎新書)の著者、沢村香苗さんが、これから老後を迎える人たちの“現実”と、安心して老後を過ごすための仕組みについて解説します。
* * *
老後の準備をしたくても、できない現実
『老後ひとり難民』では、高齢期には自分やそれまで支えてくれていた周囲の人の心身の衰えなどによって、自立した生活の継続が難しくなることを書きました。
特に高齢おひとりさまにとっては、日常生活や医療・介護の手続き、死後の対応まで、自力で完結することは不可能です。適切な助けを得ることができなければ、自分が望まなかった生活や人生の締めくくりを迎えることになりかねません。
世代の若い親族と同居していれば、日常生活の中で自然に手を借りたり、亡くなった後も様々な手続きを引き受けてもらうことが期待できます。ですが今は高齢者のみの世帯が主流となり、身近な親族に頼れない高齢者が増加しています。
将来推計では未婚者や子のない人が増える見通しで、「おひとりさま」は特殊な存在ではなく一般化していくとみられています。高齢期の支援を家族に頼るという前提はもはや崩れつつあり、新たな支援体制が求められています。
50歳から85歳の一般住民2512人を対象とした調査では、9割の人が将来の備えをしたいという意欲を持っていましたが、実際に特定の人に依頼をしている人は1割前後であることがわかりました。
いつ何をしてよいかわからない、面倒だという理由のほか、頼れる人がいないという場合も多く、特に未婚者や配偶者と離別した男性では備えが進みにくい傾向がありました。
また、もともとは家族が「老後の面倒」として行ってきたことなので、「誰かが何とかしてくれる」という漠然とした期待も行動を阻んでいるのではないかと思われます。

2043年には若者2人に対して1人の「はざま高齢者」が存在する!?
一方で、2000年代から入院や入所の時の保証人や死後事務などを家族のように代行する民間サービスが登場していますが、内容は多岐にわたる一方、トラブルもあると指摘されています。
もともとは需要に応じて、各事業者が作り上げてきたサービスですが、亡くなるまでの長期間にわたる契約であることや、契約者本人が認知症や死亡によって、自分が依頼したことを契約相手がきちんと行ってくれているかを確認できないことがありえるなど、構造的に危うくならざるを得ないサービスです。
したがって、これから増えてくるおひとりさまの課題解決をすべて委ねるのは現実的ではないでしょう。
公的な支援制度としては成年後見制度、日常生活自立支援事業などがありますが、これらは判断能力が低下している人を主な対象としています。生活保護制度も伴走的な機能がありますが、経済的に困窮している人が対象となります。
介護保険制度は心身機能が低下している人が対象で、金銭管理や死後事務は支援の範囲ではありません。
また、金融機関などが一部の富裕層にいわゆるコンシェルジェ的な伴走支援をすることはあります。そのため、判断能力があり資力も平均的な層は、公的支援と民間サービスのいずれからももれる「支援のはざま」にあるといわれています。
筆者らの試算によれば、65歳以上のうち「判断能力があり、資力が平均的」な人は2,467.3万人(65歳以上人口の68.1%)にのぼります。
この層は今後ますます増加し、2043年には約2,691.9万人と見込まれ、若年者2人に対して1人の「はざま高齢者」が存在する計算となります。
この人たちをいつまでも「はざま」と呼んでいていいのでしょうか。

「支援のはざま」を放置するリスクとは
今、公的制度の対象にならない高齢者への支援は、ケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーなどによる「アンペイドワーク」に頼っていることが多くあります。
家族がいたとしても、現役世代にとっては育児や仕事と、親の介護や死後の手続きを一手に引き受けることは大きな負担であり、結果的に離職や経済損失を生んでいます。
親族が引き取らない遺体を自治体が火葬することも増え、既に年間4万人以上が自治体によって火葬・埋葬されていると推計されています。
見方を変えると、「支援のはざま」にある高齢者の市場規模は非常に大きいといえます。
たとえば、2023年度の高齢者死亡者数のうち、支援が必要と推定される約98万人に100万円の死後事務費用がかかると仮定すれば、約1兆円規模の市場が存在することになります。
今後の死亡数の増加を踏まえると、規模はさらに拡大すると見込まれます。
一般住民の「老後に備えておきたい」意向は高いにもかかわらず、行動には移せていないことを考えると、サービスの利用までの障壁を取り除くことによって、個人の行動を喚起できる余地はかなり大きいと考えられます。

どのようなサービスや仕組みが求められるか
現在、厚生労働省による「持続可能な権利擁護支援モデル事業」が行われ、いくつかの自治体や社会福祉協議会等によって、終活相談窓口や死後事務支援等のサービスが提供され始めています。
また、金融機関や葬儀事業者等が、法律専門職と連携し、生前と死後に必要なサービスをコーディネートする例も出始めていますが、まだ、どこでも誰でも利用できるとまではいえません。
これからどのようなサービスや仕組みがあれば、「はざま」とされている人たちが人生の締めくくりに備えることができるのでしょうか。
1つは、多領域のサービスの統合的提供です。備えとして必要なことは、生活支援、医療・介護、金銭・財産管理、死後事務の4領域にまたがっていて、連動する必要があります。
各地域において中核的事業者がこれらのサービスを取りまとめることが望ましいでしょう。
2つめは、コーディネートと、利用者との継続的な接点の確保です。
個人の状況(例えば持ち家か賃貸か、お墓があるかどうかなどでも違います)に応じた備えを組み立てるだけでなく、契約から実行まで継続的に見守る体制が必要となります。
「いざという時」には自分でそのことを伝えられないことも多くあるので、備えが役に立つには誰かが状態を把握して伝達しなければなりません。
これらのことを踏まえると、持続可能な支援のためには、自治体と民間が連携し、高齢者にとって信頼できる窓口が地域に存在することが不可欠といえます。
家族でやってきたことをこれからの社会で担うには、1つの主体が肩代わりするような発想では難しく、本人や親族、地域の人たち、自治体、民間企業などが関わることが必要なのです。

* * *
「老後ひとり難民」に起こりがちなトラブルを回避する方法と、どうすれば安心して老後を送れるのかについて詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『老後ひとり難民』をお読みください。