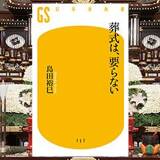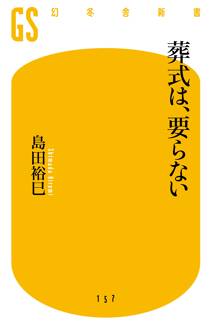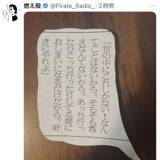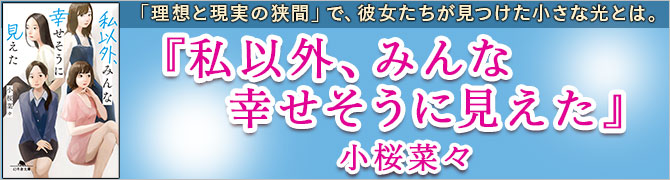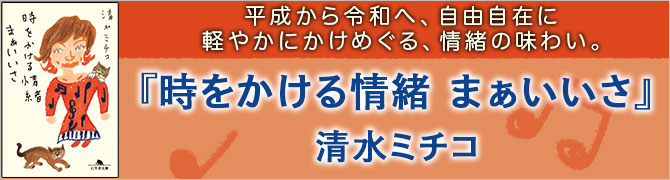葬式に200万円――そのお金、本当に「必要な弔い」のために使われていますか?
宗教学者・島田裕巳さんが日本人の死生観や葬儀の歴史をたどりつつ、葬式の「常識」を根本から問い直すベストセラー『葬式は、要らない』より、一部を抜粋してお届けします。
日本にしかない戒名
仏教界で戒名についてどういう説明がなされているのかを見ていきたい。実は、そこからして大きな問題がある。
そもそも宗派によっては戒名を「法名」や「法号」と呼ぶ。浄土真宗は法名である。そこには、宗派の特殊性がからんでくるが、その点については後で説明を加えることとし、これからの記述では、戒名に統一する。
たとえば、日本仏教の中心的な宗派である天台宗の天台宗務庁では『葬式と戒名のつけ方』という小冊子を出している。そこでは、
「(仏教徒として守るべき戒律を授ける)授戒は俗界をはなれて仏門に帰入せしめる作法であり、戒名は受戒した仏弟子を表示する永遠の法号である」と説明されている。
言い方は難しいが、「仏門に帰入する」とは要するに仏教徒になる、仏教の信者になることを意味する。戒名は、その人間が仏教徒になった証として授かるものだというのである。

現在の寺のあり方を変えようと奮闘する、長野県松本市にある神宮寺の住職、高橋卓志は、戒名には多くの問題点があり、まず「戒なき坊さんから戒名を受けるという根本矛盾だ」と述べている。僧侶は与えられた戒をかたく守らねばならないはずなのだが、現状はとてもそうなっていないというのだ。日本の僧侶は妻帯し、酒も飲む。どちらも、五戒によって戒められている。
高橋は、僧侶が破戒の道をたどっている以上、戒名を授けることなどありえないのに、現実は、葬式の際に僧侶による授戒が行われており、これは極めて矛盾したことだ、と言う(『寺よ、変われ』岩波新書)。
高橋の、いわば自己批判は根源的なものだが、仏教界で行われる戒名や戒名料についての説明はどれも奥歯にものがはさまったような言い方にしかなっていない。どこか本質的な問題から逃げているようで、それではとても納得できないのである。
最大の問題は、それが仏教の教えにもとづいていない点にある。膨大な数存在する仏典では、戒名について説明されていない。それも、戒名という制度が存在するのは、仏教が広まった地域のなかでも、この日本だけだからである。
「葬式仏教」が生んだ日本の戒名
現在の世界のなかで、仏教はキリスト教やイスラム教に比べて信者数は多くないものの、東アジアや東南アジア、南アジアの文化に依然として大きな影響を与えている。
他の仏教国でも、出家して僧侶になったときに世俗の世界の名前を捨て、出家者として新たな名前を与えられる。その点で戒名は仏教の伝統だと言える。だが、ここで注意しておく必要があるのは、それはあくまで出家者のためのもので、一般の俗人が授かるものではないという点である。
日本でも、出家した僧侶はその証に戒名を授かる。その点は、他の仏教国と同様である。ただ、一般の在家の信者の場合にも、死後には戒名を授かる。それが、日本にしかない制度なのである。
出家者は世俗の生活を捨てたわけで、出家の際にまったく新しい人間に生まれ変わったと言える。新しい名前はその象徴である。
一方死者は、生の世界から死の世界へと移るものの出家したわけではない。俗人は、俗人のまま亡くなったはずである。にもかかわらず俗の生活を捨てたかのように戒名を授かる。本来、出家という行為と密接不可分な関係にあるはずの戒名が、それと遊離してしまったのである。

他の仏教国の人が、こうした日本の戒名のあり方を知れば不思議に思うだろう。しかも、日本では、出家であるはずの僧侶が妻帯し、普通に家庭をもっている。それは破戒ではないのか。日本の仏教は戒律を蔑ろにしていると考えられても仕方がない面がある。
それは日本人自身も感じている。日本の仏教は葬式仏教に成り果てたことで堕落してしまった。そう考える人は少なくない。その堕落の象徴が、戒名と戒名料なのである。
* * *
この続きは幻冬舎新書『葬式は、要らない』でお楽しみください。