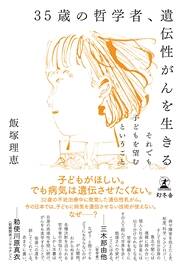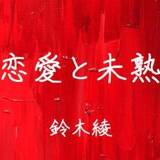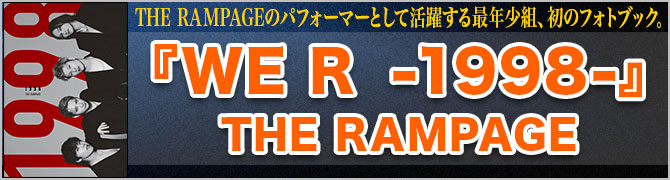32歳の不妊治療中に遺伝性乳がんが発覚した哲学者である飯塚理恵さんが、その治療の経緯と子どもを諦めたくない気持ちを綴ったエッセイ『35歳の哲学者、遺伝性がんを生きる それでも子どもを望むということ』が発売になりました。本書の一部を抜粋してお届けします。

遺伝性乳がんが家族関係に与える影響
わたしと父の仲は良好だ。遅くにできた一人娘を、父は溺愛してくれたと言っても過言ではない。悩みがあって電話すると、父は何でも聞いて優しく励ましてくれる。今までの人生で、父に何かを押し付けられた記憶がまるでない。父はわたしに優しいだけでなく、周囲の人間みんなに対しても、とても優しい人だ。若い頃から、部下のために飲み会を開いて自分が作った料理を振る舞うのが趣味だったそうだ。高齢になった母方の祖母の様子を見に訪れては、「おばあちゃんがお父さんの作ったご飯を美味しいと言っていたんだよ」と喜んでわたしに電話してきたり、30歳をとっくに過ぎた娘に、目に良いからと手作りのベリージャムを毎年せっせと送ってきたりする。わたしは父を尊敬しているし、父の娘で誇らしいと思う。父の偉大な優しさと愛情の前には、父譲りのがんになりやすい遺伝子変異の存在など霞んで見えるほどだ。
でも、世の中の父親(や母親)がみんなそうではないことを知っている。もし父と娘の仲が良好でなかったら、父方譲りの遺伝性の乳がんだとわかったときに、わたしは父に同じ気持ちでいられただろうか。すでに家族関係が壊れていたら、「ろくでもない遺伝子を受け継がせて」と怒らずにいられただろうか。がんになりやすい遺伝子を受け継ぐことが、良好な家族関係を破壊する威力を持つかどうかはわからない。でも、険悪な人間関係を、もっと悪くさせる可能性はあるかもしれない。坊主憎けりゃ袈け裟さまで憎いということわざがある。その人の特性の一つである遺伝子変異が、さらに相手を嫌う理由になることもあるだろう。
こうした感情の動きは、倫理の話ではない。本当は自分がコントロールできるわけでもない遺伝子変異について、誰かを責めるなんて決して正当化され得ないし、そもそもすべきではないのだ。でもわたしたちは、誰かを好きになったり嫌いになったりするときに、その理由の中に「自分のせいで起きたわけではないこと」をそっと忍び込ませることが、実際にはある。こうした個人の思いは法や規則で縛れるものではないので、家族性・遺伝性の病気への差別は、雇用や保険の場面ももちろん問題だが、私的な領域の方がより厄介だ。友情だったり、恋愛だったり、個人の抱く好みを縛ることはできない。あなたが友達になりたいと思っても、相手が嫌だと思えば、友情は成立しないだろう。中でも、遺伝性の疾患で問題となるのは、やはりパートナー・結婚の問題ではないだろうか。
遺伝性がんと恋愛、結婚、パートナー
わたしは大学4年生の頃に夫に出会い、8年間付き合った末、2020年に結婚した。遺伝性のがんを告知された時点(2022年)で、夫はわたしの家族であり、親友であり、恋人であり、唯一無二のパートナーであった。わたしは40歳まで生きられるかわからないし、わたしと子どもをつくれば、50%の確率で子どもにも同じ遺伝子変異が受け継がれるという告知を受けても、それらの情報は、夫とわたしの絆を破壊するような仕方では受け止められなかった。夫はわたしに死なないでほしいと願っても、別れようとは思いもしなかったと言っている。
しかし、これから人生の伴侶を探そうとしている際に、HBOC(遺伝性乳がん卵巣がん症候群)だと告知されたらどうなるだろうか。夫と出会わなかった、独身の自分を想像してみる。
もしわたしに今、新しい彼氏ができたとして、実はHBOCであると、どのタイミングで伝えるか迷うだろう。何回目のデートで、相手にHBOCのことを告白すればいいのか。そもそもがんになりやすい遺伝子変異の情報は、パートナー候補に言う必要があることだろうか。たとえば、マッチングアプリの自己紹介には書くべき事柄だろうか? 誰もが自分を良く見せようとする自己紹介に、わざわざ病気の話をする人は少ないだろう。
では真剣な交際が始まったときだろうか? わたしのように乳房の切除を行っている場合、相手と性的な関係を結ぶことになれば、当然そこで乳がんについては告白しやすい状況が浮上するだろう。しかし、果たしてセックスをする相手に自分のがんが「遺伝性」であることまで伝えるだろうか?
もし、あなたの友人に偶然HBOCの人がいて、「誰かいい人いないかな? パートナー募集中だから紹介してほしいんだ」と言われたとしよう。そのときに、その子の性格の良い面とか、外見の魅力的な部分とか、その他さまざまな要素よりも、その子がHBOCであることが頭に浮かんで、そのせいで同じく恋人を探している別の友人を紹介することを躊躇するかもしれない。そして、限られた数の人だけでなく、社会の大部分の人が同じように行動すれば、これこそが、遺伝性の病気の人たちが恐れている類の、私的な領域の差別となるだろう。
また、HBOCが結婚を考えるとき、相手の親族が反対したら、どうしようと不安に感じる人もいるだろう。何度かしか会ったこともない親戚のおばさんが、「がんが遺伝するなんて可哀想」と言ってきたら? 義理のお父さんが結婚や子を持ちたいというパートナーとあなたの選択に反対してきたら?
結婚や妊娠についての決定は、すべてにおいて、カップル二人が決めるべきことである。しかし、家と家のつながりを重視する人もいるだろう。カップルで決めたくても、親が同居していたりすると親の発言の影響力を弱めることは困難となるだろう。その際に、カップルが望まぬ親族からの圧力のせいで、カップルの取り得る選択が狭められたり、諦めたりしなければならないとき、それは遺伝子差別の一つの形態となる。
こうした苦しみは、もちろんHBOCのような家族性のがんに限られた問題ではない。がん以外の遺伝性疾患に苦しむ人やその家族たちは、長きにわたってこうした苦しみを多かれ少なかれ感じてきたはずだ。また、障害を持つ人のきょうだい児、家庭が特定の信仰を持つ人たちの間などでも、似たような状況に陥り、交際や結婚に消極的になったり、実際にパートナーに交際を絶たれたりした人たちがいるだろう。遺伝性でなくとも、がんになったことで交際相手と破局した、という話も残念ながらよく聞く。そういう話を聞くたびに、わたしはやりきれない気持ちを感じて苦しくなる。
誰とパートナー関係を結ぶかという事柄において正義を語ることは、雇用や保険のケースと比べて、より複雑で難しいものとなる。パートナーを選ぶ際に、あれやこれやの見た目がどうか、と吟味することは大抵許容されるのに、健康で長生きしそうな人が良いと望むことは差別になるのだろうか。見た目だって、大部分は自分ではどうしようもない人生の側面である。そう考え始めると、そもそも、恋は究極的な意味で差別ではないかとさえ思えてくる。わたしがどんなに相手を好きでもどんなに努力をしても、相手が同じように気持ちを返してくれなければ、関係は成立しないからだ。では、自分がHBOCだとわかってしまったら、恋のスタートラインに立てないのか? そんなことは、当然ない。
HBOCであるという特性を考えるとき、それが交際相手にとって望ましいような環境はあるだろうか? 残念ながら、HBOCであることがHBOCでないことよりも好まれるようなニッチを、現状わたしは想像することができない。つまり、いくら遺伝子変異というものが生物学的に見れば中立的な現象であっても、わたしは自分のBRCA2の病的遺伝子変異を、自分の持つポジティブな特徴とは見なせない。
でも、HBOCであるということは、その人の他の良い特性すべてをキャンセルしてしまうような、悪い特性でもないと思う。わたしはHBOCであることが、つまり、がんになりやすい遺伝子変異を持っていることが、わたしという人間のうち、ネガティブな特性の一つではあっても、たくさんある特徴のうちの一つに過ぎないものであれば良い、と感じている。欠点のない人間はいないし、その欠点が自分の努力ではどうにもならないものであることだって多くある。むしろ人間には欠陥があるからこそ、多くの人が、自分とは別の人間と一緒に過ごすことを選ぶのかもしれない。
パートナーに望ましいとされる特性はたくさんある。わたしはおそらくヘテロセクシャルな女性なので、恋愛対象は男性だ。友人と「好きな男性のタイプ」を話すときに出てくるのは、優しい性格だとか、仕事ができるとか、家事を積極的に行うとか、努力家だとか、真面目だとか、頭が良いとか、背が高いとかイケメンだとか色々なことだろう。そうした特性の中には、8割くらいの人が望ましい・望ましくないと同意する特性もあれば、意見が半分半分に分かれるような特性もある。
また、自分の努力で変えられる特性もあれば、そうではないものもある。一つの要素をすごく重要視する人もいれば、満遍なく、さまざまな要素を満たしていないと嫌な人もいるだろう。「他のすべての条件が同じ」だったら、HBOCの人か、HBOCでない人、どちらが良い? と言われたら、もちろん後者を選ぶ人が多いだろうが、実際にパートナーを探す際には、「他のすべての条件が同じ」などという前提条件はほぼあり得ない。HBOC以外の部分で、誰かにとって抗えない程魅力的な人になることはきっと可能だ。
自分がHBOCであるとわかっても、パートナーに申し訳ないとか、パートナーを解消した方が夫にとって幸せなのではないかとか、考えたことは一切ない。わたしが毎日ハッピーで笑っていた方が、泣き暮らしているより、夫はきっと幸せだろうと信じて生きている。わたしが若くしてがんになり、夫には多大なる迷惑をかけた。でも、人間はみんな他人に少しずつ迷惑をかけて生きているし、迷惑をかけ合える社会の方がきっと、多くの人が生きやすいと思う。
35歳の哲学者、遺伝性がんを生きる
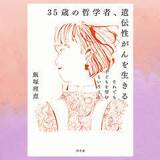
『35歳の哲学者、遺伝性がんを生きる それでも子どもを望むということ』について