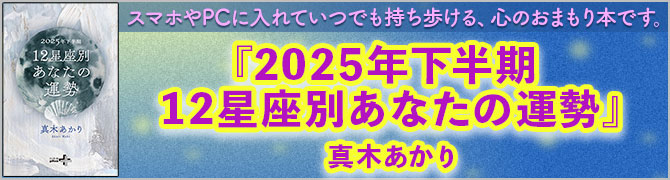「100分de名著」(NHK Eテレ)で取り上げる作品を九年にわたり選び続けてきたプロデューサー、秋満吉彦さんが最も戦慄を覚えたのは、現代社会のありようを言い当てる「名著の予知能力」でした。5月31日に発売された新書『名著の予知能力』は、まったく新しい名著の読み方を提案する書。
講師が青ざめるとき――シェイクスピア「ハムレット」(2014年12月放送)
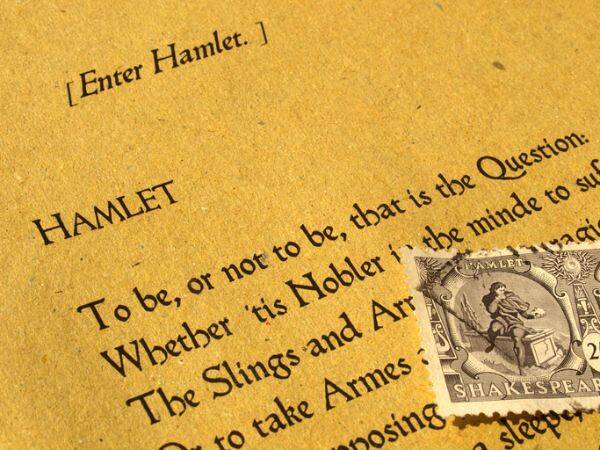
日本を代表する……いや国際的にも高い評価を受けているシェイクスピア研究の第一人者の顔が青ざめていた。モニター越しに見えた表情なので、スタジオ照明の加減もあり、やや誇張が入ってしまっているかもしれない。もっと正確にいえば、表情がこわばっていた。次の句が継げないでいる。明らかに挙動がおかしい。
東京大学大学院総合文化研究科教授・河合祥一郎さん。「ハムレットは太っていた!」「謎解き『ハムレット』」といった著作に惚れ込んだ私が、「ハムレット」解説講師として抜擢した俊英だ。該博な知識とシェイクスピア愛あふれる華麗な解説が副調整室にいるスタッフ全員の心をも鷲摑みにしていたさなかだったので、明らかに異常事態である。
ようやく気持ちを取り戻した河合さんは、こういった。
「『ハムレット』の研究については、海外のものも含めてほとんどの文献や論文に目を通してきたつもりですが、その解釈は初めてです。私自身も、そんな解釈が可能とは思いもよりませんでした。でも、その解釈は『あり』だと思います」
いったい何が起こったのか?
主人公ハムレットが父親の仇(かたき)として憎むクローディアスのある台詞(せりふ)について、司会の伊集院光さんがさりげなく発した感想が、河合さんの思考を一時フリーズさせたのである。
伊集院さんの直観的なコメントが稲妻のようにひらめき、著名な研究者や作家が一瞬我を忘れてしまう。そんな瞬間を何度体験したことか。更にいえば、この瞬間こそ、「100分de名著」という番組の最大の醍醐味である。台本通りの予定調和を切り裂く一言。それを受けて、一気に場が加速を始める。刺激された講師からも想像を超えたコメントが次々に発せられる。ウィンブルドンでの頂上決戦で一流テニスプレイヤーたちが繰り広げるようなラリーの応酬。番組の進行を俯瞰(ふかん)して眺めているはずのプロデューサーも、恍惚に近い感情に押し流されていく時空だ。
今回問題となったクローディアスの台詞とはこうである。
言葉は宙に舞い、心は重く沈む。心の伴わぬ言葉は、天には届かぬ。
(「新訳 ハムレット」シェイクスピア著、河合祥一郎訳、角川文庫)
ハムレットの父親である先王を殺した罪をクローディアスが懺悔(ざんげ)するシーン、ラストの台詞。懺悔室でさんざん懺悔した風を見せて、最後に「なーんちゃって」と、クローディアスは舌を出すわけだ。こんな懺悔なんて噓っぱちだよ、と。
物陰に潜んでこの様子を見つめるハムレットは、懺悔の途中で殺してしまっては、クローディアスを天国に送ってしまうことになる……ということで、クローディアスを殺すことを思いとどまる。だけど、実はクローディアスは懺悔なんてしていなかった。哀れ、ハムレット。ここで殺してしまえばよかったのに……と、舞台を観ている観客がはがゆい思いをするシーンとされてきた。これまでの解釈では。
ところが! 伊集院さんは新たな解釈を打ち出すのだ。
「ぼくは、真剣に何かを話すことが怖いから、本当のことをいった後に、つい照れ隠しで『なんつったりしてね』っていうことがよくあるんです。つまり、クローディアスはここで、舌を出して『なーんちゃって』といっているわけではなくて、『こんな俺が天国に行っていいわけないじゃん。懺悔で許されていいわけないじゃん』って真摯な気持ちで懺悔しているともとれるのではないか」
河合祥一郎さんが青ざめたのはこの解釈を聞いたからだ。クローディアスという登場人物が単なる悪役ではなく、極めて複雑な陰翳(いんえい)をもつ魅力的な存在として立ち上がってくる優れた解釈。一流の研究者ですら思いもよらなかった解釈が飛び出してしまうこの状況を、伊集院さんは、かつてこんな言葉で語ってくれた。
「無知との遭遇」
もちろんスティーブン・スピルバーグの映画「未知との遭遇」をパロったものだが、伊集院さんは、こんな風に説明してくれたのである。
「中卒で教養も知識もない自分のような人間だからこそ、先生方はいつも全身全霊でぼくにぶつかってくれる。だからなんだよね。いつもだったら絶対に出会わないぼくのような『無知』に先生が遭遇したときに、思いもよらない化学反応が起こる。自分自身も全く忖度(そんたく)なしで直観的に感じたことを言葉にしていくと、それが一流の先生方も驚いてしまうような言葉に結果的になってしまう。それを受けて先生も想像以上の言葉を発してくれる。この番組が一番面白いのはこういう響き合い」
伊集院さんの言葉は謙遜にすぎる。ラジオパーソナリティとして長年培ってきたトーク展開力、膨大な数触れ合ってきたリスナーたちの人生、休日すらインプットの時間としてさまざまな体験を仕込んでいく貪欲さ……伊集院光という人間の裾野の広大さが、可能にした解釈だと私は思う。
収録終了後、河合さんは私にそっと耳打ちした。
「秋満さん、ぼく、このネタで一本論文を書けてしまうかもしれません。目が覚めるようでしたよ」
私自身も体が震えた。プロデューサーに就任して以来五か月目にして、この番組の底力を見た。名著と講師と……そして進行を担当する司会、アニメーション、朗読、ナレーション……全ての要素が響き合い、幾重にも倍音となる「共鳴空間」。その中で想像を超えた「事件」が起こる。こんな番組、観たことがない。
シェイクスピアの「ぶちかまし」
「ハムレット」のシリーズは、その後も、何者かに加速させられるかのごとく、次々と魅力的な解釈を生み出していった。全てを書いていくときりがないが、その後の番組の方針を決定づけるような解釈が再び出現するので、そのことを書いてみたい。その解釈とは、以下の台詞を巡ってのものだ。
君たち、青白い顔をして、この出来事に震えているのは、まるでこの芝居のだんまり役か観客だな。
(前掲書)
この台詞は、決闘試合に臨んで、ついに父王の復讐を成し遂げて死にゆくハムレットが、呆然と見守る観衆たちに投げかける言葉。普通に考えればそうなのだが、河合祥一郎さんはこういう。
「これは『メタシアター』といって、芝居の枠組み自体を見せてしまおうというシェイクスピアのテクニックの一つなんです」
つまり「君たち、青白い顔をして、この出来事に震えているのは、まるでこの芝居のだんまり役か観客だな」という台詞は、芝居の中で描かれる決闘試合の観衆に投げかけている台詞であると同時に、リアルに「ハムレット」というお芝居を観ている現代の私たち観客自身に投げかけられた台詞でもあるというのである。
この台詞は、芝居に没頭していた私たちをいきなり現実に引き戻す効果をもっている。「そこにいる現実の観客の君たち、『ハムレット』というお芝居を、自分たちとは関係ないものと思って傍観者みたいに観ているんじゃないか? 他人事じゃないんだぜ」とシェイクスピアが叫んでいるのだ。朗読した俳優・川口覚さとるさんの読みの素晴らしさもあって、この一言を聞いたとき、思わず、我が身を貫かれるような思いがした。「おまえは、運命に唯々諾々と従うだけなのか、それとも命がけで何かを変えようと踏み出すのか、どっちだ?」とハムレットに指さされているような錯覚。
なんだ? この言葉の力は?
伊集院さんは、この手法を「ぶちかまし」と表現して、感動を次のように語ってくれた。
「役者ごとこっちの現世にタイムスリップしてきた感じも受けるし、逆に俺ら観客ごと向こうのシェイクスピアの世界にタイムスリップした感じも受ける。人によって感じ方がまるで違ってくると思う。お芝居自体の奥行きが一気に広がる。これは映画じゃできない」
時空を超えて我が身に迫ってくる名著。執筆された時代の背景と、その作家を支えた思想を奥深く読み解いていくと、名著は、今を生きる私たちの人生をも激しく揺さぶる力をもちうる。いや、そうではない。そういう力をそもそももっている本こそが「名著」なのだ。
「100分de名著」なんて、難しい本をダイジェストにして、お粥のように加工してわかりやすくする初心者向けの番組だろ?……巷(ちまた)ではそう揶揄(やゆ)する人たちもいる。
とんでもない!
私はこのシリーズで何かをつかんだ。「ハムレット」という四百年以上も前の物語が、現代の物語……いやそれ以上に私自身の物語となった。我が血肉となった「ハムレット」は、確実に今後の私の人生にコミットしてくるだろう。これこそが、名著を読むという体験ではなかったか。
私は、そのとき人類が紡いできた奥深い歴史とつながった気がした。名著は、今に甦えってこそ名著なのだ。そうやって幾年月も読み継がれてきたのだ。そのことを体感した出来事だった。
それから二か月後、私は、更なる深い体験を通して、番組の基本コンセプトを固めることになる。
※続きは、『名著の予知能力』をご覧ください。
名著の予知能力

NHK Eテレ「100分de名著」プロデューサーによるまったく新しい名著の出会い方