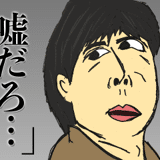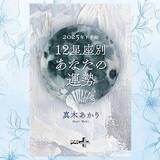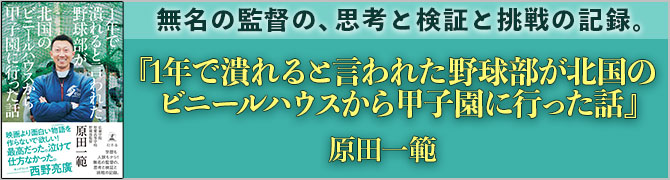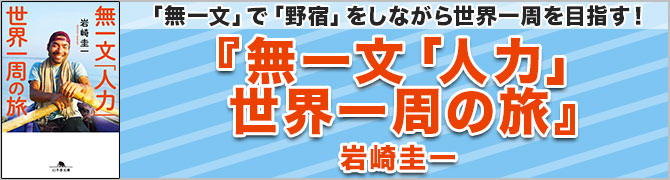メジャー大会で距離測定器の使用許可。どう変わる?
全米プロゴルフ協会が、主催するメジャー3大会で距離測定器の使用を許可すると発表した。5月に開催される全米プロゴルフ選手権を皮切りに、全米シニアプロ選手権、KPMG全米女子プロゴルフ選手権で使用が認められることになった。
通常プロは試合の数日前に会場入りし、練習ラウンドを行う。その際に、キャディとともに目印となるバンカーや樹木などからグリーンへの距離をレーザー測定器で計測し、あるいは歩測などしてコースマップに書き込む。
ここから先は会員限定のコンテンツです
- 無料!
- 今すぐ会員登録して続きを読む
- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン
ゴルフは名言でうまくなるの記事をもっと読む
ゴルフは名言でうまくなる

スコアアップの鉄則は、古今東西・名選手の金言に学ぶ。読むだけで100を切る! 知的シングルゴルファーになるためのヒント。
- バックナンバー
-
- 「われわれは人間である以上、すべてのミス...
- 「ヘッドスピードを上げるには、インパクト...
- 「レギュラーツアーではもう7番アイアンは...
- 「スタンスは楽に動ける幅であって、長いク...
- 「殴られて言うことを聞く者はいないよ。た...
- 「カップに打つんだ、という意識を持つこと...
- 「May the Force be wi...
- 「弱気は最大の敵」――津田恒実
- 「恥ずかしいのはハンディが多いことではな...
- 「プレーヤーは自分のスタート時間にスター...
- 「ティーグランドは、コースのなかでも特に...
- 「ポーカーフェイスは、その後のプレーでミ...
- 「俺は何に対しても縛られたくないんだ。」...
- 「ゴルフの上達に近道はない」――スコット...
- 「スイングにリズムを与えるためには、ボー...
- 「スウィングの始動前に、肺の奥底に少しだ...
- 「高速カメラやテレビは、スウィングをはっ...
- 「進歩の遅い人間に限って、スイングのあれ...
- 「顔が良くて、打ち損ないが少ない。それこ...
- 「パッティングでもショットと同じ様にタメ...
- もっと見る