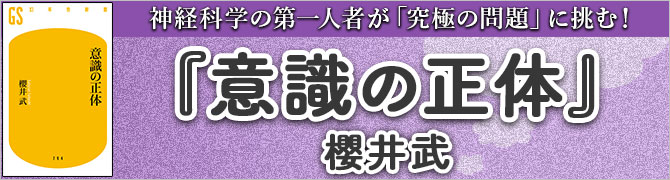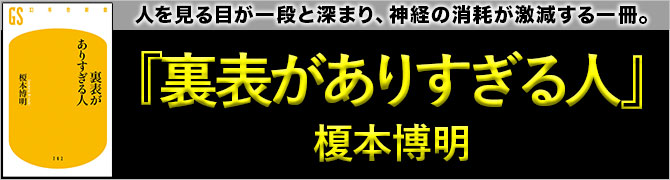起訴した事件の有罪率は99%以上、巨悪を暴く「正義の味方」というイメージのある検事。
取調室での静かな攻防、調書づくりに追われる日々――華やかなイメージとは裏腹の検事のリアルな日常と葛藤を、検事歴23年の著者が語り尽くす。『検事の本音』、その真意とは。本書より、一部を再編集してご紹介します。
* * *
被疑者の心を開かせる方法
検察官(検事)になると、殺人、強姦、強盗などの極悪卑劣な犯罪を扱うことになる。
被疑者を起訴するか否かは、検察官だけが持つ強大な権限であり、検察官による起訴、不起訴の判断は、被疑者、被害者双方の事件の関係者の人生を大きく左右する。検察官は、常に決断を迫られており、その精神的なプレッシャーたるや喩えようがない。
そのため、捜査検事は、職場から離れても、一日中事件のことを考える。
本当は、プライベートとしっかり区別しないと生活にならないのだが、少なくとも私にはそれができなかった。
帰りの電車の中でも、帰宅して風呂に入っているときも、挙げ句の果てにはトイレの中でも、布団に入ってからも、担当している事件の被疑者、上司のことで頭がいっぱいになる。
「明日はどう取り調べようか」
「どう調書にまとめるか」
「起訴状はどう構成すればいいか」
「上司に戻されたらどうしよう」
などと考えてしまう。夢にまで出てくる。寝ても覚めても頭の中は被疑者のことや上司とのことばかりなのだ。
目覚めると、もう朝なのかと嘆息する。起きたときから、すでにその日の緊張が始まっている。
寝ても覚めても被疑者のことばかり考えてしまう、検事の頭の中
そういう状態なので、私は極力、家族との会話を避ける。一人の時間をそっとしておいてほしいからだ。
こうして、ほとんどいつも大きな緊張とプレッシャーを抱えながら通勤するのだが、こらえきれず、ときには、朝の満員電車で緊張のあまり気分が悪くなることすらある。
そこで、音楽を聴きながら電車に乗ったり、座れた場合には極力寝ることにして心穏やかになるように努めたものだ。

ある殺人事件の女性被疑者を取り調べたとき、供述している動機にどうしても納得がいかなかった。自分だったらどうしただろうと、自らに置き換えて考えてみると、どうしてもその動機が理解できなかったのだ。
そこで、ある日、当の女性被疑者に「私は、帰宅の電車の中でも、自宅で風呂に入っていても、トイレに入っていても、布団に入っていても、ずっとあなたのことばかり考えている。これほどまでにあなたのことを思っている人はどこにもいないくらいだ」と素直に話した。恋人でもそこまで思わないだろうというくらいに、本心からそう思ったからだ。
すると、不思議なことに、次第に彼女の態度が変わり、本当のことを話し始めた。
自分が担当した事件の真相追求のためであるが、一日中、被疑者のことを考えている。そのことがときとして被疑者の心を開かせる力や、方法になるのだと知った。
警察と検察、一触即発のそこにある危機
検察だけでは捜査はできない。どうあっても警察の力が必要だ。
検察と警察は二人三脚であり、車の両輪のようなものだ。
だから、事件送致を受けた際には、担当の警察とよく連絡を取り合い、お互いの信頼の下に捜査を進めていかなければならない。
「検事は偉いんだから俺の言うことを聞け」などと、検事が威張っていては絶対にダメである。
新任検事の頃、私は補充捜査のために警察のある担当係長に電話していろいろとお願いをした。
補充捜査とは、警察から事件送致を受けた後、警察を指揮して被疑者や被害者、目撃者などをさらに取り調べたり、証拠を収集・分析することをいう。
ところが、担当係長は、こちらが何を言っても、それについていちいち言い訳や反論をし、「何のためにそんなことをしなくてはいけないのですか。こちらも忙しいんです。検事、もう一度よく考えてほしい」とまで言われてしまった。
つまり、担当係長が主任検事である私の指示を受け入れてくれない、という事態が起こったのだ。
ショックだった。

新任検事は、先輩検事と同じ部屋で執務している。
私の様子を見ていた先輩検事が、種明かしをしてくれた。
「君が新任検事だと分かっているから、そう言われるんだよ」
警察は、検察庁のどの部屋にどの検事と事務官が配置されていて、それぞれの内線番号が何番であるのかが一目で分かる配置図を持っている。
だから、電話をかけてきているのが新任検事であることぐらいは相手には一目瞭然なのだ。
もっとも、その係長は私に嫌がらせをしていたわけではない。
係長からしてみれば、私が求めていたのは、ただ勾留延長を請求したいばかりに不必要な証拠を集めようとしたり、警察から被害者に示談を勧めるような的外れなことだったのだ。
警察にしてみれば、「うるさいなこいつ。そんなことは分かっている。こっちもほかの事件があるから順番にやっているんだよ。そんなこともこの新米検事は分からないのか。偉そうに」と内心、思ったのだろう。
そのことを理解した上で電話しなければならなかったのだ。
だから、いきなり具体的に「これとこれを、いついつまでにやってほしい」と言っても警察には拒絶されるか、嫌われる。
それに、警察のほうも係長としてのプライドがある。
そこで熟慮の末、考えついたやり方は、「この事件についてどんな補充捜査を考えていますか?」と尋ねることだった。
これに対して、係長がいろいろと答えれば、「では、それでお願いします。いつまでにできますか」と言えるし、係長の捜査方針を支持することにもなる。
期限についても、係長が自分の口から言うことになるので、彼のプライドを保持しながら責任を持たせた補充捜査が期待できるのだ。
もし係長が具体的に答えられず、「被疑者の取調べを進めることくらいですかね」などと言ったら、「それなら、これこれをお願いできますか」と言って、その理由も説明すれば、係長は「なるほど、分かりました」となるのだ。
この係長との一件を教訓に、とにかく、警察に動いてもらうには、信頼感と安心感、何より実績を積み上げなくてはならないとつくづく思ったのだった。
同時に、警察の方でも、検事の指摘や指示を受けて、「なるほど、そういう視点もあったのか」と気づき、それがより適切な証拠の収集に結びつく。そのようなことが度重なることで信頼を寄せてもらえるのだ。
そのことを学んだ私は、転勤して着任した場合には、最初の三か月は、地元の警察の信頼を得るために結果を求めて必死に捜査をし、「この検事でよかった」と思われるように心がけた。
私に限らず、検事は警察との強固な信頼関係を築くことを目指し、そのために創意工夫しながら、連日、捜査を行っている。

ところで、ときには、警察の方から内偵段階で相談を受けることがある。
「この事件、上手くいけば警察庁長官賞ものだよ」などとおだてながら、実際に内偵段階から捜査を進め、実際に受賞に至ったこともある。
検事も警察も、一番嬉しいのは難しい事件を起訴できた際の打ち上げのときだ。
事件によっては、警察署長主催の打ち上げに、上司と検事、立会事務官が招待され、こちらが祝辞を述べることもある。
そして、酒を酌み交わしながら、互いの苦労話をして信頼関係をさらに深めていくのだ。
しかし、組織と役割が異なることから、検察と、起訴という成果を気にする警察との間には、一触即発の確執や危うさを秘めた見えない深い溝のようなものがあるのも事実である。
県警との衝突が生んだ“組織の溝”
私が刑事部長としてある地方に着任して一か月が経った頃、県警刑事部と検察との合同会議があった。こちらは検事正以下、刑事部の検事は全員出席だ。
その席で、何を思ったのか、県警捜査一課の課長ではなく、ベテランの捜査員の一人が唐突に、「今度の地検の刑事部長さん(私のこと)は、私たちの事件をいつもつぶしにかかっているようだが、これはいったいどういうことですか」と根も葉もないことを興奮しながら言い出した。
我々は、一同驚愕した。
ここは公の会議の場である。
しかも、幹部でない捜査員からの発言ということに私も驚いた。
後日、その発言については捜査一課長から私に謝罪があった。ある事件が不起訴になったことで、溜まりに溜まった鬱憤が爆発し、私を断罪するように憤りをぶちまけたということのようだ。彼には彼なりの警察官としての危機意識と正義感があったのだろうが……。
そこで、看過してはいけないと思った私は、この一件に真正面から向き合うことにした。
私のカウンターパートは県警の刑事部長であったが、その後は、捜査一課長に直接電話をするようになり、お互いの信頼関係の醸成に努めた。
実際に、殺人事件の現場には、主任検事だけでなく刑事部長の私も赴き、現場で捜査員から直接説明を聞いたりした。
例の発言をしたベテラン捜査員にも、現場で私から積極的に声をかけ、彼の見立てや、今後の段取りなども聞いた。
そうした中で、「部長、あのときは私が誤解して、口に出してしまってすみませんでした」と言ってもらった。
私が異動になったとき、県警捜査一課の課長以下捜査員がわざわざ集まって、私のために送別会を開いてくれた。
私なりに努力して、その甲斐あって、信頼関係を作れたのだと思うと嬉しかった。
検事を退職後、昔一緒に苦労した各地の警察仲間たちとは今でも付き合いがある。
私には今も貴重な財産であり、友人たちである。
* * *
冤罪を生まないために、一切のミスも許されない検事の日常を知りたい方は、幻冬舎新書『検事の本音』をお読みください。
検事の本音

起訴した事件の有罪率は99%以上、巨悪を暴く「正義の味方」というイメージがある検事。しかしその日常は、捜査に出向き、取調べをして、調書を作成するという、意外に地味な作業ばかりだ。黙秘する被疑者には、強圧するより心に寄り添うほうが、自白を引き出せる。焦りを見せない、当意即妙な尋問は訓練の賜物。上司の采配で担当事件が決まり、出世も決まる縦型組織での生き残り術も必要だ。冤罪を生まないために、一切のミスも許されない検事の日常を、検事歴23年の著者が赤裸々に吐露する。