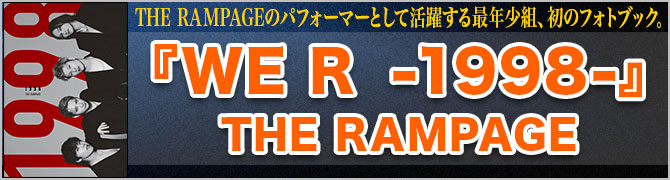前回は野菜界における2大巨頭、ジャガイモとトウモロコシについてでありました。ひょっとすると、このふたつは野菜というより穀物ではないかというご意見があるやもしれませぬ。確かにそうかもしらんけど、というようなところから始めさせてもらいます。
野菜界第3位は、これまたアンデス原産の、あの野菜
野菜と穀物の区別は意外と難しい。広辞苑だと、野菜は「生食または調理して、主に副食用とする草本作物の総称。食べる部位により、葉菜あるいは葉茎菜・果菜・根菜・花菜に大別。芋類・豆類はふつう含めない」とある。それに対して穀物は「種子を食用とする作物で、多くは人類の主食となるもの。すなわち、米・大麦・小麦・燕麦・粟(あわ)・稗(ひえ)・黍(きび)・玉蜀黍(とうもろこし)・豆など」とある。
あかんやろ。これは。ジャガイモは野菜に入れてもらえないだけでなく、種子を食用としないから野菜にも属さへんやないか。トウモロコシは「種子を食用とする作物」なので穀物の例としてあげられているけれど、野菜でもある。ジャガイモはどちらにも入れぬ仲間はずれ、トウモロコシは股座膏薬みたい、と、立場は違うが、いずれも野菜と言っても間違いではあるまい。
「股座膏薬」、死語やろか、わかりますかね。股座は「またぐら」と読んで、両ももの間のこと、膏薬は「膏(こう)で練った外用薬剤。紙片または布片にぬって身体の患部に貼る(広辞苑)」、サロンパスみたいなもんである。なので、あっちにつき、こっちにつくという意味から、態度が一定せんことを意味する。視覚的にイメージしたらなんともシュールで、好きな四字熟語なんですけど、おもろくないですかね。ということで、って、どういうことかわからんけど、やはり野菜界の生産量トップツーはジャガイモとトウモロコシにしておきたい。では、第3位はなんでしょう。
少し意外だった。生活実感の消費量から、タマネギかキャベツではないかと思ったのだが、正解はトマト。そんなに食べますかねぇ、トマト。ジャガイモ、トウモロコシは野菜としての立場があいまいなので、野菜らしい野菜ナンバーワンはトマトと言ってええんかもしれん。
野菜、穀物の区別はおくとして、トマト、ジャガイモ、トウモロコシの3大巨頭がいずれのアンデス原産であるというのは面白い。最大の理由は、太平洋岸から数十キロしか離れてないところで標高が3000メートルに達するアンデスの地形とされている。そのために、植物は異なる気候条件に適応する必要があり、遺伝的な多様化が進みやすい。それをインカ、アステカのような古代文明が栽培化し、品種改良がおこなわれたかららしい。トウモロコシはさておき、トマトとジャガイモのない食卓は寂しい。アンデス、偉いやないか。
トマトに砂糖をつけて食べたことありますか
仲野家菜園でもトマトは優等生である。普通のトマトとミニトマトを栽培しているのだが、どちらも非常によく実る。ただし、ミニトマトは売られているのと同じサイズに達するが、大玉トマトの種を育てても、あわれ、せいぜい中玉サイズにまでしか育たない。これも理由は不明である。それでも、シーズンになればどんどん採れる。特にミニトマトはこれでもかこれでもかと実る。
ナス科の植物、トマトやナス、ピーマンなどの栽培で面白いのは、2本立てとか3本立てにして収量を増やせることだ。野菜を育てる時、ふつうは主枝だけを残してわき芽を取り除く。けれど、トマトなどは、主枝ともう1本あるいは2本のわき芽を残して、収穫を増やすことができる。なんだか無理に収奪してる気がしないでもないが、こういったやり方もあるので、ミニトマトは2株もあれば、シーズン中は毎朝いやというほど食べることができる。
トマトはあまり水やりをしないほうがいいとされている。その方が、根をよくはって、糖度が上がるからだ。しかし、水やりのところで書いたけれど、これは意外と難しい。素人としては、枯らすのが何よりイヤなので、わかっていてもついやりすぎになっている。確かに糖度は低い目かもしらんが、十分に美味しいし、みずみずしさだけで十分やと納得することにしている。
糖度と言えば、最近のトマトは甘いし、売られているものはすべて完熟だ。だが、昔は違った。青い、というか、もっと緑が残っていたし、甘くなかった。完熟させると運ぶ途中でいたんでしまっていたのが、品種改良により、完熟したものも運べるようになったのだ。もちろん、甘さも品種改良により向上し、昔は4~5度だったのが、いまは10度以上のものまである。自家栽培で早採りして青いトマトを食べたら、子どもの頃の味がした。
若者に「また先生そんなウソを」と言われたことがあるが、子どものころはトマトに砂糖をつけて食べていたくらいだ。それに、ほとんどが生食だった。母親などは料理に生でないトマトが出てくるたびに、トマトを調理する時代が来るとは思わなかったと言っていた。この変化はイタリア料理の影響だろう。料理研究家の土井善晴先生オススメで、味噌汁にトマトを入れたりしてもいける。でも、考えてみたら、ケチャップはあったんやから、昔から生食以外でも食べてはおったな。
可愛い、仕事もはかどる?「ポモドーロ」
トマトという名前は、メキシコ先住民のナワトル語での「膨らむ果実」を意味するトマトゥルに由来する。そこからスペイン語の tomate、英語の tomato、ドイツ語のTomate、フランス語の tomate、日本語のトマト、などが派生してきた。アラビア語やロシア語、ヒンディー語も「トマト」に近い言葉らしい。そんな中、異彩を放つのが、イタリア語の「ポモドーロ」だ。
ポモドーロという名前には馴染みがある。なぜポモドーロなどという単語を知っているかというと、イタリア語を学んだから、という訳ではなくて、仕事や勉強の効率を上げるためのポモドーロ・テクニックを導入していたからだ。きわめてシンプルで、ネットなど外部からの情報を完全に遮断して25分間集中、そして5分間休憩する、という時間管理法である。このワンセットを1ポモドーロという。
なぜポモドーロ・テクニックと言うかというと、最初に考え出したイタリア人がトマト型のタイマー――ゼンマイ式でぎゅっとひねったらチッチッチッと回るやつ――を利用したからであって、たいした意味はない。探してみたのだが、日本ではポモドーロ型のタイマーはあまり売られてなくて、リンゴ型とか卵型がメインである。
人にもよるだろうが、私の場合は、この方法を導入することによって2倍近く生産性が向上した。紹介したHPもたくさんあるので、興味ある人はぜひやってみてもらいたい。スマホ計時でもいいのだが、ぎゅっとひねる時に気合が入るるので、ポモドーロ、あるいは、卵、リンゴ型タイマーがオススメだ。
完全に話がそれた。なぜ、イタリア語でポモドーロというか、であったわい。pomodoro はpomo d’oro = 金のリンゴが転じてできたとされている。トマトは赤いのになんで金やねんと思ったら、黄色のトマトが先に入ってきたからではないかと説明されている。ただ、ムーア人との交易を通じて伝わってきたので pomo dei mori = ムーア人のリンゴと呼ばれていたのが、いつのまにか pomo d’oro になったという説もある。どっちゃにしても、金のリンゴって、むっちゃええ感じやな。
日本にトマトが入ってきたのは17世紀半ばとされていて、当時はトマトじゃなくて中国と同じく蕃茄(ばんか)と呼ばれていた。蕃は外国、茄はナスなので、外国から来たナスという意味だ。ナス科とはいえナスには見えんと思うけど。ヨーロッパでも導入当時そうであったように、最初のころは観賞用で、食べられるようになったのは明治時代になってからのこと。
仲野家定番「イタリアすき焼き」のレシピをお教えします
トマトの花はたいして美しくないのに不思議なことであるわいと思っていたら、花ではなくて実を観賞していたらしい。なるほど、言われてみたら、赤くてぽっちゃりして可愛らしい。野菜可愛らしい選手権があったらトマトがチャンピオンかもしらん。
我が家定番のトマト料理に、イタリアすき焼きがある。もとは徳島出身の料理人・小山裕久さん考案のものだが、我が家のレシピ(というほどでもない)は、以下のとおり。
(1) タマネギとトマトをくし切りにする(ほぼ等量をたっぷり)
(2) 鍋にオリーブオイルを入れて、ニンニクを炒める
(3) タマネギとトマトを敷いて、上からスキ焼用肉をかぶせる
(4) 火を付けて、蒸し焼きのようにする
(5)トマトがとろけだしたら、割り下を入れて煮る
(6) バジルを載せる
なんのことはない、タマネギとトマトがどっさり入ったすき焼きである。卵をつけて食べるかどうかはオプショナルだが、これがやたらと美味しい! だんだんと煮詰まって味が濃くなっていくのがまたよろしい。最後にはスパゲティを投入するか、米を放り込んでリゾットにする。チーズを入れるのも忘れずに。
どうしてイタリアすき焼きかというと、バジルの緑、タマネギの白、トマトの赤が、イタリア国旗の色合いだから。こじつけっぽいけど、それはさておき、ぜひお試しあれ。ということで、次はタマネギに。
家庭菜園で採れたタマネギのオニオンスライスは絶品
各論4番目に登場のタマネギは、偶然、世界で第4位の生産量を誇る野菜である。なのではあるが、作っていて、なんとなく気合が入らんというか、盛り上がらん。タマネギに限らず、ネギ類は地味だ。というか、ひっそりしている。姿形、茎がなくて葉っぱしかないというのがあかんのかもしらん。それをいうなら、キャベツや白菜もそうではないかと言われるかもしらんが、こちらはふっくらしておるし、なんとなく愛想があるではないか。ネギ類、シュッとしすぎ。
タマネギは花をつけることもある。いわゆるねぎ坊主だ。それなりに美しいのだが、タマネギの場合、花が咲いたら失敗で、そうなるまでに収穫せねばならんのである。それに、みじん切りにした時、人間を涙させるなどというのは態度がいささか反抗的である。野菜界の風上にも置けんわな。でも、ちょっと可愛いところもある。収穫時期がわかりやすくて、立っていた葉っぱがくにゃっと倒れて、参りましたという感じになった頃が採り頃のサインだ。
子どもの時分、タマネギが嫌いだった。その恨みが、タマネギに対する厳しい意見につながってるのかもしらん。でも、いまはむしろ好きである。家で作ったタマネギ――これも大きくならなくて直径が市販のものの半分にも満たないけど――がいちばん美味しいと思うのはオニオンスライスだ。
じつは、タマネギを初めて美味しいと思ったのは、お酒を飲むようになってからで、おつまみのオニオンスライスがえらく気に入ったおかげである。70歳近くになってちょっとおかしいけど、オニオンスライスを食べながら、俺も大人になったなぁと思うことがよくある。三つ子の魂百まで、雀百まで踊り忘れず、と同じように、ナカノ百までオニオンスライス。
バジルの和名が「目帚(メボウキ)」とはこれいかに?
ついでにといっちゃあなんだが、バジルについてもちょっとだけ。これは家で作ったものが市販のものよりも圧倒的にいい作物のトップレベルだ。なにしろ香りが違う。それに、買えば結構高いけれど、植えておいたらアホほど育つ。高さが50センチくらいまでと手頃だし、地植えでもプランターでもオススメの野菜である。香りのおかげか、虫が寄りつかないのもいい。でもバジルって野菜なんかしらん?
ハーブというくくりの方がよく使われそうだが、農水省の分類では香味野菜あるいは香辛野菜だから問題なさそう。シソ科と聞いて、納得。いくつかの種類があるけれど、一般的なのは我が家でも育てているスイートバジルで、イタリア料理に使われるのもこれだ。いまごろ気づいたけど、カプレーゼもイタリア国旗と同じ配色やん。ひょっとして気づいてなかったのは私だけか。
イタリア語名はバジリコ、ギリシャ語の「王」であるバシレウスに由来するらしい。なんか、えらいやないか。って、タマネギと扱いが違いすぎるかな。和名を知っている人はほとんどおられまいが「目箒(メボウキ)」という。どうしてそんな名前なのか、おわかりになられるだろうか。これは難易度が高い。
バジルの種子は黒くて小さいごま粒のような感じだが、ものすごく水を吸って、カエルの卵みたいな寒天状になる。デザートに入ってたりする、カエルの卵の小型版みたいなやつだ。目にホコリが入った時にバジルの種子を入れると、水を吸いながら取り去ってくれるから、江戸時代に目箒と名付けられたらしい。そんなん入れたらかえってゴロゴロして痛そうな気がするけど、そんなことないんやろか。
昔、バジルシードダイエットというのをやったことがある。なにを隠そう、私はいろんなダイエットを試すのが好きな、ダイエット入門の達人だ。小さじ1杯くらいのバジルの種を水150mlくらいを入れてふやかし、食前に食べる。そうすると、おなかが膨れてあまり食べずに済むという原理だ。あんまり効果がなかったけど……。
そういえば、同じ原理の寒天ダイエットもやってたことあったなぁ。こっちはある程度効いたが、ちょっとお腹を膨らませてから食べるので、食べ物をあまり美味しく感じられずにやめたんやった。
話は思わぬ方向に展開してしまいましたが、今回は、トマト、タマネギ、バジルと、イタリアすき焼き三兄弟でありました。とはいうものの、トマトすき焼きを作る時に仲野家菜園で作ったのを重点的に使ってるのはバジルだけですわ。トマトもタマネギも、ちょっと量的に足らんから、市場で買ってこねばならんのであります。なんやそれは! と言われるやもしれませんが、今回はこういったところで。
知的菜産の技術
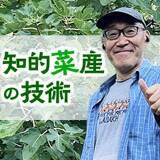
大阪大学医学部を定年退官して隠居の道に入った仲野教授が、毎日、ワクワク興奮しています。秘密は家庭菜園。いったい家庭菜園の何がそんなに? 家庭菜園をやっている人、始めたい人、家庭菜園どうでもいい人、定年後の生き方を考えている人に贈る、おもろくて役に立つエッセイです。
- バックナンバー