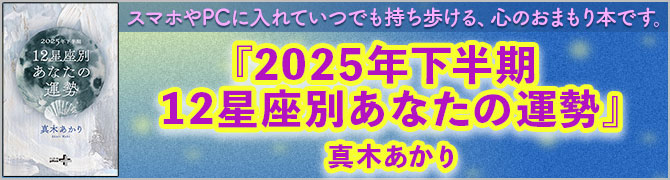「味の豆腐~♪ペッペッペペイ♪」
「3匹の子ブタはお肉を焼くよ~♪チュウチュウチュウ~お花が咲くよ~ダメだよね~これつけるものなんだもんね~」
「メーメーメーメーアイスクリームがあーげーるよーメーメーメー大好きさーアイスクリームがーアイスクリームがーもういくつねるとーマンマママママ(略)」
2歳半を過ぎ、突如クリエイティブの神が舞い降りてきた娘。どうですか、このダダイスティックな自作曲。新しい文学の地平を切り開く子供靴の足音が聞こえてきませんか。
最近、自分の子がめきめき賢くなってきたような気がする。私のiPhoneを勝手にいじって壁紙を自分のキメ顔写真に変更したり、iPhoneで動物や他人の子供の面白YouTube動画を探し出してきてはニヤニヤ笑いながら見てたり、「はい、おかあしゃん、iPhoneさわってていいわよ?」とムリヤリ母の両手にiPhoneを持たせてそのスキに母の乳をまさぐろうとしたり、寝かしつけに聞かされた「寿限無」をいつの間にか暗記していたり。こうしてみると若干偏っているような気がしなくもないけれど、つい思ってしまう。「もしかしてウチの子、生まれながらのパワーエリート?」と。
客観的に見れば、これは親バカ以外の何者でもないのだった。知識人が我が子をあられもなく褒めそやす文章を読むたびに、「ププー、親バカすぎる~。あなたのお子さんだってオカンの前ではウンコもらしガールですよ?」とほくそ笑んでいたのに。だいたい他の2歳児などろくに知っているわけもなく、比較対象はちょっと前までの一点曇りもなく無力でアホの子だった頃の娘で、いわば当社比にすぎないのだから、パワーエリートも何もない。「ウンチしてないよ!」とウンチ臭をだだもらしながらしらばっくれる子を見て、「なぜごまかせると思う!? やっぱりウチの子アホや……」とかろうじて我に帰ることができるのは、育児メイン担当者の特権といえよう。あー、危なかった(親バカトラップに片足突っ込みながら)。
つくづく、ヒトの子とは魔性の生きものである。「無心なかわいさ」という赤子ならではの小悪魔ならぬ小天使テクを駆使するにとどまらず、知恵づくやすかさず「急激に成長する」というカードをきって世の親たちを「さすが我が子は賢い!」とたらしこみ、彼らから自己愛の延長線上の愛情を獲得せしめ、まんまと自らの養育に駆り立てんとする。成人までに手がかかるヒトの子ならではの生存戦略なのだろうか。育児を母親任せにしていた父親が、2歳を過ぎたあたりで急に育児に目覚めたりするのも、この愛されテクのなせるワザに違いない。繁殖するわけだ、人類。
おかげさまで母性本能という言葉とは縁がないまま出産した私も、窓の外へ子供をぶん投げることなく、どうにか普通に子供を育ててこれた。だいたい、母性本能ってなんだ。若い頃を振り返ってみればこの言葉、弱そうな男の子への恋愛局面で使われることが多かった気がする。それがもし本能なら、本能のままに生きている動物たちこそが「ボサボサの羽根……私が毛繕いしてあげたい!」「本当はイイ声で鳴けるのにくすぶっている彼……私が支えてあげたい!」という動機で繁殖活動しててもおかしくないはず。でも実際には羽根ボサボサの孔雀や鳴けないスズムシは、哀れD.T.のまま朽ちていくのみ……。
ヒトの場合、弱い異性に対して庇護欲をそそられることは、男女問わない現象のように見える。思うにこれは「庇護するという形で支配欲を満たしたい」「おぼつかない異性の必要不可欠な存在になることで、自己承認欲求を満たしたい」という、本能と呼ぶにはあまりにこじらした欲望なんではないかしら。また、「男はみな女に母性を求めているのだ」というけれど、この場合求められている母性とは、「オカンのように部屋を漁ってエロ本を勝手に捨てておいてほしい」でも「ヘソの上まであるオカンパンツをはいてほしい」でもなく、「何を言おうが何をしようが許容して無条件で愛してほしい」というもので、一般的なオカンの実勢からはかけ離れているし、ワガママ気味の女の子が言う「包容力のある男性が好き」と何が違うのかわからない。
そんな感じで何かと都合良く使われる「母性」という言葉。未だになんなのか実感できないままだ。『成熟と喪失 母の崩壊』(江藤淳)は確かに名著なのだけれど、近代化で「母性」が「破壊」されてしまったというくだりはいまいち納得しづらかった。ここで言われている無限に他者を受容する「母性」とやらが、生まれつき女性に備わっているものとは思えないのだ。自分のことを振り返っても、子供時代のほうが「世界が破滅して自分以外死んじゃえばいいのに。そしたら好きなだけおやつ食べて好きな本読めるのに」という不寛容にもほどがある欲望を抱えており、近代化というか、社会経験を経て徐々に他者を受容できるようになった気がする。女の子なんて、今も昔も経験値が浅ければ浅いほど許容度が低い生きものだと思うのだけど。「母性」というものがあったとして、それは理不尽な赤子との生活における努力と根性と忍耐で後天的に会得するものなのなんじゃないか。与謝野晶子は昔から姑の嫁いびりが絶えないことを嘆いて、旧世代の無学な老女にも学ぶ場を与えるべきだと主張していたが、これは近代化以前の女性の「母性」が、権威に対する従順さに過ぎず、必ずしも受容力の高さを意味しているわけではないことを物語っている。「子殺し」がメディアを賑わすたびに「最近の母親には母性が欠けている」と識者が嘆くけれども、近代化以前の農村において子殺しが日常茶飯事だったのは、前回見たとおり。
そもそも「母性」という日本語、実は大正時代に生まれた新しい言葉なのだそうだ。婦人の母性的使命を説いたスウェーデンの女性思想家エレン・ケイの著作をフェミニストである平塚らいてう『母性の復興』(1919)と翻訳したのが始まりらしい。女子にも教育の門戸が開かれたものの、社会にその才能を生かす場などろくになく、子供を産めば家事育児に忙殺されて仕事や学問どころではない。自分の理想とはほど遠い現状に悩み抜いていた子持ちインテリ女性たちにとって、「(学のある)女性が子供を立派に育てることで国家に寄与することができる」と謳う「母性」論は大いに励みになったのだろう。
「母性」は鳩山首相の曾祖母にあたる鳩山春子の教育書『我が子の教育』がベストセラーになることで、一般層にも広がっていく。鳩山春子の『我が自叙伝』を読んでみたのだが、この人、現代のカツマーもびっくりのモーレツ勉強家なのだ。幼い頃から学問が大好きだった春子は松本藩士だった父親に気に入られ、明治7年に日本初の官立女学校へ入学する。この学校に入るために父と2人きりで上京した彼女は、家では威張り散らかしていた父が自分を甘やかしてくれることを誇りに思い、どんどん飛び級をして父の期待に応えていく。人一倍賢い娘を親バカ的にかわいがりたいけれど、家父長制の手前できなかった父親像が浮かんでくる。ところが「他の文明国に侮られないよう女にも教育をつけなくては」「女はやっぱりバカなほうがいいよねー」という明治政府のゆれるオヤジ心に振り回される春子。官立女学校が入学3年で廃校になってしまったり、女子師範学科の修業のために米国留学生に抜擢されるも、女子の留学に反対する閣僚のせいで立ち消えになってしまったり。それでも彼女はめげず、夜間でも寝具入れの中に入ってろうそく1本の灯りをたよりに勉強を続けていく。
そんな彼女を見初めたのが、外国暮らしが長かった鳩山和夫。当時の日本男児としては破格にリベラルだった彼は、語学ができて議論を好む春子を気に入ったらしい。不器量なガリ勉である自分と結婚してくれ、姑にいびられないよう周到に根回ししてくれる夫に感謝する春子は、息子2人を立派に育てることで恩に報おうとする。彼女のいう「母性」とは、
母性愛にして完全に啓発さるるなれば、此母性愛実現の為に母自ら自己改善をすれば、その接する人を高く引上げ、その人を美化し、その人を善化するものでございます。(『我が自叙伝』p205)
とあるように、あくまで自己改善して身につけるもの。決して本能なんかじゃないのだ。そして彼女は子供に教育を授ける技術を身につけるべく次男生後4ヵ月で教職に復帰し、夫の仕事をよりよく理解するために勉学に励んだのだと語る。あれ?結局大好きな勉強をしているだけなんじゃ……と思わなくもない。「世の多くの日本婦人の様に世辞もなければ遠慮もなく、礼儀にも詳かならず、まるで男子の如き言語挙動」で、母に「どうしてこんなに不別嬪に生んで下さいました」と詰め寄るほど女子力に自信のなかった彼女が、カツマー的な自分を肯定するためのよりどころ、それが「母性」だったのだろう。
「美貌と精神修養」という章では、淀君を例に挙げて精神的教育をろくに受けなかった美人が地位の高い夫を操ることで世を滅ぼしている、とおバカな美人批判まで繰り広げている。これには平塚らいてうのような美人にはほど遠い大正時代の一般婦人も、大いに勇気づけられたことだろう。今も昔も、「女の子はおバカがいいよね」というのが世の趨勢で、そこから外れた女子はさまざまな戦術をとらざるをえないのだなあ、ということがよくわかる。非モテ女子のための新しい生き方だったはずの「母性」が、時代を下って女子力に吸収されてしまったのは皮肉なことだけれど。
鳩山春子の二人の兄弟に対する教育方針も面白い。とにかく公平を重んじ、一方の誕生日には二人を祝ってそれぞれに金銭を与え、兄が高等学校に入学してからは弟にも小遣いを平等に渡したという。この教育方針がひ孫の世代まで伝わり、例の9億円お小遣い事件が生まれたのだろうか。かつて桂正和好きをカミングアウトしたこともある、歴代首相随一の萌え首相のルーツはここにあるのだろうか。母子密着と萌えを巡るオカンの旅はまだまだ続くのです。
文化系ママさんダイアリー

フニャ~。 泣き声の主は5ヶ月ほど前におのれの股からひりだしたばかりの、普通に母乳で育てられている赤ちゃん。もちろんまだしゃべれない。どうしてこんなことに!!??
- バックナンバー
-
- 「3歳児の人間模様とあれこれ」の巻
- 「生殖の人、石原慎太郎の教育論」の巻
- 「文化系の遺伝子戦略」の巻
- 「コスプレ嫌いの七五三」の巻
- 「私の中のカツマーVSカヤマー論争」の巻
- 「ショッピングモールからテン年代を考える...
- 「間違いだらけの『絵じてん』選び」の巻
- 「『アーティスト枠』に生まれて」の巻
- 「イヤイヤ期の終りに思うこと」の巻
- 「2歳児の笑いのツボを考える」の巻
- 「女の子の絵本、男の子の絵本」の巻
- 「ママさん的iPad活用法~お料理レシピ...
- 「『冷たい怒り』とギスギスする女たち」の...
- 「ゴシップ読書から学ぶ家庭マネジメント」...
- 「ママと煙草と男と女」の巻
- 「タコ公園から考える公園遊具問題」の巻
- 「モヤモヤ育児雑誌クルーズ~『主婦之友』...
- 「自動車CMとママさんのキュンキュンしな...
- 「母性と本能が出会った頃」の巻
- 「『母性』という戦略」の巻
- もっと見る