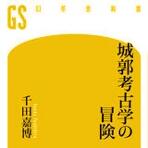今、私たちが目にする天守(天主)をもった城郭は、信長の城に端を発したといえます。では、なぜ信長は山頂に高層の天主を建てたのでしょうか? その狙いとは何だったのでしょうか? 信長の城づくりから信長が目指したものを読み解きます。
好評発売中の『城郭考古学の冒険』から一部を試し読みとしてお届けします。
* * *
絶対的な超越者としての信長
従来は文献史学による研究分野と一般に認識されてきた戦国・織豊期の研究も、遺跡としての城から多くのことを明らかにできるようになった。たとえば織田信長が初期に居城とした清須城(愛知県)、那古野城(愛知県)は、館型の城が横並びに連結してできており、ゆるやかな階層性を備えた城であった。こうした城郭構造は広く戦国期の城郭に共通したもので、大名と家臣との連合・分立的な権力を反映した。
信長はその後、一貫して自分自身を絶対的な超越者として家臣と人びとに臨むことを目指した。小牧山城(愛知県)→岐阜城(岐阜県)→安土城(滋賀県)と、居城を移転するにつれて、城内における信長と家臣の屋敷との隔絶性が深まっていった。信長は、山城への生活・政治・軍事の統合を果たした上で、家臣と横並びの関係を払拭していった。新たな城の築城は軍事的な要請だけではなく、信長が家臣に超越する信長の目指した政治と社会のあり方を具現化し、定着させる手段としての意味をもった。
そうした信長の意図を信長の城はみごとに示した。それは越前国主にした柴田勝家に与えた一五七五年(天正三)の越前国掟にもうかがえる。「とにもかくにも我々を崇敬して、影後にてもあだにおもふべからず。我々あるかたへは足をもささざるやうに心もち簡要に候。其分に候へば侍の冥加ありて長久足るべく候」と断言した(『信長公記』巻八)。つまり信長は、信長を頂点に武士たちが結集した社会を建設しようとしていた。だから信長の城は、同時代の戦国期拠点城郭と比べて極端に求心性を強く指向した。
信長の城に見られた、信長による石垣の独占使用(小牧山城)、信長と家族との居所であった山城の圧倒的な隔絶(岐阜城)、高石垣の集中使用(安土城)といった特徴は、まさに信長の政治的特性と不可分の関係にあり、信長の城を軸として戦国期拠点城郭のなかから近世城郭が出現したことを物語る。
さらに安土城では、幾重にも重ね築いた石垣で最も守られ、城郭構造としても、安土山の山頂という空間的な位置としても文字通りの頂点に、高層の天主を建てた。信長は天主を御殿の一部としてそこに住むことで、天主を信長と自らの政権が目指すもののシンボルとした。すべての家臣屋敷と城下にくらす人びとの頂点に天主が君臨した。安土城の強力な求心的な城郭構造は、まさに信長を頂点にした新たな社会の構造を象徴した。

信長の城は、もちろん軍事的な要請や戦略目標にもとづいていたが、一貫して家臣を一元的に編成し、社会を変えていく手段であった点に特徴があった。そして、信長の城づくりを豊臣秀吉、徳川家康が受け継ぎ、さらにそれぞれの家臣が自らの居城に取り入れたことで、近世城郭は信長の城に端を発した大名を頂点としたきわめて強い求心構造を、等しく共有することになった。戦国期に日本列島を広く覆っていた横並びの城は、織豊期に一斉に階層的な織豊系城郭へと変化したのである。
つまり大名が住み、天守を備えた本丸を頂点に、二の丸・三の丸と身分に応じて家臣が順次屋敷をもち、その外に町人や商人、寺院を配置した典型的な城下町の全国的な成立であった。今ではあたりまえのように考えられている近世の身分制に照応した城と城下の構造は、信長の城に端を発したといえる。
そして信長の城は、単に天守や瓦・石垣を用いはじめたという近世城郭の表層の特色を規定しただけでなく、近世の社会のあり方そのものを規定した点に、歴史的意義と画期性があった。だから中世城郭と近世城郭との違いは、天守や石垣、礎石建物、瓦の有無ではなく、社会構造に連動した求心的・階層的な城郭構造の成立に求められる。城郭構造そのものに近世城郭の本質的意義があったから、石垣がなくても、天守を途中で失っても、近世城郭は城としての機能と政治的象徴性を発揮しつづけた。