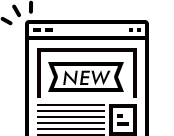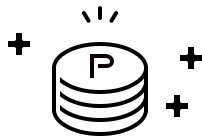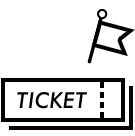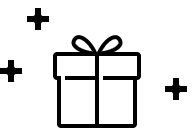プロレスラーには限界から先の姿を見せていく使命がある――。
新日本プロレスのスター選手として活躍後、アメリカのプロレス団体「AEW」でも躍進を続ける“レインメーカー”オカダ・カズチカが人生の極意を記した書籍『「リング」に立つための基本作法』より、一部を抜粋してお届けします。
きついトレーニングに耐えきれず送った母へのメール
〈闘龍門をやめて、安城へ帰ろうと思う〉
15歳で闘龍門に入門して一ヵ月も経っていないころ、母親にメールを打った。トレーニングがきつすぎて、これ以上は続けられない、もう限界だと感じていたのだ。プロレスラーになることをあきらめようと本気で思っていた。

スクワットや腕立て伏せ、どれもきつくて、どれも同期生たちのようにできなかった。僕ができないと、連帯責任で仲間たちに迷惑をかけることがなによりもつらかった。
練習中は水が飲めない。それも苦しかった。
トレーニングとトレーニングのインターバルに、トイレに行くことは許されていた。トイレの便器のなかには水がある。水面がゆらゆら揺れている。それを飲んじゃおうかとまで思った。
「つらかったら、いつでも帰っていらっしゃい」
神戸にある闘龍門に入るために安城の家を出るとき、母親に言われていた。だから、受け入れてもらえるだろう、と安易に考えていた。
ところが、母親の反応は僕の期待とは違っていた。
〈もう少し頑張りなさい〉
レスポンスが来た。がっかりした。
〈えー! 話が違うじゃない!〉
そうメールをしたかったけれど、懸命に我慢した。
とにかくもう少し頑張ろう、と決めた。
なぜならプロレスラーになる道をあきらめたら、僕にできることはなにもない。今さら高校へも行かれない。中学時代の友だちの後輩になってしまう。そもそもプロレスのほかに、やりたいことなどなかった。
子どものころの僕は足は速かった。でもマット運動だけは苦手だった。せいぜい前転、後転まで。開脚前転はできなかった。もたもたしている僕を横目に、友だちはヘッドスプリングやネックスプリングをやっていた。どうしても僕はみんなにマット運動で勝てなかった。
では、なぜプロレスラーになろうと思ったのか──。
笑われるかもしれないが、ある夜、僕は夢を見たのだ。
夢のなかで、僕はプロレスのリングのなかにいた。闘おうとしていた。相手は屈強なレスラー。そして……勝ってしまった。
試合のプロセスは覚えていない。どんな技で勝ったのかも覚えていない。それなのに、勝ってレフェリーに握られた手を上げているシーンは鮮明に記憶している。
目覚めた僕はプロレスラーになると決めたのだ。
揺らぎそうなときは退路を断て
単純な僕は、その日からもくもくとスクワットを始めた。やり方はわからなかったので、なんとなく想像で、膝の屈伸運動を続けた。
筋トレが必要だろうと思い、ジムにも入会。近所のジムは15歳では会員になれない。安城市の体育館も利用できない。そこで兄の名前を借りてなりすました。
学校の授業中は居眠りかプロレスのマスクをつくっていた。でも、テストでいい成績だったらプロレスのビデオを買ってくれる、と母親が約束してくれたので頑張った。結果、いい成績で、ビデオを買ってもらった。通知表もよかった。
そんな僕を両親は闘龍門に送り出してくれた。初期費用は、入学金と半年分の学費で72万円だったと思う。
プロレスをやめたら、その後生きていくためにどんな仕事をするのか、なにも思いつかなかった。だから母親に「帰ってくるな」と言われたら、闘龍門の寮と道場のほかに、いる場所はない。
僕には退路はなかった。安城へ帰る選択などできなかったのだ。そのことを母親からのメールで再認識した。
やめる人とやめない人、どこが違ったのか──。
今思うと、根性や忍耐力よりも、まずプロレスが心底、ほんとうに好きなのか、そうでないかの違いだったのではないか。そしてもう一つ、プロレスのほかに人生の選択肢があるかないかの違いだった気がする。
やりたいことがあるなら、自分の目標が明確ならば、そしてその大切な目標へ向かう気持ちが揺らぐのを避けるには、退路を断つべきだ。
ちなみに苦手だったマット運動は、闘龍門の練習生だったときはなんとかできるという感じだったが、メキシコに行ってから、どうやったら自分の思うように身体を動かせるかを教えてもらった。それは今にすごく活きている。
* * *
この続きは書籍『「リング」に立つための基本作法』でお楽しみください。
「リング」に立つための基本作法

もうダメ限界! と諦めた、そこから先が人生を分けていく。
マインドを鍛えるスクワット法から、SNSとの付き合い方、後輩体質のコミュニケーション力、そしてスーツや日記の効用など、老若男女、誰もが自らの「リング」に立つためにヒントとなる、オカダ流人生の極意の数々。