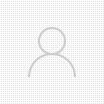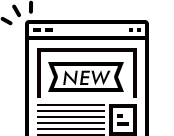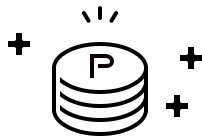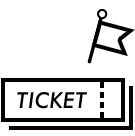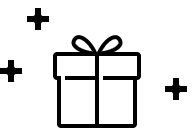時は大正。舞台は日本で最も美しい監獄。言われのない罪で監獄に投獄された数学教師と印刷工が、頭脳と胆力で脱獄を目指すバディ小説、『奈良監獄から脱獄せよ』の、試し読みをお届けします。
(1話目から読む方はこちらから)
* * *
「496号、勝手にしゃべるな」
「申し訳……」
「だから、俺に口を利くな。こっちは看守だ。おまえから話しかけてきたら、いちいち注意しなくちゃならん。わかったな?」
僕たちを監督する看守は二種類いる。それなりに僕らを人間扱いしてくれるやつと、完全にごみだと思って見下してくるやつだ。
基本的に囚人と看守は立場的に相容れないが、片岡は比較的囚人に対しても寛容で、こういうときも噛んで含めるようにゆっくりしゃべる。
「わかりました。どういうときなら話していいんですか?」
「どうって……ああ、もう、いい」
囚人たちの漏らすくすくす笑いが、天井の高い工場に漣のように広がっていく。
板張りの工場は二階にあり、天井の骨組みが素通しで見えている。風通しがよいが、そうでなくとも冷え込む奈良の冬ではよけいに寒く、今も手がかじかんでいた。
「とにかく、おまえに任せる。いいな、センセイ?」
「はい」
ほかの嫌みな看守に比べたら片岡はましな部類だが、それでも、『センセイ』という発音には、僕に対する微妙な感覚が透けている。
僕の罪状は、殺人罪だ。
聞けば、女学校の教師が教え子を絞殺したという一大醜聞は、地元紙だけでなく全国紙の紙面をもにぎわせたそうだ。そのうえ、強姦したなどという尾鰭もついていたとか。あまりに有名なので、僕のあとに入獄した連中はたいていあの事件を知っている。何でも、大正六年の重大事件の一つにも数えられたらしい。

女子供に手をかけるのが最も軽蔑されるこの監獄で、僕はほかの囚人や看守から蛇蝎のように嫌われていた。
心情的にいえば、罪は496号よりも重いかもしれない。
そんなわけで、僕は監獄という一種の独立国では、完全に浮き上がっていた。
ここでは人に言えない過去や臑すねに傷を持った囚人たちが、規律で雁字搦めにされ、集団生活を送っている。娯楽に飢えた彼らにとって、僕のような罪状の人間は鬱憤を晴らす格好の標的だ。
多くの囚人たちが抱える気性の荒さは、僕にとって嫌悪と恐怖の対象で、一緒にいるのは落ち着かなかった。
取り分け、目の前にいる496号は終身刑の極悪人だ。
機嫌を損ねたら半殺しにされるかもしれないし、気をつけて接しなくては。
一度深呼吸をして、気持ちを切り替える。
僕はぽつねんと佇む496号に視線を向けて、「来てくれ」と促した。
「はい」
作業場の片隅に、使っていない『丸台』が雑然と積まれている。監督者に声をかけて組み玉と糸束を受け取り、帳面に記録をしてもらう。
「これが君のだ」
「はい」
片岡が噛んで含めるように言ったとおり、原則として僕たち囚人は私語厳禁だ。
とはいえ、囚人同士が作業中に無駄口を叩くのは、よほどまずい内容でなければ目こぼしされていた。つまり、私語厳禁はある程度は建前だ。
だが、暗黙の了解で話していいことといけないことは分類されている。
たとえば、看守の悪口や待遇への不満。他人の悪口も避けたほうがいい。それから、脱走計画なんて冗談でも口走ってはいけない。看守に知られたら、場合によっては懲罰房である『丸房』に送られる。この丸房の環境が劣悪で、一日二日そこに入れられただけで、囚人は牙を抜かれたような顔になって戻ってくるのだ。
496号の頭がよければ、さっき片岡が発した言葉の裏には、『ほかの囚人はともかく、看守には話しかけてくれるな』という真意があるとわかるだろう。それを察するかどうか、僕は少し意地悪な気持ちで彼を観察しようと決めた。
そもそも、この奈良監獄では九百人あまりの男性の囚人を、たった百人の看守で制御して運営が成り立っているのだ。何かことが起きれば、絶対的に数が多い囚人が勝つに決まっている。
数のうえで圧倒的優位に立つ囚人が反抗せずに従っている理由は、看守が武器を持っていることと、僕たちが足並みを揃えた行動ができないことだった。看守側は数が力になると知っているので、九百人を一度に集めるような愚かな真似はしない。それぞれのグループを細分化し、私語を禁じて意思の疎通を封じている。
それでも、囚人たちが抑圧に耐えかねて暴動でも起こせば大ごとになるだろう。だからこそ、多少の私語は黙認されていた。
「組み紐は初めてか?」
「ハジマです。羽嶋亮吾」
初めてかどうかを聞いたのに、返ってきたのはまったく求めていない情報だった。
「羽嶋のハは鳥の羽で、シマは難しいほうの……左に山がつくシマです」
羽嶋は笑うと右の頬にえくぼができて、黒目がちの目が和んで顔がくしゃっとなる。図体の大きな子供みたいだ。年齢も二十歳そこそこくらいだろうか、たぶん僕よりも年下だ。
「必要ない」
「えっ?」
相手が怒らないことを確認してから、僕は言葉を続けた。
どうやら彼はおとなしい部類のようで、僕が教師として振る舞っても文句はないようだ。
「ここでは、称呼番号にさん付けをするんだ」
「称呼番号」
「僕は421号で、君は496号だ」
僕が指で胸に書かれた称呼番号を指すと、羽嶋は「ああ」と納得したように頷く。
「同じ房の人は教えてくれたんです。林さん、納富さん……」
意外にも、羽嶋は『四監』では珍しい雑居房に入れられたようだ。

「私語は禁止だ」
「けど、これからいろいろ指導してくれるんでしょう? そういう相手にお礼を言ったり名前を聞いたりするのは、ただのおしゃべりとは違うと思うんです」
「それは屁理屈だ」
ああ言えばこう言う、なんて面倒な生徒なのか。
「待ってください。今みたいのが、私語じゃないですか?」
羽嶋に真顔で問い返されると、僕は困ってしまう。
「揚げ足を取らないでくれ」
羽嶋は上背も肩幅もあって体格は僕よりもずっと立派で、筋肉もしっかりついている。人懐
っこい表情のせいか威圧感はないが、殴られたら僕なんて吹っ飛びそうだ。これなら、外役──外での工事に行かせるか、もっと大きな家具製作などの作業をやらせたほうがよさそうだ。
なのに地味な内職を割り振るなんて、管理側も無期刑の凶悪犯に対して様子見を決め込んでいるのかもしれない。
「でも、名前くらい教えてくれたって」
「だめだ」
僕は冷ややかに答えたが、後ろの席から「そいつは弓削だよ。弓削センセイ」とほかの囚人がよけいな口出しをしてくる。
「ありがとうございます!」
何が嬉しいのか、羽嶋は声を弾ませた。
「そっか、弓削さんは本物の先生なんですね。すごいなあ!」
「もういいだろう。続きだ」
「はい!」
それもこれも看守の仕事なのに、どうして僕が新人教育を任されなくちゃいけないのかと、忌々しくなってきた。
けれども、立場的に反抗はできない。
ここでの作業は、僕たちにとっては立派な仕事だ。適性のある内容を割り当てられ、その実績や生活態度を定期的に評価される。
監獄の責任者である『典獄』の覚えがよければ恩赦の対象に推薦され、刑期短縮の道も開ける。
しかし、飴があるなら、当然鞭もある。成績を盾にされれば、僕たちは看守に尻尾を振らざるを得なかった。
また、中には看守の心証をよくするため、他人を蹴落とそうと企むやつもいる。
ここでは、看守の言うことは絶対だ。国が決めた『監獄則』という法律はあるが、運用は管理側のさじ加減次第の面を持つ。
僕も、この監獄に組み込まれた一つの歯車にすぎなかった。
奈良監獄から脱獄せよ

8月23日刊行の、和泉桂さん初めての一般文芸作品『奈良監獄から脱獄せよ』の試し読みをお届けします。
- バックナンバー
-
- 和泉桂×前畑洋平×元刑務官クロストーク#...
- 和泉桂×前畑洋平×元刑務官クロストーク#...
- 和泉桂×前畑洋平×元刑務官クロストーク#...
- 四-5 羽嶋の罪は、冤罪だったのか――。
- 四-4 羽嶋の罪状を知り、弓削は失望を覚...
- 四-3 なぜ、僕の行く先々に羽嶋がいるの...
- 四-2 羽嶋の教育から解放されて訪れた、...
- 四-1 監獄でも陽気な羽嶋に、自分とは違...
- 三-7 自由を求めるのは、人として当然の...
- 三-6 粗暴な囚人に誘われても、勝算のな...
- 三-5 今後18年、単調な日々を繰り返す...
- 三-4 無期懲役週とは思えない天真爛漫さ...
- 三-3 寧子が残したもう一通の手紙とは一...
- 三-2 面会にあらわれたのは、事件の検事...
- 三-1 冤罪を晴らしてくれるかと思った新...
- 二-5 警察の取り調べも裁判も、力がある...
- 二-4 ほかの囚人と交わらないと決めたは...
- 二-3 凶悪犯であっても、誰かにものを教...
- 二-2 完全数で無期刑の凶悪犯は、人懐っ...
- 二-1 無実の罪で投獄されたのは、難攻不...
- もっと見る